「不動産の個人売買は誰でもできるの?」「不動産の個人売買はおすすめ?」など、不動産の個人売買に興味はあるけれど、不安や疑問を抱えている方もいるでしょう。
不動産の売買は、不動産会社に依頼するのが一般的ですが、知人に売却したい、手数料を削減したいなどの場合、個人売買も選択肢です。
結論からいえば、不動産の個人売買は可能ですが、さまざまなリスクも存在します。
本記事では、不動産の個人売買のメリットやデメリット、やり方、安全に取引するための注意点などを詳しく解説します。
不動産の個人売買を検討している方は、ぜひ本記事を参考に、自身にメリットのある取り引きかを確かめましょう。
不動産の個人売買は資格がなくてもできる

不動産仲介業者は宅地建物取引業法における許可がなければ不動産取引ができませんが、個人売買は無資格でも取引可能です。
しかし、不動産の売買は必要書類が多く、手順や法律も複雑なため、専門知識なしに取引を進めるのは難しいでしょう。
法律に対する詳しい知識がない方の取引では、売買成立後のトラブルも頻繁に起こります。
また、不動産の適正価格を把握しなければ、取引相手を見つけることすら簡単ではありません。
不動産の個人売買をはじめる前に、手間やリスクを正しく理解しましょう。
不動産を個人売買するメリット3選

不動産の個人売買にはリスクがつきものですが、少なからずメリットもあります。
ここでは、不動産を個人売買するメリットを3つ紹介します。
今後、不動産の個人売買をする可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。
不動産会社に支払う仲介手数料が不要
不動産を個人間で売却すれば、不動産会社に支払う仲介手数料が不要になります。
仲介手数料は売買する不動産の価格に比例して上がり、高額な場合は数百万円必要なケースもあるため、個人間で売却すれば節約につながります。
参考までに、不動産売却時の仲介手数料上限を次の表にまとめました。
| 不動産売買価格 | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|
| 400万円超 | 物件価格×3%+6万円+消費税 |
| 200万円超400万円以下 | 物件価格×4%+2万円+消費税 |
| 200万円以下 | 物件価格×5%+消費税 |
売却価格ごとの仲介手数料の一例は、次のとおりです。
| 売却価格 | 仲介手数料(税込) |
|---|---|
| 1,000万円 | 396,000円 |
| 2,000万円 | 726,000円 |
| 3,000万円 | 1,056,000円 |
| 5,000万円 | 1,716,000円 |
上記の金額を見てわかるとおり、不動産売却時の仲介手数料の負担は大きいため、支払わなくてよいことはメリットといえます。

自身の意思で自由に売買できる
不動産を個人で売買する場合、不動産会社の介入を受けず自由に進められるため、価格設定や売却時期などを自身の都合で設定できます。
不動産会社を使用すればプロに任せられる安心感がありますが、その分少なからず指図を受ける可能性が高く、自由度が減ることも事実です。
個人売買ではプロからのアドバイスを受けられないぶん、自由度が高い取引ができます。
知り合いに売却しやすい
知人への不動産売却を考えている場合は条件交渉がまとまりやすく、不動産会社の手助けが必要ないケースが多いため、個人売却しやすい傾向があります。
不動産会社の仲介が入らないことで、手数料が削減できるのみでなく、速やかな売却ができるケースも考えられます。
そのため、すでに知人への売却が決定していれば、個人売買を進めてもよいでしょう。
不動産を個人売買するデメリット3選

不動産の個人売買にはリスクがつきものであり、複数のデメリットがあります。
リスクやデメリットを知らずに個人売買をはじめると、売買できないのみでなくトラブルに巻き込まれる恐れもあります。
不動産の個人売買を検討中の方は、デメリットも確認しましょう。
買主とトラブルになるリスクが上がる
不動産を個人売買すると、買主とトラブルになる可能性が高まります。
たとえば、価格交渉の際に相場から離れた金額を提示されても、不動産会社からのアドバイスを受けられないため気づかず損をすることが考えられます。
さらに、認識の相違や必要書類の不備などが起こりやすいことも実情です。
個人売買をトラブルなく進めるためには、細心の注意と知識、買主への気遣いが必要です。

売買に手間がかかる
不動産を個人売買すると必要な手続きや作業をすべて自身でおこなう必要があり、仲介業者に任せるよりも手間がかかります。
たとえば、価格設定に関しても相場の調査も1から進めるため、仲介を依頼した際よりも時間がかかるでしょう。
さらに、手続きや書類の作成、買主との交渉など、トータルの作業量は計り知れません。
不動産の個人売買にはメリットも多くありますが、すべての作業をやり切れるか確認してからはじめましょう。
買主を見つける難易度が上がる
不動産の個人売買は、買主を見つける難易度が仲介業者に依頼するよりも上がります。
不動産会社は広告媒体や他の仲介業者とのコネクションがありますが、個人売買では自身のつながりや知恵のみで買主を探さなければなりません。
知人への売却が決定している方なら問題ありませんが、1から買主を探す方は苦戦を強いられる可能性があります。
個人売買で不安があるならファンズ不動産へ相談しよう
不動産の個人売買は、仲介手数料がかからないというメリットがある一方で、契約内容の確認や税金の扱い、トラブル発生時の対応など、専門知識が求められる場面も多くあります。
「本当にこの条件で大丈夫?」「手続きに抜け漏れがないか不安」と感じる方も少なくありません。安全に取引を進めるためには、リスクや必要な手続きを正しく理解しておくことが重要です。
不安がある場合は、早めに専門家へ相談することで、安心して判断できるようになります。ファンズ不動産では、個人売買に悩む方の相談にも丁寧に寄り添い、状況に合った進め方をサポートします。
フォロワー数万人のキュレーターがあなたの物件を紹介
ファンズ不動産は、キュレーターのSNS発信を通じて「情報拡散力」と「信頼性」を掛け合わせ、物件の売却可能性を広げます。
例えば、同社キュレーターのJeremy Tsang氏は、Instagramで8万人以上(2023年9月時点)のフォロワーを有しています。
影響力の高い専門家が「おすすめできる家」としてSNSで紹介することは、キュレーターを信頼するフォロワーへの「価値ある情報」として届きます。
この独自の仕組みが、高い反響とスピーディーなマッチングを生み出す秘訣です。
「SNS不動産®」であなたの物件価値を最大化
SNS不動産®では、専属キュレーターが物件のスペック情報だけでは伝わらない「不動産の真の価値」をSNSで発信します。
これにより従来の広告でリーチできなかった、物件の魅力に共感する潜在的な買主候補へ情報を届けることが可能です。
特に物件への感度が高い20〜40代の若年層や女性層への訴求に強く、キュレーターが買いたいユーザーの価値観に響く物件のポテンシャルを発信することで、新たな買主候補を見つけ出すことができます。
一般的な情報発信だけでは埋もれがちな魅力を「価値」として明確に伝えられるため、最適な買主候補を見つけたい方におすすめです。
購買意欲の高いユーザーへ能動的にアプローチできる
ファンズ不動産が運営する「SNS不動産®」は、LINEで購買意欲の高いユーザーに不動産情報を届けます。
従来のポータルサイトで「待つ」のではなく、1万人超のLINE登録者へ能動的にアプローチできる点は大きな強みです。
さらに都心に精通した担当者が的確な売却戦略でサポートするため、物件の魅力を最大限に引き出す価格設定と販売活動がおこなえるでしょう。
購買意欲の高いユーザーへ「届ける」力と、物件価値を引き出す「専門家の戦略」が組み合わさることで、「高く・早く」売却できる可能性を最大化できます。
不動産の個人売買に必要な書類
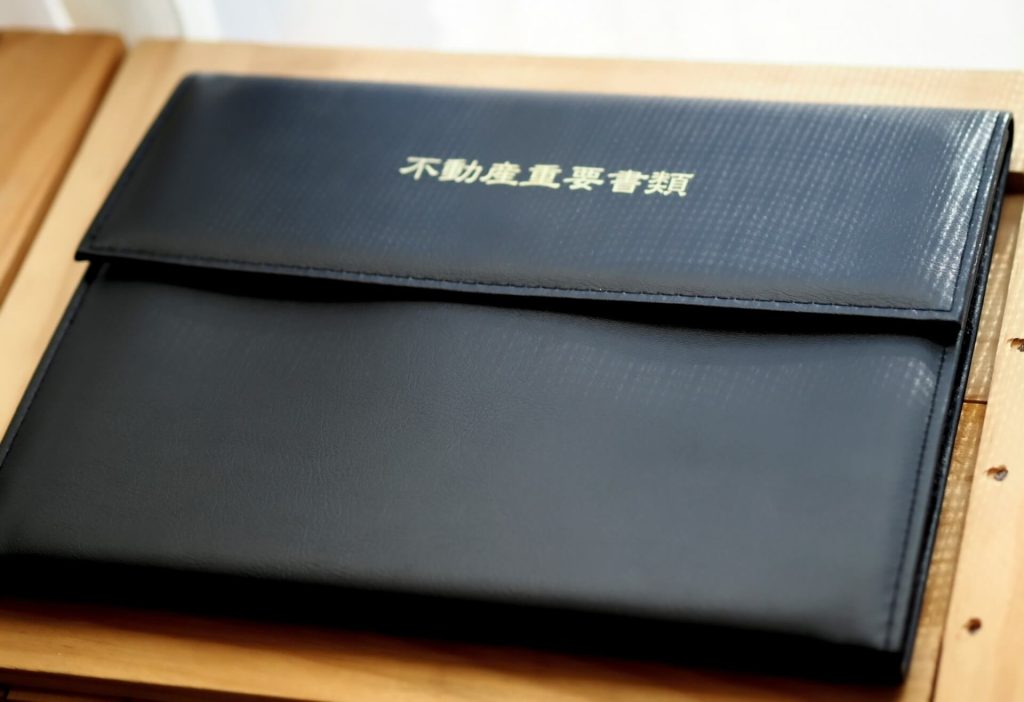
つづいて、不動産の個人売買に必要な書類を紹介します。
売主側と買主側それぞれの立場に分けて紹介するため、ぜひ参考にしてください。
売主が準備する必要がある書類
不動産売買で売主側が準備する必要がある書類は次のとおりです。
- 全部事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産税評価額証明書
- 公図
- 不動産売買契約書
- 登記済証か登記識別情報通知書
- 建築確認通知書
- 印鑑登録証明書
- 領収証
- 本人確認書類
- 実印
不動産の売主は、建物や土地、税金関係の書類を準備しなければなりません。
買主が準備する必要がある書類
不動産売買で買主側が準備する必要がある書類は次のとおりです。
- 住民票
- 本人確認書類
- 印鑑登録証明書
- 実印
不動産の買主は、基本的に本人に関する書類のみ準備すれば問題ありません。

不動産を個人売買するときのやり方や流れ

不動産を個人売却する際は、次の手順で進めます。
- 不動産の状態を把握する
- 不動産の売買価格を決める
- 不動産を売り出す
- 買い手と売買条件を交渉する
- 買い手と売買契約を結ぶ
- 買い手に不動産を引き渡す
- 確定申告をおこなう
各ステップの進め方を詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。
1.不動産の状態を把握する
まずは、不動産の状態を把握しましょう。
不動産の状態を把握していなければ、買い手に正しい説明ができず、売却後にトラブルが発生する可能性があります。
不動産を売却する前に確認するべき項目は次のとおりです。
- 建物の状況(劣化や破損など)
- 土地の境界線
- 建物と土地の面積
- 土地の名義人
建物の状態については「ホームインスペクション(住宅診断)」を活用すると細部の状況までわかります。
また、土地面積の測量図(地積測量図)で土地の境界線を確認し、全部事項証明書(登記事項証明書)で名義人も明確に把握しておきましょう。
地積測量図や全部事項証明書は、法務局で取得できます。
2.不動産の売買価格を決める
不動産の状態を把握したら、売却価格を決めましょう。
売却価格は、買い手の付きやすさを左右する大きなポイントで、相場よりも高すぎるとほかの不動産に買い手が流れる可能性が高まります。
反対に、相場よりも安すぎる売却価格にすると「なにか問題がある不動産なのでは?」と買い手に不安を抱かせる恐れがあります。
高すぎても安すぎても売買に支障をきたす可能性があるため、次のサイトを活用して相場に合わせた価格を設定しましょう。
- 一括査定サイト
- 不動産ライブラリ
- レインズマーケットインフォメーション
複数のサイトでデータを集め、適切な価格設定を心掛けましょう。
3.不動産を売り出す
売却価格を決めたら、個人売買専門のサイトに広告を出し、不動産を売り出します。
個人売買専門のサイトは手数料やサポート内容が異なるため、複数のサイトを比較しましょう。
不動産の知識を持ったエージェントからサポートを受けられるサイトもあるため、有効活用すれば知識が少ない方でも効率よく進められます。
不動産の広告を出す際のポイントは、次のとおりです。
- できる限り多くの写真を載せる
- 明るくキレイに撮れた写真を載せる
- 不動産や周辺環境のメリットをアピールする
多くの方に興味を抱いてもらうため、広告の作成にはこだわりましょう。
4.買い手と売買条件を交渉する
不動産の購入希望者が現れたら、売買条件をすり合わせます。
購入希望者とは、売却価格のみでなく引き渡しの時期、契約内容の取り決めも必要です。
買い手が不動産値引き交渉をしてきた場合は、設定している売却価格の根拠を示し、双方が納得できるようにまとめることが大切です。
買い手と取り決めた事項は、売買後のトラブルを防ぐためにも、細かく売買契約書に記載しましょう。
5.買い手と売買契約を結ぶ
不動産の売買条件がまとまれば、契約書を用いて買い手と売買契約を結びます。
契約書を作る際には、トラブルを防ぐために次のポイントを押さえましょう。
- 不動産に適した契約書のひな形を使用する
- 売買条件は小さなことでもすべて記載する
- 収入印紙を貼り付けて割印する
契約書のひな形は、インターネットで手に入るもので問題ありません。
土地と建物を売買する場合は「不動産売買契約書」、土地のみを売買する場合は「土地売買契約書」など、契約形態により契約書の種類が異なります。
さらに、売買契約の締結には次の書類も必要です。
| 書類 | 取得方法 |
|---|---|
| 全部事項証明書(登記事項証明書) | 法務局 |
| 測量図・公図 | |
| 住民票 | 市役所・区役所 |
| 印鑑登録証明書 | |
| 固定資産税評価額証明書 | |
| 身分証明書 | 自身の所有物 |
| 登記済権利証(登記識別情報) | |
| 建築確認済証 | |
| 購入時の売買契約書・重要事項説明書 | |
| 納税通知書(固定資産税・都市計画税) | |
| 耐震診断・リフォームに関する書類 |
スムーズに契約を進めるためにも、準備漏れがないように注意しましょう。
6.買い手に不動産を引き渡す
売買契約を結んだら、買い手と取り決めた日までに不動産を引き渡します。
引き渡し時の手順は次のとおりです。
- 買い手から代金を受け取る
- 所有権移転登記をおこなう
- 住宅ローンを完済する
- 抵当権抹消登記をおこなう
- 不動産の鍵を買い手に引き渡す
所有権移転登記は不動産の所有者を買い手に変更する手続きで、司法書士に代行してもらうか、法務局に直接申請します。
所有権移転登記にかかる登録免許税や、抵当権抹消登記にかかる費用は、買い手が負担するケースが一般的です。
なお、住宅ローンの完済と抵当権抹消登記は、住宅ローンの残債がある場合にのみ必要です。
7.確定申告をおこなう
不動産を売却した翌年には、譲渡所得税を納めるために書面やオンラインで確定申告をおこなう必要があります。
譲渡所得税とは不動産を売却した際の所得にかかる税金で、不動産の売却金額から、次の項目をマイナスし、一定の税率をかけて算出されます。
- 不動産を購入した際にかかった費用
- 不動産を売却した際にかかった費用
- 適用される控除の額
不動産の所有年数に応じた譲渡所得税の税率を次にまとめました。
| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得(5年を超える) | 15% | 5% | 0.315%(15%×2.1%) | 20.315% |
| 短期譲渡所得(5年以下) | 30% | 9% | 0.63%(30%×2.1%) | 39.63% |
※ 国税庁、短期譲渡所得の税額の計算
※ マンションを売却したら住民税が上がる?税金の計算方法と軽減する方法を解説
※ 2037年までは復興特別所得税として、各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と合わせて申告し、納付することになります。
※所有期間は不動産を売却する年の1月1日現在で判定します。
一般的には上記の計算で納税が必要ですが、次の控除を受けられるケースもあります。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
- 特定の居住用財産の買換えの特例
控除の適用条件は細かく設定されているため、国税庁の公式サイトで確認しましょう。

不動産の個人売買で住宅ローンは組める?

不動産の個人売買では、まず住宅ローンは組めないと考えましょう。
ここからは、個人売買での住宅ローンが難しい理由や対策について解説するため、個人売買における住宅ローンに不安を抱える方は、ぜひ参考にしてください。
個人売買で住宅ローンを組むのが難しい理由
不動産の個人売買で住宅ローンを組むことが難しい理由は、審査に必要な重要事項説明書が発行されないケースがあるためです。
重要事項説明書とは、不動産取引における重要な事項を記した書面で、不動産会社は契約前の交付が義務付けられています。
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
引用:宅地建物取引業法 | e-Gov 法令検索
重要事項説明書は宅地建物取引士のみが発行できる書類であり、個人売買での準備は困難です。
重要事項説明書が発行できない物件は、金融機関が融資をするための判断材料が少なくなるため、個人売買では原則として住宅ローンは組めません。
個人売買で住宅ローンを組む具体的な方法
不動産の個人売買では、次の方法を用いれば住宅ローンを組めます。
- 重要事項説明書の作成を不動産会社に依頼する
- 不動産個人売買のサポートサービスがある不動産会社を活用する
不動産個人売買のサポートサービスを提供する不動産会社を活用すれば、個人売買でも重要事項説明書を作成できます。
いずれにせよ、重要事項説明書を作成しなければ住宅ローンを組めないことを覚えておきましょう。
不動産の個人売買でかかる税金

不動産の個人売買では、次の4つの税金がかかります。
- 譲渡所得税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 印紙税
ここからは、条文を踏まえて税金について詳しく解説するため、個人売買を検討中の方は覚えておきましょう。
譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産を売却して得た所得に対してかかる税金です。
譲渡所得税の金額を計算するためには、まず次の式で譲渡所得を計算する必要があります。
収入金額 − 取得費 − 譲渡費用 = 譲渡所得
簡単に説明すると、売却金額から諸経費を差し引いた金額が譲渡所得で、譲渡所得がプラスの場合は、次の計算式で譲渡所得税を求められます。
(譲渡所得 - 特別控除) × 20.315% or 39.63% = 譲渡所得税
譲渡所得にかかる税率の違いは次のとおりです。
| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得(5年を超える) | 15% | 5% | 0.315%(15%×2.1%) | 20.315% |
| 短期譲渡所得(5年以下) | 30% | 9% | 0.63%(30%×2.1%) | 39.63% |
※ 国税庁、短期譲渡所得の税額の計算
※ マンションを売却したら住民税が上がる?税金の計算方法と軽減する方法を解説
※ 2037年までは復興特別所得税として、各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と合わせて申告し、納付することになります。
※所有期間は不動産を売却する年の1月1日現在で判定します。
上記のとおり、売却前の保有年数に応じてかかる税率は異なります。
登録免許税
登記免許税とは、不動産登記の際に課される税金です。
登録免許税は不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税されます。
引用:No.7190 登録免許税のあらまし|国税庁
不動産売買では土地と建物それぞれの登記の際に発生し、次の表で示す税率が課されます。
| 対象 | 種類 | 税率 |
|---|---|---|
| 土地 | 所有権移転登記(売買、贈与、交付など) | 2.0%(※) |
| 土地 | 所有権移転登記(相続) | 0.4% |
| 建物 | 所有権保存登記(新築、建築) | 0.4% |
| 建物 | 所有権移転登記(売買、贈与、交付など) | 2.0% |
| 建物 | 所有権移転登記(相続) | 0.4% |
| 土地・建物 | 抵当権設定登記 | 0.4% |
| 土地・建物 | 抵当権抹消登記 | 不動産1個につき1,000円 |
※2026年3月31日までの登記は軽減税率1.5%
不動産を登記する際は、上記の税率を参考にしてください。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を購入した際にかかる税金です。
不動産取得税は「課税標準額(固定資産税評価額)×税率」で計算され、購入後に納税通知書が届きます。
不動産取得税の税率を次にまとめました。
| 不動産 | 税率 |
|---|---|
| 宅地 | 評価額×4% |
| 宅地(軽減税率) | 評価額×1/2×3% |
| 住宅 | 評価額×4% |
| 住宅(軽減税率) | 評価額×3% |
税率は原則4%ですが、2027年3月31日までに取得すれば、軽減税率が適用されます。
印紙税
印紙税とは、課税文書を作成する際に課される税金です。
不動産の売買契約書には収入印紙を貼る義務があり、貼らなければ罰金が発生する恐れがあります。
収入印紙は、契約書に記載されている金額により必要な金額が次のとおり変化します。
| 記載された契約金額 | 税額 | 軽減後の税額 (2027年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
※税額は一部を抜粋しています。
印紙税の金額が分からない方は、ぜひ参考にしてください。
不動産を個人売買する際の注意点

不動産仲介業者を介するよりも難易度が高い不動産の個人売買をスムーズにおこなうためのポイントは、次の4つです。
- 相場の調査を怠らない
- 書類作成や名義変更は司法書士に依頼する
- トラブルの際は無理せず専門家に相談する
- 契約不適合責任に注意する
これから不動産の個人売買にチャレンジする方は、ぜひ参考にしてください。
相場の調査を怠らない
不動産の個人売買をはじめる際は、相場の調査を怠らないようにしましょう。
相場からかけ離れた価格設定で不動産を売りに出すと、買主が見つかりにくいため、相場の調査を怠らないことが大切です。
相場よりも高く売りに出した場合は、値段を見ただけで対象外にされる恐れがあるでしょう。
一方、相場よりも安すぎる価格設定で売りに出した場合は、買い手は見つかるものの損をする可能性があります。
いずれも売主にとって不利益となるため、まずは相場の調査を徹底しましょう。
書類作成や名義変更は司法書士に依頼する
書類に不備があると後々のトラブルにつながるため、登記に関する書類の作成は、司法書士に依頼しましょう。
書類の作成や準備を個人でおこなうことは可能ですが、手間がかかるうえ、不備が起こりやすい傾向があります。
不動産は個人売買をする際でも、面倒な書類作成は確実に作成できるプロへの依頼がおすすめです。
トラブルの際は無理せず専門家に相談する
不動産の個人売買は、仲介業者を介するよりもトラブルが起こりやすく、対処法を誤るとさらに状況が悪化します。
不動産売買でのトラブルに対処できる専門家を次の表にまとめました。
| 専門家 | 依頼できる業務 |
|---|---|
| 司法書士 | 登記手続き・登記に関する書類作成 |
| 行政書士 | 許認可に必要な書類作成 |
| 弁護士 | 幅広いトラブルの解決 |
| 税理士 | 税金の相談 |
| 不動産鑑定士 | 不動産の価値の鑑定 |
| 土地家屋調査士 | 土地の境界線の測量 |
| 住宅診断士 | ホームインスペクション |
トラブルが起きた際は、無理せず専門家への相談がおすすめです。

契約不適合責任に注意する
個人の不動産売買では、売却後に契約内容との不適合が発覚した際に売主が負う、契約不適合責任に注意が必要です。
たとえば、売却時に雨漏りがある、シロアリが発生しているなどを伝えず、引き渡し後に発覚した場合などが当てはまります。
契約時に契約不適合責任の保障期間や詳細を取り決め契約書に明記している場合は、その内容に従い契約解除や損害賠償の支払いなどを進めます。
しかし、記載がなければトラブルに発展するケースもあるでしょう。
トラブルを防ぐためにも、不動産の状態を正直に買主に伝え、万が一契約内容との不適合が発覚した場合の保証期間や詳細を契約書に明記してください。
不動産個人売買サイトのおすすめ3選

つづいて、不動産の個人売買をスムーズにおこなうためにおすすめの、不動産個人売買サイトを3選紹介します。
- e-物件情報
- 不動産直売所
- 家いちば
特徴をそれぞれ解説していきます。
e-物件情報
e-物件情報は、手数料無料で利用でき、エージェントサポートが利用できるサイトです。
料金設定は、次のとおりです。
| 掲載コース | 掲載料 | 添付可能な画像数 |
|---|---|---|
| スタンダード | 3,300円 | なし |
| シルバー | 6,600円 | 2点 |
| ゴールド | 11,000円 | 8点 |
掲載期間の決まりがなく、掲載料を一度払えば売れるまで無期限で掲載可能なため、焦らずじっくりと買い手を探せます。
また、GoogleやYahoo!などの大手検索エンジンに登録されており、登録している人に専用の新着メールで掲載した物件情報が届くことも魅力です。
また、エージェントサポートが受けられるため、不動産の知識はないけれど、トラブルなく不動産個人売買をおこないたい方におすすめです。
不動産直売所
不動産直売所は、無料で不動産情報を掲載できるサイトです。
掲載ではなく処分にも対応してくれるサイトであり、処分を依頼する場合は一律35万円で引き取ってくれる場合があります。
日本全国の土地や建物を対象としており、空き家や別荘、再建築不可物件も引き取ってくれるため、他社で断られた場合でも問題ありません。
家いちば
家いちばは、廃墟寸前の訳アリ物件や、工場・お店をはじめとする家ではない物件など、「なんでも載せていい」ことが売りのサイトです。
掲載段階では無料で、契約が成立した場合は、「媒介報酬分+基本料」の費用が発生します。
媒介報酬分と基本料は、次のとおりです。
【媒介手数料】
| 売買価格 | 手数料 |
|---|---|
| 400万円超 | 1.5%+3万円 |
| 400万円以下 | 2%+1万円 |
| 200万円以下 | 2.5% |
| 120万円以下 | 3万円(一律) |
【基本料】
| 売主(システム登録基本料) | 9万円(一律) |
|---|---|
| 買主(成約基本料) | 9万円(一律) |
媒介手数料は、通常の仲介手数料の半額です。
成約時の費用はかかりますが、手厚いサポートが含まれているため、不動産の知識がなくても個人売買をスムーズにおこないたい方におすすめです。
不動産の個人売買に関するよくある質問

最後に、不動産の個人売買に関してよくある質問をまとめました。
同じ不安を抱える方は、ぜひ参考にしてください。
個人売買で消費税は発生する?
不動産の個人売買では売主が個人の場合、消費税は発生しません。
売主が法人の場合は、建物にのみ消費税が発生します。
ただし、売主が個人の場合でも、課税事業者である場合は建物にのみ消費税が発生するため注意が必要です。
司法書士費用の相場は?
不動産の個人売買で司法書士に依頼する場合の費用相場は、5万円~20万円です。
所有権移転登記のみを依頼する場合は10万円以下、抵当権設定登記や抵当権抹消登記などの登記手続きを依頼する場合は20万円程度の費用が必要です。
ただし、司法書士への依頼費用は事務所ごとに異なるため、複数の司法書士に問い合わせて比較しましょう。
税金控除に利用できる特例は?
売却した不動産が住居用であった場合、次の特例を利用できる可能性があります。
- 居住用財産を売却した場合の3,000万円控除
- 居住用財産の買い換えの特例
そのほかにも、条件を満たすことで利用できる特例があるため、専門家に相談すると安心です。
まとめ

本記事では、不動産の個人売買について解説しました。
不動産の個人売買は簡単ではありませんが、正しい知識と手順で進めれば可能です。
ただし、書類の準備など、一部の作業は専門家に依頼したほうがスムーズに取引が進むため、個人での対応が難しい工程は、専門家への依頼がおすすめです。
効率よく専門家を活用し、個人売買の手間を省きつつメリットのある取り引きをしましょう。













