土地を売却するときは、不動産会社へ支払う仲介手数料や司法書士へ支払う手数料など、さまざまな費用が発生します。
また、土地の境界が不確定のときや分筆したうえで売却するときは、追加で手数料が発生します。
さらに、取得したときの金額よりも高い価格で売却できたら、所得税や住民税などを納税しなければなりません。さまざまな手数料や税金が発生する点に留意し、資金計画を立てましょう。
今回は、土地の売却時に発生する手数料・税金などを解説します。
土地の売却を進めるときは、手数料や税金を考慮したうえで、最終的な手取り額を計算しましょう。
土地の売却時に発生する手数料・費用

土地をはじめとした不動産を売却するときは、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
具体的に発生する手数料や費用の項目、金額の相場などを見ていきましょう。
【必須】仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社へ支払う手数料です。媒介契約を締結し、実際に買主を見つけて成約に至ったとき、売却価格に応じて仲介手数料を不動産会社へ支払います。
仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法において、以下のように定められています。
| 不動産売買価格 | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|
| 400万円超 | 物件価格×3%+6万円+消費税 |
| 200万円超400万円以下 | 物件価格×4%+2万円+消費税 |
| 200万円以下 | 物件価格×5%+消費税 |
仲介手数料には、成功報酬の意味合いがあります。複数の不動産会社と媒介契約を締結した場合でも、仲介手数料を支払うのは実際に買主を見つけた不動産会社だけです。
【必須】司法書士へ支払う手数料
土地を売却する際には、司法書士に権利関係の登記を依頼します。具体的な金額は依頼する司法書士によって異なりますが、抵当権抹消登記の報酬として1万円〜3万円程度の手数料が発生するのが一般的です。
実務上は、不動産会社と連携している司法書士に依頼して登記を進めます。
土地の測量費用
売却しようとしている土地の境界が不明確な場合、土地の境界を確定させるために、測量をする必要があります。
測量図が古く、現在の状況と合っていない可能性がある場合も、土地の測量を行って境界を確定させておくとよいでしょう。
土地の境界を確定させる目的は、売買後のトラブルを避けるためです。土地の境界が曖昧だと買主としても安心して購入できないため、境界が不明確な場合は測量を行い、境界を確定させましょう。
なお、土地の測量を依頼する専門家は土地家屋調査士です。依頼費用は土地の形状や面などによって異なりますが、10万円〜30万円程度の費用が発生するのが一般的です。
複雑な地形の場合は追加費用が発生することがあるため、事前に依頼費用の見積もりを取得するとよいでしょう。
土地の分筆費用
分筆とは土地を複数の区画に分けるための手続きで、法務局で登記が完了したあとに、それぞれの区画に新しい地番が付与されます。
土地の面積が広い場合は、分筆をしたうえで、部分的に売却することがあるかもしれません。また、「所有している土地の一部だけを売却したい」と考えている場合においても、分筆した上で売却するケースがあります。
他にも、共有名義の土地を分筆し、共有者ごとの単独所有にしたうえで売却することも可能です。
なお、分筆を進めるときも土地家屋調査士に依頼しましょう。分筆にかかる費用は土地の面積や形状によって変動するものの、15万円〜50万円程度が相場です。
分筆した土地を登記するときは、1筆あたり1,000円の登録免許税が発生します。例えば、分筆登記後の土地が2筆であれば、2,000円の登録免許税を納付する必要があります。
水道管を引き込む工事の費用
土地に水道管が引き込まれていない場合は、水道管を引き込むための工事が必要です。水道管が引き込まれていない場合は上水や下水を使用できず、生活できないためです。
例えば、公道に水道本管はあるものの、売却する土地まで引き込み管が設置されていない場合が挙げられます。
また、複数区画に分けた土地を売却する際に各区画への水道引き込みが必要になる場合においても、水道管を引き込むための工事が必要です。
工事を依頼するときは、自治体の認定を受けた水道工事業者に相談しましょう。引き込み工事の費用は本管から敷地までの距離や口径などによって異なるものの、10万円〜60万円程度になります。
詳細な金額は土地の状況によって異なるため、業者に見積もりを依頼し、正確な費用を把握しておきましょう。
解体工事費用
建物が建っている土地を更地にしてから売却する場合は、解体工事費用が発生します。相続した土地に空き家が建っており、更地にしてから売却するようなケースでは、解体したうえで売り出すケースが多く見られます。
更地にすることにより、土地を購入した人が自由に使用できます。需要が高まる効果が期待できるため、空き家が建っている状態よりも高額で売却できるでしょう。
なお、解体工事費用は建物の構造や規模、立地条件などによって異なります。例えば、木造住宅の場合は100万円〜300万円程度、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物は150万円〜500万円程度のように差があります。
信頼できる解体業者に作業を依頼するためにも、複数の業者から見積もりを取得し、廃棄物の適正処理を行ってくれる業者に依頼しましょう。
土地の売却時に発生する税金

土地の売却時には、売却金額次第で税金も発生します。
どのような税金が発生するのか、確認していきましょう。
譲渡所得税・住民税
取得時の金額よりも高い金額で土地を売却した場合は、譲渡所得税と住民税が発生します。
課税譲渡所得金額を「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で算出したうえで、土地の所有期間に応じた税率をかけます。
| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得(5年を超える) | 15% | 5% | 0.315%(15%×2.1%) | 20.315% |
| 短期譲渡所得(5年以下) | 30% | 9% | 0.63%(30%×2.1%) | 39.63% |
※ 国税庁、短期譲渡所得の税額の計算
※ マンションを売却したら住民税が上がる?税金の計算方法と軽減する方法を解説
※ 2037年までは復興特別所得税として、各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と合わせて申告し、納付することになります。
※所有期間は不動産を売却する年の1月1日現在で判定します。
土地の所有期間が5年以内の場合は税率が39.63%、5年超の場合は20.315%です。
ただし、取得費が不明な場合、売却額の5%を取得費として譲渡所得を計算する「概算取得費」で対応することがあります。
居住用財産の3,000万円特別控除
居住用財産の3,000万円の特別控除を利用すれば、譲渡所得から3,000万円を控除できます。
譲渡所得が3,000万円以下の場合、この特例を利用できれば、譲渡所得税・復興特別所得税・住民税が発生しません。節税につながるため、有効活用しましょう。
土地のみを売却する場合、「家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る」という期間の制約があります。
その他にも詳細な要件があるため、土地を売却するときに利益が発生する場合は、税理士に相談するとよいでしょう。

軽減税率の特例
軽減税率の特例とは、所有期間が10年を超える家と土地を売却したとき、本来の税率よりも低い税率が適用される特例です。
| 所有期間※1 | 所得税 | 復興特別所得税 ※2 | 所得税合計 | 住民税 | 譲渡益に対する 税金の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 0.63% (30%×2.1%) | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 0.315% (15%×2.1%) | 15.315% | 5% | 20.315% |
| 10年超軽減税率 (6,000万円以下) | 10年超 | 10% | 0.21% (10%×2.1%) | 10.21% | 4% | 14.21% |
※2:2037年までは復興特別所得税として、各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と合わせて申告し、納付することになります。
※ 国税庁、長期譲渡所得の税額の計算
※ 国税庁、短期譲渡所得の税額の計算
※ 国税庁、No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
※ マンションを売却したら住民税が上がる?税金の計算方法と軽減する方法を解説
居住用財産の3,000万円の特別控除と併用が可能で、併用することにより節税効果が高まります。
手元に多くのお金を残すためにも、両者を利用できるか調べてみてください。
印紙税
売買契約書を作成したときには、収入印紙を貼付して印紙税を納付します。
貼付する収入印紙は、土地の成約金額に応じて以下のように決まっています(令和9年3月31日までの間に作成される契約書は軽減税率が適用)。
| 記載された契約金額 | 税額 | 軽減後の税額 (2027年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
※税額は一部を抜粋しています。
売買契約書に貼る印紙税は、売主と買主が折半で負担するのが一般的です。なお、電子契約の場合は印紙税の課税対象となる文書には含まれないため、印紙税の納付が不要です。
仲介手数料を安く抑える方法
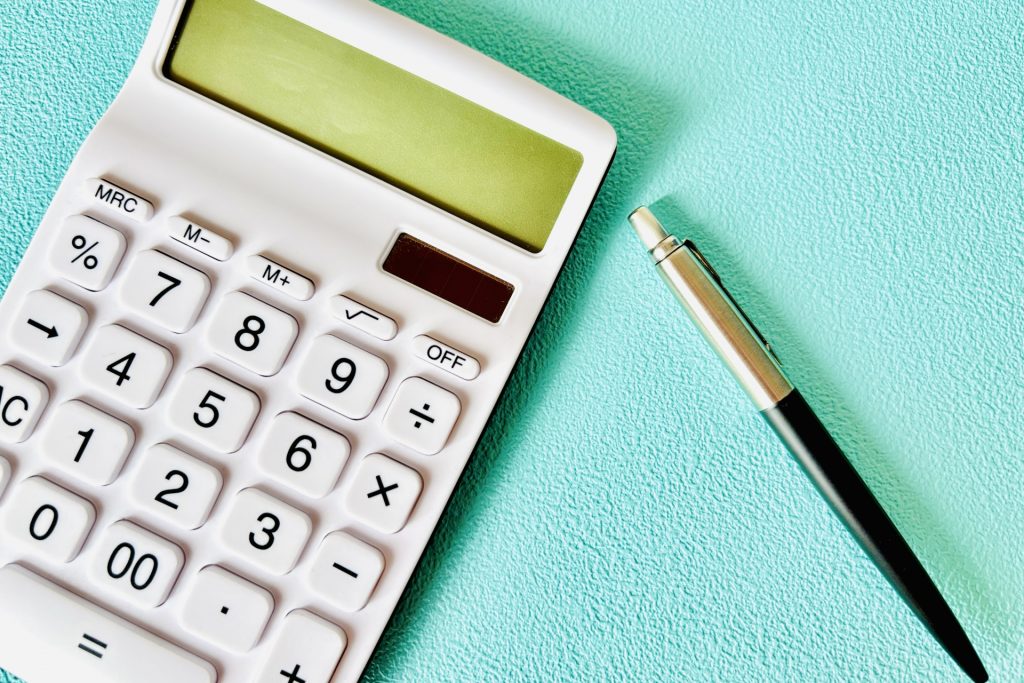
土地を売却する中で、負担になりやすい費用が仲介手数料です。売却価格によっては数百万円になるため、売主にとって負担となります。
ただし、場合によっては仲介手数料を抑えられる可能性があります。どのような方法が考えられるか、詳しく見ていきましょう。
不動産会社に値引きを依頼する
不動産売買に関する仲介手数料に上限は設けられているものの、不動産会社次第では値引き交渉に応じてくれる可能性があります。
土地の査定を依頼したあと、仲介手数料の料金設計について確認したあと、値引きできる余地があるか相談するとよいでしょう。
手数料が下がれば、その分だけ手取り額が増えるため、直接的な利益が増えることを意味します。
複数の不動産会社で仲介手数料の金額をシミュレーションしてもらい、競争原理を働かせるのも一つの手段です。
また、特定の一社に仲介を依頼する「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」にすることを条件に、値引き交渉をする方法も考えられるでしょう。
ただし、単純に仲介手数料の金額だけを比較するのではなく、サービス内容や不動産売却の実績などを比較することも大切です。
仲介手数料が安くても、営業活動の質が悪いと、低い価格での売却になりかねないためです。
自分自身で買主を探す
自分自身で買主を探せば、不動産会社へ支払う仲介手数料が1円も発生しません。不動産の売却経験があり、自分だけで売却活動を進められる方というは、検討するとよいでしょう。
例えば、SNSを活用したり、親族や知人を通じて潜在的な買主にアプローチしたりする方法があります。
また、不動産会社と一般媒介契約を結びつつ、自分でも買主を探す「自己発見取引」の可能性を残しておくことも可能です。
不動産会社を介さずに土地を売却する場合は、売買契約書の作成や重要事項説明などを、売主自身が行わなければなりません。
説明が不十分だと、土地に何らかの問題があったときに「契約不適合責任」を問われ、トラブルになる可能性があります。
また、効果的なマーケティングを行う必要があるだけでなく、適正な価格設定をはじめとした専門知識が必要になります。
不動産売買の実務経験がある方でなければ、自分で買主を探すのは現実的ではないでしょう。
仲介手数料を無闇に抑えるべきではない理由

土地を売却するにあたって、仲介手数料を抑えられれば手元に多くのお金を残せます。
しかし、仲介手数料を無闇に抑えようとすると、結果的に損をする事態になりかねません。以下で、その理由を解説します。
熱心に売却活動が行われない可能性がある
不動産会社は、仲介手数料を不動産の取引をまとめるために必要な経費に充てます。具体的な経費は、宣伝広告費や契約書類の作成をはじめとした事務手続きなどの費用です。
つまり、仲介手数料を安くすると不動産会社が売却活動のために割ける予算が減少するため、熱心に売却活動が行われない可能性があるのです。
これにより、効果的な広告が行われず、潜在的な買主に対するアプローチの機会が少なくなってしまいます。
さらに、不動産会社の営業員のモチベーションを損ねる要因にもなります。成約価格で妥協を余儀なくされる可能性もあり、手元に残る利益が少なくなってしまう可能性が考えられるでしょう。
適正な手数料を支払うことで、最終的に当初の想定どおりの金額で売却できたり、売却期間を短縮できたりします。
トータルで見ると、無闇に仲介手数料を安く抑えようとするのは、得策とはいえません。
仲介手数料以外の費用が発生する可能性がある
仲介手数料を抑えた結果、仲介手数料とは別の名目で費用が発生する可能性があります。不動産会社としては、仲介手数料を安くする分、別の形で収益を確保しようと考えるためです。
例えば、広告費を別途請求したり、ポータルサイトへの掲載料や写真撮影費などが上乗せされたりする可能性があります。
また、成約後に「事務手数料」「事務処理費」などの名目で、別途費用が発生することもあります。
つまり、手数料を抑えたつもりでいても、結果として値引き前の仲介手数料を支払っているのと同じ結果になるのです。
むしろ、本来の値引き前の仲介手数料を支払ったほうが、トータルで得をする可能性もあります。
土地の売却を進めるときの流れ

土地を実際に売り出してから成約するまでに、1年以上の期間がかかることもあります。希望している価格・時期に売却するためにも、計画的に売却活動を進めましょう。
以下で、土地の売却を進めるときの流れを解説します。
価格の査定を受ける
まずは、売却しようとしている土地に関して、不動産会社に価格の査定を依頼します。査定の結果は、土地が属するエリアの需要や広さ、形状などを参考にしながら算出されます。
不動産会社によって査定結果は異なるため、最低でも3社以上に査定を依頼しましょう。査定結果を比較検討したうえで、どの不動産会社に仲介を依頼するか決定します。
インターネットの一括査定サイトを利用すると、1回の入力で複数社から査定を受けられるため、スムーズに査定結果を収集できます。
不動産会社の中には、契約を取るために意図的に高い査定額を提示する「高値査定」を行う会社があります。
査定を一社に絞ると、高値査定額を行う不動産会社を見抜けない可能性があるため、必ず複数社に査定を依頼しましょう。
あわせて、査定書を取得したり査定額の根拠を聞いたりして、相応の根拠がある査定結果かどうかを確認することも大切です。
不動産会社と媒介契約を締結する
土地の売却を不動産会社に依頼する場合は、媒介契約を締結します。以下3つの種類があるため、適している契約方法を選択しましょう。
| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 複数社との契約 | 〇 | × | × |
| 指定流通機構(レインズ)への登録 | 任意 | 義務 (7営業日以内) | 義務 (5営業日以内) |
| 不動産会社の売主への業務報告 | 任意 | 義務 2週間に1回以上 | 義務 1週間に1回以上 |
| 自己発見取引 (売主が自ら発見した相手との契約) | 〇 | 〇 | × 必ず媒介契約を結んだ不動産会社を介して契約する必要あり |
| 契約有効期間 | 法律上の制限なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
※ 全日本不動産協会、一般媒介契約
※ 媒介契約とは?
競争原理を働かせたい場合は、複数の不動産会社と契約できる一般媒介契約が向いています。
また、自分で買主を見つける「自己発見取引」も可能であるため、柔軟に売却活動を進められるでしょう。
信頼できる不動産会社が見つかり、1社のみに販売を依頼したい場合は、専任媒介契約または専属専任媒介契約が向いています。
どの媒介契約を締結する場合でも、販売活動・広報活動の具体的内容や仲介手数料の計算方法などを確認しておきましょう。
不動産会社が実際に売り出す
媒介契約を締結したあとは、不動産会社が実際に売り出します。売り出す価格は、売主と不動産会社が話し合ったうえで決定します。
代表的な売り出し方法は、不動産ポータルサイトへの掲載やSNSでの発信などです。
「実際にどの程度の反響があったのか」「見込み客が現れたのか」などの情報を収集し、その後の販売戦略に生かしていきましょう。
買主と売買契約を締結する
買主が現れたら、現地案内や価格交渉などを経て、成約価格に折り合いをつけます。お互いに納得できる金額が決まったら、不動産会社の事務所や店舗で売買契約を締結します。
売買契約を締結する際には、不動産会社の宅地建物取引士による重要事項説明が行われます。
買主から質問を受けたら、適宜回答しましょう。売買契約書を作成したら、売主と買主が記名と押印を行います。
決済と引き渡しを行う
売買契約を締結したあとは、契約で決めた日程にしたがって、代金の決済や土地の引き渡しを行います。代金の決済は金融機関の支店で、平日の午前中に行われるのが一般的です。
権利を移転するための書類を司法書士に渡し、司法書士が法務局で所有権移転登記を行えば引き渡しは完了です。
土地売却の費用や税金で迷ったらファンズ不動産へ
土地を売却すると、仲介手数料や登記費用、譲渡所得税など、さまざまな費用や税金が発生します。項目が多く複雑なため、「結局いくらかかるのか」「どの費用が必要なのか」と迷ってしまう方も少なくありません。
正しい知識を持っておくことで、思わぬ出費を避け、納得感のある売却につなげることができます。費用や税金に不安がある場合は、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
ファンズ不動産では、土地売却にまつわる疑問や悩みにも丁寧に寄り添い、状況に合わせた判断をサポートできます。
売却査定から引渡しまで、安心のワンストップ対応
ファンズ不動産は、LINEを活用した効率的なプロセスと、幅広い専門知識でスムーズな不動産売却を実現します。
相談は「オンライン面談」から始まり、やり取りもLINEメインでおこなうため、店舗へ足を運ぶ手間も最小限です。
また土地のプロやリノベーションの専門家も在籍しているので、専門知識が必要な相談も窓口一つで完結します。忙しい方でも、スムーズで安心な売却活動が可能です。
日中は仕事で時間が取れない方や、複雑な手続きをまとめて任せたい方でも、ストレスなく売却活動を進められます。
売却が初めての方へ:ファンズ不動産が選ばれる3つの強み
ファンズ不動産は、売主様が抱える不安を解消する、独自の「訴求力」「専門性」「手軽さ」を兼ね備えています。
- 訴求力:1万人超のLINE登録者へ直接情報を届ける高い「訴求力」が、早期の買主発見をサポートします。
- 専門性:都心特化・設立1年半で取扱高100億円を突破した「専門性」が、適正な価格設定と売却戦略を実現。
- 手軽さ:オンライン面談からLINEで活動を進められる「手軽さ」が、忙しい方でもスムーズな売却を可能にします。
初めての売却で不安をお持ちなら、まずはLINEでの気軽なご相談から、納得のいく売却への第一歩を踏み出しましょう。
リノベ前提の物件や土地売却も。専門チームが対応
ファンズ不動産は、一般的なマンションや戸建てだけでなく、専門知識が求められる不動産の売却にも対応しています。
社内には土地売買のプロが在籍しているほか、2025年10月からはリノベーションのワンストップサポートも開始しました。
そのため「リノベーション前提」といった付加価値を付けた売却提案や、複雑な権利関係が絡む土地の売却も、窓口一つでスムーズに進められます。
他社では取り扱いが難しいと言われた物件でも、まずは一度相談してみる価値があるでしょう。
まとめ

土地を売却するときには、事前にどのような手数料が発生するのかを確認しましょう。
最終的に手元に残るお金は、売却価格から手数料や税金などを差し引いた金額になるため、諸経費を把握することは大切です。
土地の売却に際して発生する手数料の中でも、不動産会社へ支払う仲介手数料は大きな割合を占めることがあります。
仲介手数料の値下げを依頼することは可能ですが、結果的に売却活動の質が落ちてしまい、結果的に損をしてしまう可能性がある点に注意しましょう。
なお、土地の売却で失敗しないためには、仲介を依頼する不動産会社選びも大切です。売主に寄り添って売却活動を行い、誠実に対応してくれる不動産会社に売却を依頼しましょう。













