相続した土地をどうするか決める際、「売却したほうがよいのだろうか」「売ったらどのような税金がかかるのだろうか」と考える方もいるでしょう。
また故人名義の土地をどのようにして売却したらよいかわからず、不安になるときもあるのではないでしょうか。
相続した土地を売却したときに納める税金は、登録免許税や印紙税、譲渡所得税で特例を利用できれば、節税できる可能性があります。
本記事では、相続した土地を売却するときに納める税金やすぐに売却しなくてもよいケース、節税になる特例や売るときの流れなどを解説します。
亡くなった方から相続した土地の売却を検討している方や、納める税金がわからず不安な方は、ぜひ参考にしてください。
相続した土地を売却したときに納める税金

相続した土地を売却するときは、次のような税金が発生します。
| 税金の種類 | 金額・計算方法 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% |
| 印紙税 | 契約金額による例: 1,000万円超5,000万円の場合、1万円(軽減税率) |
| 譲渡所得税 | 課税譲渡所得金額×20.315%(5年超所有) |
それぞれ発生する税金を詳しく解説します。
登録免許税
相続した土地を売却する前には相続人の名義に変更しなければなりませんが、名義変更の手続きを法務局でおこなうときに、登録免許税を支払う必要があります。
相続に関する登録免許税は、次の計算式で算出します。
固定資産税評価額×0.4%=登録免許税
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の土地の場合、登録免許税は8万円です。
固定資産税評価額とは、固定資産税を計算する際のベースとなる評価額で、毎年4月~6月に届く「固定資産税納税通知書」に記載されています。
印紙税
相続した土地を売却する際、印紙税が発生します。
印紙税は不動産売買契約書に印紙を貼付し、消印することで納税することになり、契約金額によって税額は異なります。
具体的な税額は以下の通りです。
| 記載された契約金額 | 税額 | 軽減後の税額 (2027年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
※税額は一部を抜粋しています。
たとえば、売買契約が折り合った金額が3,000万円の場合、1万円の収入印紙を貼付して消印することで納税となります。
収入印紙は郵便局や法務局、金額によってはコンビニエンスストアなどで入手できるため、契約金額にあわせて購入してください。
譲渡所得税
相続した土地に関して、被相続人(故人)が取得したときの金額よりも高い価格で売却できた場合は、譲渡所得税が発生します。
課税譲渡所得金額の計算式は、次のとおりです。
譲渡所得(利益)−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
また譲渡所得税は不動産の所有期間によって、以下の所得税率と住民税率を乗じて計算します。
| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得(5年を超える) | 15% | 5% | 0.315%(15%×2.1%) | 20.315% |
| 短期譲渡所得(5年以下) | 30% | 9% | 0.63%(30%×2.1%) | 39.63% |
※ 国税庁、短期譲渡所得の税額の計算
※ マンションを売却したら住民税が上がる?税金の計算方法と軽減する方法を解説
※ 2037年までは復興特別所得税として、各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と合わせて申告し、納付することになります。
※所有期間は不動産を売却する年の1月1日現在で判定します。
譲渡所得税は、利益が出るときに発生する税金です。取得したときの価格よりも低い金額での売却となった場合、譲渡所得税は発生しません。
また、譲渡所得税は売却した翌年2月中旬〜3月中旬に確定申告をして納付するため、忘れずに手続きをしてください。
相続した土地はすぐ売却すべき?
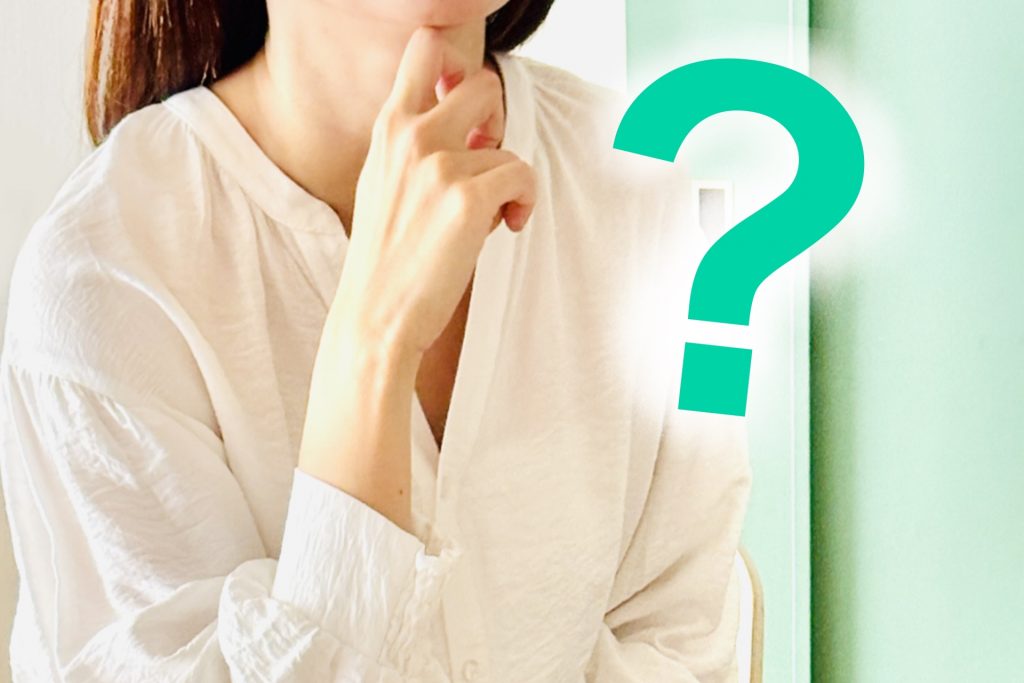
亡くなった方の土地を相続した際、すぐに売却したほうがよいのか悩む方もいるでしょう。
相続した土地をすぐに売却したほうがよいケースと、やめておいたほうが無難なケースをそれぞれ解説します。
すぐ売却したほうがよいケース
故人から相続した土地を早めに売却したほうがよい主なケースは、次のとおりです。
- 相続税を納付する資金がない
- すでに相続税を納付した
- 土地活用が難しい
- 遺産分割で揉める可能性がある
すでに相続税を納付した場合は、税金の負担を軽減できる特例措置があるため、早めの売却がおすすめです。
他にも上記が当てはまる場合は、相続した土地をすぐに売却して現金化したほうが、維持費がかからず、遺産分割もスムーズに進むでしょう。
すぐ売却しなくてもよいケース
亡くなった方から相続した土地をすぐに売却しなくてもよいケースは、次のとおりです。
- 相続税を納付できる
- 相続税が発生しない
- 土地活用を検討している
- 遺産分割でトラブルにならなかった
上記のケースが当てはまる方は、相続した土地をどうするかの判断を急がなくても問題ないでしょう。
なお、相続した土地を売却するかどうか悩む場合でも、故人から相続人に名義を変更する相続登記は義務化されています。
相続登記の申請は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内におこなう必要があります。
ただし、令和6年4月1日以前に相続した不動産については、令和9年(2027年)3月31日までに登記を完了しなければならないため、注意が必要です。
相続した土地を3年以内に売却した際に使える特例

相続した土地を売却するとき、節税につながる特例がいくつかあります。
土地を売却する際には、以下で解説する特例のなかから、利用できる制度がないか確認してみてください。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
3,000万円の特別控除とは、所定の条件を満たしたとき、課税譲渡所得金額から最高3,000万円を控除できる特例です。
相続した空き家を3年以内に売却するときに利用でき、大きな節税効果を得られます。
「空き家特例」とも呼ばれる、3,000万円特別控除の主な要件は、次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築されている
- 区分所有登記がされている建物ではない
- 相続開始から3年経過した年末までの売却
- 売却代金が1億以下
故人から相続した空き家で、要件に当てはまる場合は特例が適用され、税負担を大きく軽減できます。
詳しい内容や要件を知りたい方は、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」のページやチェックシートを確認してください。
マイホームを売った時の軽減税率の特例
軽減税率の特例とは、所有期間が10年を超えるマイホーム(居住用財産)の売却に伴って譲渡所得が発生したとき、本来よりも低い税率が適用される特例です。
所有期間5年超の長期譲渡所得税率(20.315%)からさらに税率が軽減されるため、大きな節税効果が期待できます。
適用される税率は、次の表を参考にしてください。
| 課税長期譲渡所得金額 | 税額 |
|---|---|
| 6,000万円以下 | 課税長期譲渡所得金額×10% |
| 6,000万円超 | 課税長期譲渡所得金額6,000万円を超える部分は15% |
※税率は所得税・住民税・復興特別所得税の合計
なお、本特例を利用する際の主な要件は以下のとおりです。
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が10年超
- 住んでいるまたは空き家になって3年以内
- 親族以外の第三者への売却
- 前年、前々年にこの特例を利用していない
特例の内容や詳しい要件を知りたい方は、「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」のページを参考にしてください。
取得費加算の特例
相続税を納付している場合は、取得費加算の特例を利用できます。
相続税の一部を取得費に入れて計算してよいとする特例で、適用されれば支払う税金が少なくなります。
取得費加算の特例の主な要件は、次のとおりです。
- 相続人が売却する
- 相続人が相続税を支払う
- 相続開始から3年10か月以内の売却
3,000万円特別控除と比べると要件が多くはなく、利用しやすい特例です。
取得費加算の特例の詳細な内容や要件が知りたい方は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」のページを参考にしてください。
相続した土地を売却する際の節税対策

亡くなった方から相続した土地を売却する場合に、できる節税対策は次のとおりです。
- 取得費が確認できる書類を準備する
- 譲渡費用はすべて計上する
- ふるさと納税を活用する
それぞれ詳しく解説するため、可能な限り節税したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
取得費が確認できる書類を準備する
相続した土地を売却する際は、取得費が確認できる書類を探して、準備しておきましょう。
取得費がわからないと売却した金額の5%を概算取得費として税金を計算するため、納付額が高額になる可能性もあります。
取得費が確認できるときと、わからない場合の譲渡所得税の一例は次のとおりです。
| 所有期間8年の土地を売却 | |||
|---|---|---|---|
| 売却金額 | 譲渡費用 | 取得費 | 譲渡所得税 |
| 2,000万円 | 100万円 | 1,500万円 | 81.26万円 |
| 不明 (100万円) | 365.67万円 | ||
上記のとおり、土地の取得費が確認できたほうが、納める税金の額を大きく抑えられることがわかります。
相続した土地の売却で節税したい方は、売買契約書や住宅ローンの契約書など、取得費がわかる書類を探しましょう。
譲渡費用はすべて計上する
土地の売却でかかった譲渡費用は、譲渡所得税を算出するときにすべて計上してください。
課税対象の課税譲渡所得金額を算出する際、譲渡費用を差し引けるため、できる限り計上したほうが納める税金額を抑えられます。
計上できる譲渡費用の一例は、次のとおりです。
- 不動産会社への仲介手数料
- 売買契約書の印紙代
- 売却活動での広告費
- 売却のために依頼した測量費
上記のとおり土地の売却を目的にして支払った費用は、譲渡費用に計上できます。
ただし、抵当権抹消費用や維持管理費など譲渡費用として認められない支出もあるため、判断に迷う方は税理士や税務署に確認しましょう。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税を活用すると、住民税や所得税の控除により税負担を軽減できる仕組みとして利用できます。
ふるさと納税をすると、自身が選んだ自治体に寄付することで、寄付額から2,000円を引いた金額が、翌年の住民税から控除、および所得税から還付されます。
ふるさと納税は節税効果に加えて、寄付した自治体から返礼品がもらえる点も大きなメリットです。
寄付限度額は土地売却で得た譲渡所得や年収などで異なるため、ふるさと納税を考えている方は、各サイトにあるシミュレーターで試算してみましょう。
相続した不動産を売却するときの流れ

相続した土地を売却するまでの流れを解説します。
故人の土地の売却を検討している方や、どのように進めたらよいかわからず不安な方は、ぜひ参考にしてください。
1.相続手続きの完了
相続が発生したら、7日以内に亡くなった方の死亡地か本籍地、届出人の所在地の市区町村役場に死亡届を提出します。
その後、相続人や遺言書の有無などを調査し、相続方法を決めましょう。遺言書がある場合は、故人の遺言の内容にしたがって相続を進めます。
遺言書がないうえに相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議をする必要があります。
土地を相続する方が決まったら、不動産の名義を故人から相続人に変更する相続登記をおこなってください。
2.不動産の価値評価
相続した土地を売却する際には、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
1社ではなく複数の不動産会社に査定を依頼し、どのくらいの価格で売却できるのかを調査しましょう。
査定は基本的に無料です。複数の査定結果を比較し、さらに自身でも周辺物件の価格を調査して、売却見込み額の見当をつけましょう。
なお、価格の調査には不動産ポータルサイトや国土交通省が公開している不動産情報ライブラリがおすすめです。
3.不動産会社との媒介契約
査定を依頼した不動産会社のなかから、信頼できそうな業者と媒介契約を締結します。なお、媒介契約の種類は以下の3つです。
| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 複数社との契約 | 〇 | × | × |
| 指定流通機構(レインズ)への登録 | 任意 | 義務 (7営業日以内) | 義務 (5営業日以内) |
| 不動産会社の売主への業務報告 | 任意 | 義務 2週間に1回以上 | 義務 1週間に1回以上 |
| 自己発見取引 (売主が自ら発見した相手との契約) | 〇 | 〇 | × 必ず媒介契約を結んだ不動産会社を介して契約する必要あり |
| 契約有効期間 | 法律上の制限なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
※ 全日本不動産協会、一般媒介契約
※ 媒介契約とは?
土地の需要や不動産会社の営業力などによって、売却金額や成約までの期間は左右されるため、どの契約形態がよいかは難しいポイントです。
人気があるエリアの土地であれば一般媒介契約、信頼できる業者に任せたいのであれば、専任または専属専任媒介契約がよいでしょう。
4.売り出し
信頼できる業者と媒介契約を締結したら、実際に土地を売り出します。不動産会社と相談して、売り出し価格を決定しましょう。
不動産のポータルサイトや自社SNSなどで情報発信をする関係上、土地だけでなく中古戸建てとしても売却するのであれば間取り図の作成や家屋の外観、内観の写真撮影に協力する必要があります。
相続した土地の場合は、不動産会社が内覧に対応するため、必ずしも立ち会わなければならないわけではありません。
ただし業者に任せっきりにするのではなく、どの程度の問い合わせや内覧があるのかは、定期的に確認しましょう。
なお、不動産会社と締結する媒介契約が専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約であれば、不動産会社から定期的に営業報告を受けることができます。
5.買主との交渉と契約
購入希望者が見つかったら、価格交渉を経て契約に至るのが一般的です。売買金額に折り合いが付き、条件に合意したら売買契約を締結します。
多くの場合、売買契約は買主や売主、司法書士同席のもと、不動産会社の事務所でおこなわれます。
重要事項説明や引き渡しまでのスケジュール調整などをおこなうため、不明点や疑問点がある場合は確認しておきましょう。
売買契約を締結するタイミングで買主より手付金を受領し、土地を引き渡す日に残金を決済するケースが一般的です。
6.決済・引き渡し
相続した土地の売買契約後は片付けや引っ越し、必要書類の準備など、スケジュールどおりに引き渡すための準備を進めましょう。
決済は平日の午前中におこなわれるケースが多く、何かトラブルがあった場合でも、当日中に対応できるようにするのが一般的です。
決済後は不動産登記の手続きや鍵・書類の引渡しなどをおこないます。
引渡しや決済には不動産会社の担当が同席するため、不安点や疑問点は随時確認しながら進めてください。
7.確定申告・税金納付
相続した土地を売却したら、相続税の申告をおこない納税する必要があります。
また、相続した土地の売却で利益が出ている場合は、翌年の2月16日〜3月15日にかけて、確定申告をしなければなりませんが、相続税の申告と納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内におこなわなければならないため、注意が必要です。
相続税や土地の売却での税金は申告しなくてもよかったり、納付はないけれど確定申告が必要だったりするケースもあるため、専門家への相談がおすすめです。
相続した土地の売却相談はファンズ不動産へ
相続した土地の売却は、名義変更や評価額の確認、売却後の確定申告など、通常の不動産売却よりも確認すべき項目が多く、複雑に感じやすい手続きです。
特に、3年以内に活用できる特別控除や税金の扱いは、タイミングによって負担額が大きく変わるため、早めの判断が重要になります。
相続後の売却をどのタイミングで進めるべきか迷っている方や、税金まわりを整理したい方は、ファンズ不動産へ相談してみてはいかがでしょうか。状況に応じた適切な進め方のヒントが得られ、安心して売却を検討できます。
信頼度の高い買主とマッチングが可能
ファンズ不動産は、キュレーターの価値観に「共感」した、購買意欲の高いユーザーへ物件情報を届けます。
キュレーターは日頃からSNSで専門知識やライフスタイルを発信しており、人柄や実績が公開されています。
そのため単なる物件情報としてではなく、「あのキュレーターが勧める物件」という信頼度の高い情報として不動産情報を届けることが可能です。
情報発信のプロセスを介することで、物件の背景にあるストーリーや価値観を理解してくれる買主と出会う確率も高められるでしょう。
ぜひファンズ不動産で、物件への想いを共有できる「信頼できる買主」とのマッチングを実現してみましょう。
売却査定から引渡しまで、安心のワンストップ対応
ファンズ不動産は、LINEを活用した効率的なプロセスと、幅広い専門知識でスムーズな不動産売却を実現します。
相談は「オンライン面談」から始まり、やり取りもLINEメインでおこなうため、店舗へ足を運ぶ手間も最小限です。
また土地のプロやリノベーションの専門家も在籍しているので、専門知識が必要な相談も窓口一つで完結します。忙しい方でも、スムーズで安心な売却活動が可能です。
日中は仕事で時間が取れない方や、複雑な手続きをまとめて任せたい方でも、ストレスなく売却活動を進められます。
リノベ前提の物件や土地売却も。専門チームが対応
ファンズ不動産は、一般的なマンションや戸建てだけでなく、専門知識が求められる不動産の売却にも対応しています。
社内には土地売買のプロが在籍しているほか、2025年10月からはリノベーションのワンストップサポートも開始しました。
そのため「リノベーション前提」といった付加価値を付けた売却提案や、複雑な権利関係が絡む土地の売却も、窓口一つでスムーズに進められます。
他社では取り扱いが難しいと言われた物件でも、まずは一度相談してみる価値があるでしょう。
相続した土地を売却するメリット

相続した土地を売却する主なメリットは、次のとおりです。
- 土地の維持費を負担する必要がない
- 相続税の納税資金を用意できる
- 取得費加算の特例を活用できる
- 遺産分割や土地活用の方法で悩む必要がなくなる
それぞれのメリットを具体的に解説します。
土地の維持費を負担する必要がない
相続で取得した土地を売却すると、管理費や税金などの維持費を負担しなくてもよくなるのが利点の一つです。
不動産所有者は、利用していなくても毎年固定資産税や地域によっては都市計画税が課されるため、税金が大きな負担になることも少なくありません。
また不動産には管理義務があり、周辺に迷惑がかからないよう掃除や雑草取りをする必要があります。
自身で管理する場合は交通費や実費、業者に依頼する場合は依頼費用がかかりますが、相続した土地を売却すると維持費はかからない点がメリットです。
相続税の納税資金を用意できる
相続税の納税資金が手元にない場合、相続した土地を売却して必要なお金を用意できます。
基礎控除の金額が大きいため、一般的な家庭であれば基本的に相続税の納付は発生しません。
しかし、土地を含めた故人の財産が多額の場合は相続税が発生し、遺産のなかに現金の割合が少ない場合は、税金を納付する資金が不足します。
上記のような場合は相続した土地を売却すれば、相続税を納付するための資金を確保しやすいでしょう。
取得費加算の特例を活用できる
相続税を納税している場合は、土地の売却によって取得費加算の特例を活用できます。
取得費加算の特例とは、相続した土地を相続発生から3年10か月以内に売却すれば、納付した相続税の一定金額を取得費に加算できる特例です。
取得費加算の特例を活用すれば、支払った相続税の一部を取得費として譲渡費用から差し引けるため、譲渡所得税を軽減できます。
特例の適用を受ける要件や計算方法などを知りたい方は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」のページを参考にしてください。
遺産分割や土地活用の方法で悩む必要がなくなる
遺産の分配や土地活用で悩む必要がなくなる点も、相続した土地を売却する一つのメリットです。
不動産を売却して現金化すれば、複数の相続人に分配するのが簡単になり、公平性もあることから遺産相続でトラブルになりにくいでしょう。
また相続した土地を売却すれば、賃貸物件を建てて不動産所得を得るべきか、定期借地権で貸し出すべきかなど、活用方法に悩まなくて済みます。
遺産分割で揉めたくない、土地活用は面倒なので避けたいと考える方は、相続した土地を売却するのが有力な選択肢でしょう。
相続した土地を売却するデメリット

相続した土地を売却するメリットがある一方で、デメリットもあります。
デメリットも把握したうえで、相続した土地を売却するのかを判断しましょう。
土地の所有権を失い将来的な土地活用ができない
相続した土地を売却して所有権を失うと、将来的な土地活用ができなくなります。
賃貸経営をして不動産所得を得たり、将来地価が上昇したときに売却益を得たりする機会を失う点に注意が必要です。
また、相続した土地を売却すると、子どもや孫世代の居住用地としての活用もできなくなります。
相続した土地を活用して不動産所得を得たい、将来子どもや孫に残したいと考える方はすぐには売却せず、慎重に判断したほうがよいでしょう。
税金や売却費用が発生する
土地を売却する際には、税金や売却費用が発生します。
売却金額がそのまま手取りの収入になるわけではなく、考えていたより手元に残るお金が少ないと感じるケースもあるため注意が必要です。
相続した土地の取得費が想定よりも低く、相続後の値上がり額が大きいと、想定以上の税負担となる可能性があります。
また土地の売却では測量費や解体費など、さまざまな費用が発生する可能性があるため、事前に把握しておくのをおすすめします。
相続した土地を売却する際は、不動産会社に相談しながら見積もりを依頼し、あらかじめシミュレーションしておきましょう。
相続した土地を売却するときの注意点

相続で取得した土地を売る際、遺産分割でトラブルになったり、売却がスムーズに進まなかったりする可能性があるため注意が必要です。
事前に注意点を把握しておき、避けられるリスクは対策しておきましょう。
遺産分割協議がまとまるとは限らない
遺産の分け方は相続人全員による遺産分割協議で決定します。
「誰が土地を相続するのか」「土地を売却して現金化してもよいか」などの決定は、相続人全員の同意が必要です。
相続人が多いほど全員の合意形成が難しくなるため、売却したくても話がまとまるとは限りません。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停や審判といった手続きを利用する可能性もあります。
売却が進まないと資産価値が下落する
相続した土地を売ろうとしてもスムーズに売却活動が進まず、資産価値が下落していくリスクもあります。
売却活動中に不動産市況が悪化したり、金利が上昇したりすると、土地の価値が低下する可能性があるためです。
とくに人口減少が進んでいる地域では、早めに売却しないと資産価値が下がっていき、当然ながら売り出し価格も下げなければなりません。
相続した土地を売ろうと考えている方は、不動産需要も加味しながら、相場が下がりそうであれば早めに売却する必要があります。
売却タイミングを見極める必要がある
相続した土地を高い価格で売却するためには、不動産市況の変化を考慮しつつ、タイミングを見極める必要があります。
売却のタイミングを見誤ると、市場の下落期に売却してしまい、本来よりも安い価格で売却する事態になりかねません。
一般的には、転勤や進学などで新生活がはじまる前後である2月〜3月、9月〜11月は不動産取引が活発になる時期です。
他にも経済状況や周辺環境の変化も、適切な売却のタイミングを左右するため、気軽に相談できる不動産会社を選ぶことが大切です。
土地が売却できないときに検討すべき「相続土地国庫帰属制度」

相続した土地を手放したいにもかかわらず売却できないときは、相続土地国庫帰属制度を検討しましょう。
2023年4月27日からはじまった相続土地国庫帰属制度とは、一定の要件を満たした土地を国に引き取ってもらう制度です。
売却が難しい土地でも相続人には管理義務があり、維持費もかかり続けるため、負担となるケースも珍しくありません。
相続土地国庫帰属制度で相続した土地を国に引き取ってもらえれば、活用が難しい土地を手放せて、所有者の負担を軽減できます。
ただし制度の利用には要件があり、負担金も納付する必要があるため、詳しく知りたい方は法務局のページを参考にしてください。
相続した土地の売却に関するよくある質問
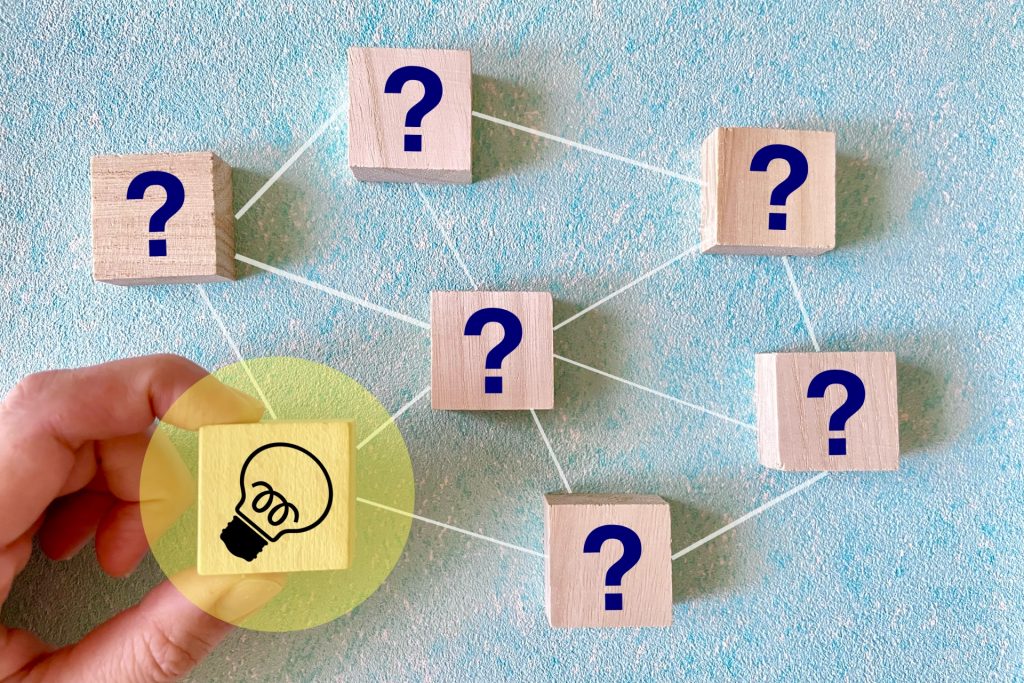
相続した土地の売却に関して、よくある質問と回答をまとめました。
疑問を抱く点や気になる質問があれば、ぜひ参考にしてください。
相続した土地を兄弟で分ける方法は?
亡くなった方から相続した土地を兄弟で分ける方法は、主に次のとおりです。
| 分割方法 | 内容 |
|---|---|
| 換価分割 | 売却後現金を分ける |
| 現物分割 | 土地を物理的に分ける |
| 共有名義 | 複数の相続人で土地を所有 |
換価分割は公平性が保たれやすいため、故人から相続した土地を分けるのに向いているでしょう。
相続せずに土地を売却できる?
相続せずに土地は売却できません。不動産を売却するためには、相続人の名義に変更する相続登記をする必要があります。
なお、令和6年4月1日から相続登記の申請は法律上の義務となり、取得を知った日から3年以内(過去の相続の場合は2027年3月31日まで)に手続きをしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
売却の有無にかかわらず義務なので、忘れずに手続きをしましょう。
しかし、相続登記は申請して即日に完了するものではありません。戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、準備だけで数ヶ月かかるケースもあります。
買い手が現れてから慌てることがないよう、売却を検討し始めた段階で、早めに名義変更の準備に着手することをおすすめします。
相続した土地を5年以内に売却する際の注意点は?
相続した土地を5年以内に売却する際は、次の点に注意する必要があります。
- 土地の所有期間
- 譲渡所得税が発生するか
- 特例が利用できるか
- 不動産市場動向
とくに相続に関する特例は、約3年間と期間が定められているため、適用を受けたい場合は注意が必要です。
まとめ
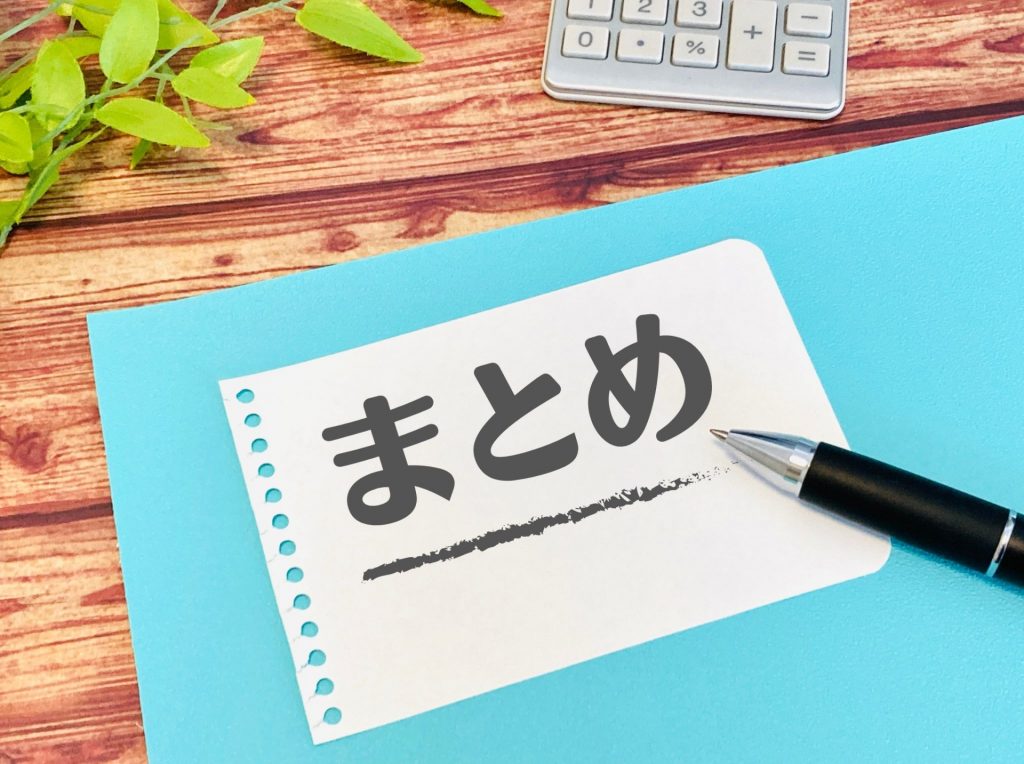
相続した土地を売却する際に発生する税金やすぐに売却したほうがよいケース、利用できる特例などを解説しました。
相続した土地を売却する際には、登録免許税・印紙税・譲渡所得税などの税金が発生する場合があります。
ただし、3,000万円特別控除や軽減税率の特例、取得費加算の特例などを活用すれば節税できるため、要件に該当するか確認してください。
相続で取得した土地を売却しようと考えている方は、本記事の内容を参考に各種手続きを進め、遺産相続でのリスクを避けるようにしましょう。













