亡くなった親の家を売る際に、「相続で必要な手続きを知りたい」「どのように進めたらよいのだろうか」と考える方もいるでしょう。
相続を経験している方は多くはないため、親名義の家をどうしたらよいのかわからず、不安になるときもあるのではないでしょうか。
亡くなった親の家を売る場合は、まず相続登記をして名義人を変更してから、不動産会社に売却を依頼する必要があります。
本記事では、亡くなった親の家を売るときの流れや少しでも高く売却するコツ、発生する税金や節税する方法などを解説します。
相続の進め方がわからない方や、親名義の家の売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
亡くなった親名義の家を相続せずに売却できる?

相続を経験していない方は、亡くなった親名義の家をどのようにすればよいか悩む方もいるでしょう。
故人名義の不動産を相続せずに売却できるのかや、法定相続人の決め方などを解説します。
相続しないと売却できない
亡くなった親名義の家を売却する際は、相続の手続きをしないと売却できません。
親名義の不動産を管轄している法務局で、所有権移転登記を申請して、相続登記をする必要があります。
相続の手続きは自身でもできますが、法務局に行く時間がない、やり方がわからないという場合は司法書士への依頼も可能です。
亡くなった親名義の不動産の売却を検討している場合は、誰を名義人にするかを決めて、相続人に所有権を移転させてください。
法定相続人・法定相続分の決め方
亡くなった親が遺言書を残していない場合、法定相続順位どおりに相続人が決まります。民法で定められた法定相続順位は、次のとおりです。
- 配偶者
- 子ども
- 祖父母
- 兄弟姉妹
また、親が亡くなった際の法定相続分の主なケースは、次の表を参考にしてください。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者・子ども | 配偶者:1/2 子ども:1/2を人数で分割 |
| 子どものみ | 子どもの人数で分割 |
上記のとおり両親ともにおらず、子どもが1人であればすべて相続し、複数人いる場合は人数で分割します。
法定相続人と法定相続分のルールを把握しておき、相続の話し合いや手続きを進めましょう。
亡くなった親の家を分割相続する方法

亡くなった親の家を複数人の子どもで分割相続する方法や特徴は、次のとおりです。
| 分割方法 | やり方 | 特徴 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産の種類を分割する | シンプルだが不平等になりやすい |
| 代償分割 | 1人が家を取得し、他の相続人に代償金を支払う | 家を所有できる一方で現金が必要 |
| 換価分割 | 不動産を売却して分配する | 売却に手間がかかるが公平になりやすい |
| 共有分割 | 家を共有名義で所有する | 手続きが簡単だが売却時に全員の同意がいる |
それぞれの分割方法を詳しく解説します。
現物分割
現物分割とは、亡くなった親の財産をそれぞれの相続人が、現物の状態で相続する分割方法です。
親名義の家や預貯金、株式などを兄弟で分け合う分割方法で、一例は次の表を参考にしてください。
| 長男 | 次男 | 三男 |
|---|---|---|
| 家 | 預貯金 | 株式、車 |
上記のとおり財産の種類別に相続するためシンプルな一方、家と他の財産の価値が同じではないケースであれば、公平性に欠ける分割方法です。
話し合いによってそれぞれの相続人が納得できるケースや、財産の分配が公平になるのであれば、現物分割が向いています。
代償分割
代償分割は、1人が亡くなった親の不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して価値にあわせた代償金を支払う分割方法です。
親が住んでいた家に住める、平等な相続ができるなどのメリットがある一方、代償分割をすると名義人になる方は現金が必要になります。
ただし、代償金を支払えば亡くなった親の家を自由にできるため、売却を急がなくてよい点もメリットでしょう。
親の家を残したいと考えている、または代償金を支払える資金がある場合は、代償分割が適しています。
換価分割
換価分割は亡くなった親の家を売り、得られた金額を相続人で分ける分割方法です。
トラブルが発生することも多い相続ですが、公平に財産を分割できるため、兄弟で揉めるのを避けたい方に向いています。
換価分割の場合は誰か1人が名義人になり、不動産を売却して他の相続人にお金を分ける形が一般的です。
相場を知らずに売買価格を設定したり、焦って処分しようとしたりすると、安く売却するおそれがあるため、信頼できる不動産会社を選ぶ必要があります。
共有分割
共有分割は、亡くなった親の家を相続人で共有する分割方法です。
不動産を共有名義にして相続するため、名義変更のみで済むうえに公平性が保たれやすい点がメリットでしょう。
ただし、売却する際は名義人全員の同意が必要になり、兄弟間でトラブルに発展する可能性もあります。
親が住んでいた家を残したい、兄弟間で揉める心配はないなどの場合は、共有分割を検討してください。
亡くなった親の家を売る流れと手続き

亡くなった親の家を売る際の流れや手続きは次のとおりです。
- STEP1:名義変更(相続登記)
- STEP2:不動産会社に査定を依頼する
- STEP3:媒介契約を締結し、売却活動開始
- STEP4:売買契約締結
- STEP5:決済・物件の引渡し
- STEP6:確定申告をする
それぞれの段階を解説するため、家を相続する方は参考にしてください。
STEP1:名義変更(相続登記)
不動産は、亡くなった被相続人の名義のまま売却できません。誰が不動産を相続するかが決まれば、名義変更が必要です。
このときの手続きを相続登記といいますが、2024年4月1日から義務化されました。
名義変更に必要な書類
被相続人から相続人へ名義変更するには、次の書類が必要です。
| 誰のもの | 必要書類 | 入手先 |
|---|---|---|
| 【遺産分割方法関係なく必要な書類】 | ||
| 被相続人 | 戸籍謄本 (出生から死亡までの戸籍・除籍謄本) | 本籍地の市区町村 |
| 住民票の除票または戸籍の附票 | 住所地の市区町村本籍地の市区町村 | |
| 法定相続人 | 戸籍謄本(抄本) | 本籍地の市区町村 |
| 固定資産税課税明細書 | 不動産の所在地の市区町村から毎年4月頃に送付 | |
| 【遺産分割協議による相続の必要書類】 | ||
| 法定相続人 | 遺産分割協議書 | 相続人か専門家が作成 |
| 印鑑証明書 (遺産分割協議書に押印されたもの) | 住所地の市区町村 | |
| 法定相続人のうち 不動産の所有者になる人 | 住民票 | 住所地の市区町村 |
| 【法定相続分による相続の必要書類】 | ||
| 法定相続人 | 住民票 | 住所地の市区町村 |
| 【遺言書による相続の必要書類】※法定相続人が相続する場合 | ||
| 被相続人 | 遺言書 | 自宅や法務局等 |
| 所有者になる人 | 戸籍謄本(抄本) | 本籍地の市区町村 |
このほか、法務局に登記申請するための登記申請書を作成しなければなりません。司法書士に申請手続きを依頼する場合は委任状が必要です。
STEP2:不動産会社に査定を依頼する
相続した不動産の名義変更が終われば、不動産会社に査定を依頼します。
査定の目的は2つです。1つは、売り出し価格を決めるための査定価格や相場を知ること、もう1つは、売却を依頼する不動産会社を決めることです。
できるだけ高く売却したいならば、複数の不動産会社に査定を依頼してみましょう。
また、不動産会社が査定に来るまでに、登記識別情報(権利証)や不動産を購入したときの売買契約書、重要事項説明、固定資産税課税明細書など準備できるものは準備しましょう。
STEP3:媒介契約を締結し、売却活動開始
売却を依頼する不動産会社が決まれば、媒介契約を締結します。
媒介契約には、複数の不動産会社に依頼できる「一般媒介契約」のほか、1社に依頼する「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあります。
それぞれの特徴を把握したうえで、不動産会社の業務内容や契約期間、仲介手数料がかかる時期など契約内容をしっかりと理解して進めることが大切です。疑問点があれば遠慮なく担当者に確認しましょう。
査定結果をもとに売り出し価格を決めたら、売却活動を開始します。不動産ポータルサイトへ物件が登録され、購入希望者を募集します。
STEP4:売買契約締結
購入希望者が見つかれば、購入の正式な意思表示として不動産購入申込書を受け取ります。
このとき、価格や引渡し時期などの条件交渉が入る場合もあります。交渉にどこまで応じるかは不動産会社と相談しながら決めましょう。
買主と条件面で合意できれば、売買契約に進みます。売買契約に先立って、不動産会社が買主に重要事項説明を行い、その後、売買契約書の読み合わせをして、双方に納得したうえで契約締結です。
売買契約時は、買主から手付金を受領するとともに、売買契約書の印紙代や不動産会社の仲介手数料(半金)が必要となります。
STEP5:決済・物件の引渡し
最後に、売買代金の残金や固定資産税精算金などの諸費用をすべて精算し(決済)、物件を引渡します。
建物内の残置物の撤去などが必要であれば、引渡し日に間に合うように進めることが必要です。
STEP6:確定申告をする
亡くなった親の家を売り、利益(譲渡所得)が出た際は、確定申告が必要になります。
確定申告は親の不動産を売却した翌年、2月16日〜3月15日の期間でおこない、算出された税金を納付します。
後ほど「亡くなった親の家を売るときの税金の特例」の章で、節税になる特例を解説するため参考にしてください。
亡くなった親の家を少しでも高く売るコツ

亡くなった親の家を相続した際、できる限り高い金額で売却したいと考える方が大半でしょう。
相続した不動産を少しでも高く売るためのコツについて解説します。
相続開始から売却までのスケジュールに余裕をもつ
相続が発生してから売却までのスケジュールには、できる限り余裕を持ちましょう。
売却にかけられる期間が短くなると、売り急いで価格を下げざるを得なくなったり、価格交渉に応じなければならない状況になったりして、結果的に売却価格が下がってしまう恐れがあります。
不動産の売却期間は、物件の登録から成約まで平均3~4か月です。相続不動産の場合、相続財産の確定や遺産分割協議に時間がかかることもあります。
できるだけ余裕を持ったスケジュールで売却を進めることが高値売却のポイントです。
複数の不動産会社に査定を依頼する
亡くなった親の家をできる限り高く売りたい方は、複数の不動産会社に査定を依頼してください。
複数の不動産会社に査定を依頼すれば「相場価格がわかる」「担当者の対応を比較できる」などのメリットがあります。
目安として3〜5社程度の不動産会社に査定を依頼すれば、信頼できる業者や担当者を見つけられるでしょう。
複数の不動産会社に査定依頼をするのが手間に感じる方は、一括査定サイトを利用すれば、一度の入力で複数社の査定結果を受け取れます。
取り壊して更地にすることも検討する
相続した不動産が、築年数が経過した一戸建ての場合、取り壊して更地にすることで高く売れる場合があります。
メンテナンスの状況などにもよりますが、木造住宅の場合、一般的に20~25年で建物の価値はほとんどなくなる傾向にあります。
こうした建物を売却するときは、古家付の土地として売却する方法と、建物を解体して更地にする方法の2つがあります。
どちらの方法も、建物の価値を売却価格に反映させずに売る方法です。
更地にした方が購入者は解体費用を考える必要がなく、また土地全体の状況を把握し、新築後のイメージがしやすくなるため、流通性が上がり高く売却できることがあります。
ただし、解体費用や家財の回収費用などがかかりますので、不動産会社と相談しながら進めるようにしましょう。
亡くなった親の家の売却手続きで迷ったらファンズ不動産へ
亡くなった親の家を売却する場合、相続手続きや名義変更、税金の負担など、進めるべきステップが多く戸惑う方は少なくありません。
特に、どの順番で手続きすべきか、どの税金が発生するのかを理解しておくことは、スムーズな売却につながる大切なポイントです。
状況によって最適な選択肢は異なるため、早い段階で相談できる相手がいると安心して判断できます。ファンズ不動産では、相続した家の売却に関する悩みにも丁寧に寄り添い、状況に合わせた進め方を一緒に検討できます。
「何から始めればいいのか不安」という方も、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
売却査定から引渡しまで、安心のワンストップ対応
ファンズ不動産は、LINEを活用した効率的なプロセスと、幅広い専門知識でスムーズな不動産売却を実現します。
相談は「オンライン面談」から始まり、やり取りもLINEメインでおこなうため、店舗へ足を運ぶ手間も最小限です。
また土地のプロやリノベーションの専門家も在籍しているので、専門知識が必要な相談も窓口一つで完結します。忙しい方でも、スムーズで安心な売却活動が可能です。
日中は仕事で時間が取れない方や、複雑な手続きをまとめて任せたい方でも、ストレスなく売却活動を進められます。
売却が初めての方へ:ファンズ不動産が選ばれる3つの強み
ファンズ不動産は、売主様が抱える不安を解消する、独自の「訴求力」「専門性」「手軽さ」を兼ね備えています。
- 訴求力:1万人超のLINE登録者へ直接情報を届ける高い「訴求力」が、早期の買主発見をサポートします。
- 専門性:都心特化・設立1年半で取扱高100億円を突破した「専門性」が、適正な価格設定と売却戦略を実現。
- 手軽さ:オンライン面談からLINEで活動を進められる「手軽さ」が、忙しい方でもスムーズな売却を可能にします。
初めての売却で不安をお持ちなら、まずはLINEでの気軽なご相談から、納得のいく売却への第一歩を踏み出しましょう。
購買意欲の高いユーザーへ能動的にアプローチできる
ファンズ不動産が運営する「SNS不動産®」は、LINEで購買意欲の高いユーザーに不動産情報を届けます。
従来のポータルサイトで「待つ」のではなく、1万人超のLINE登録者へ能動的にアプローチできる点は大きな強みです。
さらに都心に精通した担当者が的確な売却戦略でサポートするため、物件の魅力を最大限に引き出す価格設定と販売活動がおこなえるでしょう。
購買意欲の高いユーザーへ「届ける」力と、物件価値を引き出す「専門家の戦略」が組み合わさることで、「高く・早く」売却できる可能性を最大化できます。
亡くなった親の家を売ることで生じる税金

亡くなった親の家を売ると生じる税金は、次のとおりです。
- 登録免許税
- 印紙税
- 相続税
- 譲渡所得税
それぞれの税金を解説するため、必要に応じて専門家に聞きながら納税の手続きを進めてください。
登録免許税
遺産分割方法が決まり不動産を相続する人が決まれば、被相続人から相続人に所有権移転登記をします。このときにかかるのが登録免許税です。
相続による所有権移転登記の登録免許税は以下の計算式で求めます。※1
登録免許税額=固定資産税評価額×0.4%
固定資産税評価額は、毎年1月1日時点の所有者宛てに送られる固定資産税課税通知書に記載されています。
司法書士に相続登記を依頼する場合は、登記費用の見積もりのなかで確認できます。
印紙税
売買契約時に印紙税が必要です。印紙税は、売買契約書などの課税文書にかかる税金です。
税額は、売買契約書に記載された契約金額で異なります。以下は、10万円超えから10億円以下までの印紙税額をまとめたものです。
| 記載された契約金額 | 税額 | 軽減後の税額 (2027年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
※税額は一部を抜粋しています。
収入印紙を郵便局や法務局で購入し、契約書に貼付したあとに消印を押して、印紙税の納付は完了します。
相続税
相続税がかかる場合、相続の開始があった日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に納付しなければなりません。
まずは亡くなった親の家をはじめ、相続税の対象になる財産(課税財産)を把握しましょう。相続税の簡単な計算式は次のとおりです。
課税財産−基礎控除=課税遺産総額
基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)のため、法定相続人が子ども2人の場合の基礎控除は4,200万円です。
また相続税の計算の主な流れは、次のとおりです。
- 課税財産の総額を計算
- 基礎控除を引いて課税遺産総額を算出
- 一度法定相続分で相続人ごとの税額を算出
- 相続人全員の税額を合算
- 遺産分割協議で決めた割合で再度按分
相続税の計算方法は複雑なため、必要に応じて税理士をはじめとした専門家に相談しながら進めてください。
譲渡所得税
亡くなった親の家を売り、利益(譲渡所得)が出た場合は譲渡所得税が発生します。譲渡所得税の計算方法は、次のとおりです。
譲渡所得×税率=譲渡所得税
また譲渡所得税率は、物件の所有期間によって次のように異なります。
| 不動産の所有期間 | 譲渡所得税の税率 |
|---|---|
| 5年以下 | 39.63% |
| 5年超〜10年以下 | 20.315% |
| 10年超 | 14.21%(6,000万円超の部分は20.315%) ※特例の軽減税率適用後の例、マイホーム(居住用財産)の売却」に限定される |
不動産を売却した際に利益が出ていない場合や、特例ですべて控除されるケースは、譲渡所得税は発生しません。
亡くなった親の家を売るときの税金の特例

亡くなった親の家を売るときに利用できる税金の特例は、次のとおりです。
- 取得費加算の特例
- 空き家を売ったときの特例
- 小規模宅地等の特例
- マイホームを売ったときの特例
- 低未利用土地等を売ったときの特例
それぞれ特例の内容や簡単な要件を解説するため、ぜひ参考にしてください。
取得費加算の特例
相続税をすでに納税している場合は、取得費加算の特例を利用できます。
譲渡所得から納付した相続税の一部を差し引けるため、譲渡所得税の負担が軽減されます。
取得費加算の特例が適用される要件は、次のとおりです。
- 相続や遺贈により財産を取得した方
- 財産を取得した方に相続税が課税されている
- 財産の相続開始から3年10か月以内に譲渡している
計算方法や手続きに関して知りたい方は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を参考にしてください。
空き家を売ったときの特例
相続した親の物件に誰も住んでいない場合は、空き家を売ったときの特例が利用できる可能性があります。
空き家を売ったときの特例とは、売却して得た譲渡益から3,000万円を控除できる制度で、主に次の要件を満たしていれば利用可能です。
- 昭和56年5月31日以前に建築されている
- 居住用の建物として利用されていた
- 相続開始の直前に相続人以外居住していた方がいない
- 相続を開始して3年が経過する年の12月31日までの譲渡
- 売買価格が1億円以内
古い空き家をなくす目的の特例で、誰かが住んでいる場合は利用できません。
空き家を売ったときの特例は要件が多いため、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を確認するか、専門家に問い合わせてください。
小規模宅地等の特例
亡くなった親の家や事業用の不動産は、要件が当てはまれば小規模宅地等の特例が利用できる可能性があります。
小規模宅地等の特例は、不動産の評価額を最大80%下げられ、相続税の負担を軽減できる制度です。
利用できる可能性のある方は、次のとおりです。
- 配偶者
- 同居していた子どもや親族
- 要件を満たしている同居親族以外
小規模宅地等の特例は、対象となる不動産の種類や広さ、どの相続人が利用できるかなど要件が複雑です。
相続時に小規模宅地等の特例を利用できるか知りたい方は、税理士や税務署に聞いてみましょう。
また、国税庁の「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」のページも参考にしてください。
マイホームを売ったときの特例
亡くなった親の家に自身も住んでいた場合は、マイホームを売ったときの特例を利用できる可能性があります。
3,000万円の特別控除を受けられるため、売却したときに利益が3,000万円までなら譲渡所得税が発生しません。
マイホームを売ったときの特例の主な要件は、次のとおりです。
- 居住用の不動産(別荘、賃貸物件は不可)
- 売却先が親族以外
- 指定の特例の適用を受けていない
要件を詳しく知りたい方は、「マイホームを売ったときの特例」のページを参考にしてください。
低未利用土地等を売ったときの特例
亡くなった親の家を売った際、売却価格が500万円以下で他の要件も満たしていれば、低未利用土地等を売ったときの特例を利用できます。
低未利用土地等を売った特例の適用を受けられれば、譲渡所得から100万円を控除できて節税になります。
100万円の特別控除を受けられる特例の、主な要件は次のとおりです。
- 売却した不動産が都市計画地域内にある
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている
- 売却先が親子や親族以外
- 売買価格が500万円以下
詳しい要件や内容を知りたい方は、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」を参考にしてください。
亡くなった親の家を売るときの注意点

相続した家に相続人が住んでいないことも多いため、売却するときに注意すべき点もあります。
亡くなった親の家を売る際に意識したい点を解説するため、参考にしてください。
家の片付け・遺品整理をしておく
亡くなった親の家を売る場合、まずは家の片付けや遺品整理をする必要があります。
遺品や不用品を整理すれば、物件のなかをきれいに掃除でき、亡くなった親の家を売却しやすくなるでしょう。
遺品整理は時間がかかるため、専門の業者に依頼するのも選択肢の一つですが、家が広ければ数十万円程度の費用が発生します。
親の家を売却する際は、まず自身や業者への依頼で片付けや遺品整理をおこない、家のなかをきれいにしてください。
共有名義の場合は相続人と話し合う
亡くなった親の家を共有名義で相続している場合、売却するためには相続人全員の同意が必要です。
売却を検討する際は、共有名義になっている相続人同士で話し合いをしましょう。
全員が同意すればスムーズに売却できますが、反対された場合は次のような対処法をする必要があります。
- 自身の共有持分のみ売却する
- 他の名義人に自身の共有持分を売却する
- 他の共有持分をすべて買い取る
相続人同士のトラブルに発展しないよう事前によく話し合い、亡くなった親の家の売却を進めてください。
相続税の申告期限に注意する
相続税は、相続発生の翌日から10か月以内に、原則現金一括で納める必要があります。ただし、納税資金の準備が難しい場合には、延納(分割払い)や物納(不動産での納付)といった方法も認められています。
相続税を納付する現金が準備できる場合は別として、不動産を売って納税資金に充てる場合は早めに売却活動をはじめてください。
相続開始から売却までの流れは以下のとおりです。
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議
- 相続登記
- 売却依頼・開始
- 売買契約締結
- 決済・引渡し
相続財産の調査に時間がかかる場合や遺産分割協議がなかなかまとまらないケースも考えられます。また、売却時の土地の境界確定に時間を要する可能性もあるでしょう。
もし、申告期限を過ぎてしまった場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できなくなる可能性があります。
また、申告期限を過ぎたペナルティとして無申告加算税が課せられるため、注意が必要です。
隣地との境界が明確になっているか確認
土地や一戸建てを相続して売却する場合、隣地との境界が明確になっているか確認することが重要です。
土地を売却するには、売主が境界を明示することが原則です。境界が曖昧な場合は、確定測量し、隣地の所有者の合意を含めて境界の確定が必要となる場合もあるでしょう。
隣接地の数が多い場合など、思った以上に時間も費用もかかる場合があります。
また、相続人が相続した土地の状況を把握していないケースも多く、隣接地の所有者との関係が良くない、境界トラブルを抱えている可能性もあります。
境界トラブルの内容によっては、売買契約時の告知事項に該当し、売却価格に影響する可能性もあるでしょう。
物件の状態を正確に把握する
売主は売買契約にあたり、原則として契約不適合責任を負います。契約不適合責任とは、売買の目的物が数量や品質等で契約内容と異なる場合に売主が負う責任です(民法562条以下)。
契約不適合責任を負わないためには、建物や土地の欠陥や不具合箇所を契約内容に含めておく必要があります。
相続したマンションや一戸建てについて、相続人が土地、建物の状態をしっかりと把握できていない場合も少なくありません。
そのため契約不適合責任を負わない、引渡し後にトラブルにならないためにも、物件の状態をできるだけ正確に把握しながら進めることも大切です。
売却を依頼する際、契約不適合責任を含めてしっかりとアドバイスをもらえる不動産会社を選ぶことが大切です。
亡くなった親の家を売る際のよくある質問

亡くなった親の家を売る際によくある質問と回答をまとめています。
相続登記を司法書士に依頼したときの費用や、不動産会社の選び方などが気になる方は、ぜひ参考にしてください。
いつまでも家が売れない場合の対処法は?
いつまでも家が売れない場合の対処法は、次のとおりです。
- 売り出し価格を見直す
- 不動産会社の売却活動をチェックする
- 業者や担当者、媒介契約を変える
- 不動産会社の買取を検討する
周辺の相場と比較して高い場合は、売り出し価格を見直す必要があります。
不動産会社の売却活動を確認して、十分な宣伝をしていなかったり誠意が感じられなかったりする場合は、業者の変更も検討しましょう。
相続登記を司法書士に依頼した場合の費用相場は?
相続登記を司法書士に依頼した場合、一般的に5〜15万円程度の費用がかかります。
不動産や相続人の数、相続関係の複雑さなどの要因によって費用は異なるため、一度見積もりを依頼するとよいでしょう。
可能であれば複数の司法書士事務所に見積もりを依頼して、費用や対応を比較するのをおすすめします。
依頼する不動産会社の選び方は?
亡くなった親の家の売却を依頼する不動産会社は、次のポイントを意識して選んでください。
- 不動産売却の実績が豊富
- 物件のエリアに詳しい
- 査定価格の根拠の説明がある
- 営業担当の対応がよい
信頼できる不動産会社を選べれば、売却までスムーズに進められ、希望する価格で売れる可能性を上げられるでしょう。
まとめ
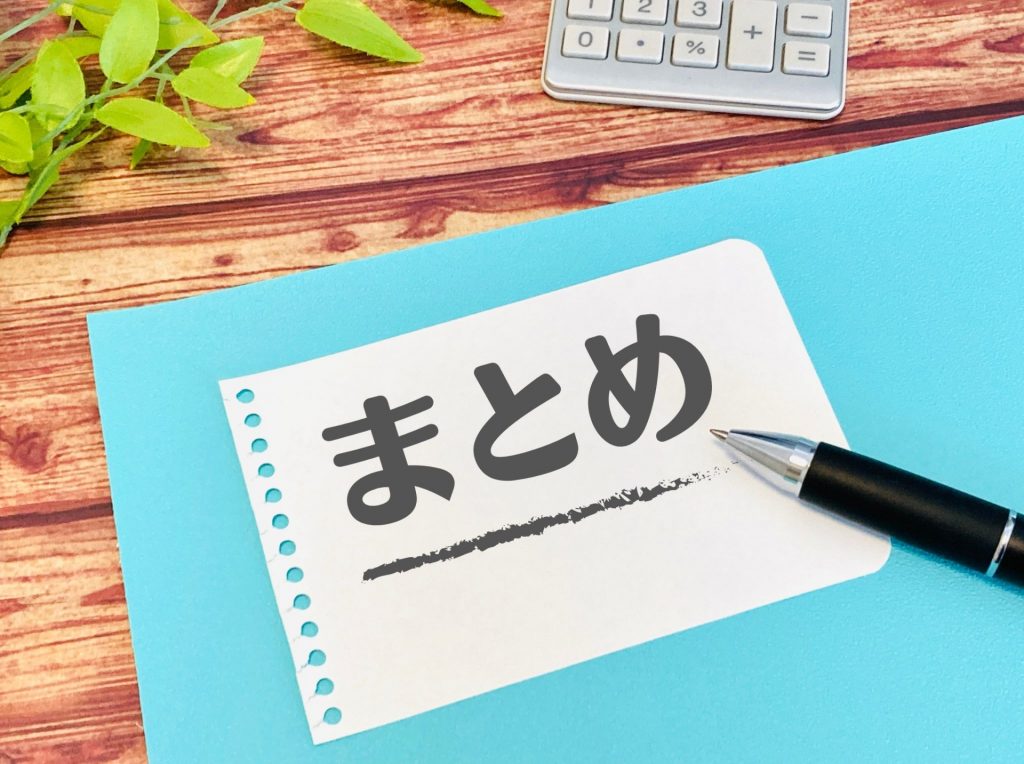
亡くなった親の家を売る方法や流れ、親名義の不動産の売却時に利用できる特例や注意点などを解説しました。
親の家は相続せずに売却できないため、一度不動産の名義を変更してから売る必要があります。
親が亡くなってから家を売るまでの主な流れは、次のとおりです。
- 名義変更(相続登記)
- 不動産会社に査定を依頼する
- 媒介契約を締結し、売却活動開始
- 売買契約締結
- 決済・物件の引渡し
- 確定申告をする
不動産の売却で税金が発生する場合もありますが、基礎控除やさまざまな特例を利用すれば、相続税や譲渡所得税の納税がないケースもあります。
亡くなった親の家を売ろうと考えている方は、本記事で解説した内容を参考に手続きを進め、物件の売却は信頼できる不動産会社に依頼しましょう。













