「売れない土地をどうにかしたい」「維持費ばかりかかって困っている」とお悩みではありませんか?
立地条件や物件状況によっては、通常の売却では買い手が見つからず、長期間放置せざるを得ないケースもあります。
本記事では、売れない土地をスムーズに処分・放棄する具体的な方法から、売れない原因、2025年時点の制度や支援策をわかりやすく解説します。
記事を読むことで、土地の活用・処分に向けた現実的な選択肢が明確になり、固定資産税や管理の負担から解放される可能性が高まるはずです。
不要な土地に悩まされない未来を手に入れる第一歩として、ぜひ本記事を参考にしてください。
売れない土地の特徴

土地がなかなか売れず、手放したくても買い手が見つからない場合、土地そのものに「売れにくい理由」がある可能性が高いです。
ここでは、売却が難航しやすい土地の代表的な特徴を5つ挙げ、対処法のヒントを紹介します。
立地が悪く需要がない
買い手が最も重視するのは「立地」です。たとえば、最寄り駅やバス停まで徒歩30分、周囲に生活施設が何もない山間部などは、需要が極端に低くなります。
さらに、人口減少や高齢化が進んでいる地域では土地を活用しにくく、買い手が見つからない状況に陥りやすいです。
このような土地は、一般的な不動産市場では流通しにくいため、買取業者や寄付など、別の選択肢を検討する必要があります。
土地の条件が悪い
土地そのものの形状や状態が悪いと、住宅用地や商業利用地としての活用が難しくなります。
たとえば、細長い旗竿地や極端な傾斜地などは、建物を建てにくいため買い手が敬遠しがちです。
また、地盤が弱い、雑草が生い茂っている、ゴミが不法投棄されているなど、見た目や安全性に問題がある場合も、売却に大きく影響します。
売却を希望する場合は、草刈りや清掃などの基本的な整備をおこない、土地の魅力を高める工夫が有効です。
希望売却価格が高い
相場よりも明らかに高い価格で売り出している場合、買い手がつかないのは当然です。
相場より高く設定してしまうのは、購入当時の価格や、これまでに支払った固定資産税を基準に考えてしまうことが原因になっている場合があります。
売却を成功させるには、複数の不動産会社に査定を依頼し、現在の市場価格を把握することが欠かせません。
市場価格を基準とした売却戦略に切り替えることで、売れる可能性が高まります。
災害リスクがある
洪水や土砂災害などの危険区域に指定されている土地は、住宅用や事業用としての価値が低くなります。
たとえば、ハザードマップで危険区域に指定されている土地は、住宅ローンの審査が通らないケースもあります。
近年は災害リスクに対する意識が高まっており、安全性が重視される傾向です。
災害リスクの高い土地は、相場より大きく価格を下げても売れにくいため、売却以外の処分方法も視野に入れましょう。
土地の境界があいまい
土地の境界が不明確な状態では、買い手が購入後のトラブルを懸念し、敬遠されることがあります。
境界不明確な土地は、越境や隣地トラブルのリスクが高まるためです。
売却を円滑に進めるには、確定測量を実施し、境界を明確にすることが求められます。
確定測量は一定の費用を伴いますが、円滑な売却に向けた重要な準備といえるでしょう。
売れない土地を手放したい方におすすめの方法

土地の売却が難しい場合でも、処分する方法は複数あります。
ここでは、売れない土地を処分するための具体的な7つの方法を紹介します。
自治体に寄付する
不要な土地は、条件が合えば自治体へ寄付できる場合があります。たとえば、道路整備や公共用地として利用されるケースです。
ただし、すべての自治体が受け入れるわけではありません。形状が管理しやすいか、将来的な用途があるかなど、個別の基準に基づいて判断されます。
寄付を検討する際は、事前に自治体へ相談し、現地調査を受けたうえで判断されるのが一般的です。
相続土地国庫帰属制度を利用する
「相続土地国庫帰属制度」は、2023年4月から始まった制度で、条件を満たせば不要な土地を国に引き渡すことができます。
| 対象者 | 相続や遺贈により土地を取得した個人や共有者 (全員での申請が必要) |
|---|---|
| 申請条件 | ・境界が明確であること ・建物が存在しないこと ・担保権や他人の使用権が設定されていないこと ・土壌汚染がないこと |
| 審査手数料 | 土地一筆につき14,000円 |
| 負担金 | 10年分の土地管理費相当額 |
| 制度適用外の土地 | ・崖地などで管理に過度な費用がかかる土地 ・地上・地下に障害物がある土地 ・隣接地との紛争が予想される土地など |
審査を通過して正式に国庫帰属が認められると、所有権は完全に消滅します。
維持管理が困難な相続土地を手放したい場合、制度の活用を検討するのも一つの方法です。
相続放棄する
相続前であれば「相続放棄」は有効な選択肢です。
土地以外にも借金や不要な不動産がある場合、すべての財産を放棄する形で回避できます。
注意点として、相続放棄は「相続があったことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所で手続きを行う必要があり、一度放棄すると取り消しはできません。
相続人全員で相談し、リスクと費用を十分に把握してから判断しましょう。
知人・友人に譲渡する
売却が難しい土地でも、近隣の知人や親族が有効活用できることもあります。
とくに隣接地を所有している人なら、駐車場や家庭菜園として土地を役立てられるケースも少なくありません。
譲渡には「名義変更」「契約書作成」などの手続きが必要ですが、不動産会社を通さずに済むため、費用負担を抑えられるメリットがあります。
ただし、後々のトラブル防止のため、書面での契約は必ずおこないましょう。
不動産会社・契約内容を変更する
売却が長引いている場合は、不動産会社や契約内容に原因があるかもしれません。
とくに、媒介契約が「一般媒介」になっていると販売活動が消極的になる傾向があります。
売却活動を活性化させるためには、以下のような対応が効果的です。
| 契約形態を変更する | 「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」に変更すると、不動産会社の販売意欲が高まる傾向 |
|---|---|
| 他社へ切り替える | 地元に強い不動産会社に依頼することで、新たな買い手と出会える可能性が高まる |
| 販売戦略を再確認する | 広告内容・価格設定・販売方法などを見直し、改善の余地がないか検討する |
売れない原因を見極めて、柔軟に対応することが土地売却の成功につながります。
マッチングサイトに登録する
不動産マッチングサイトを利用すれば、従来の販売ルートでは接点がなかった買い手層にも情報を届けられます。
たとえば、空き家バンクや土地活用を希望する個人・企業向けのプラットフォームが代表例です。
多くのサイトは掲載料が無料で、成約時のみ手数料が発生するため、金銭的な負担が少なく始めやすいのも特徴です。
| サイト名 | 特徴 | 掲載料 |
|---|---|---|
| SUUMO (スーモ) | ・全国の不動産情報を網羅する大手ポータルサイト ・購入希望者の利用が多く、売却 ・査定・建築相談まで一括対応 ・不動産会社を介した掲載が基本 | 1枠あたり数万円~ ※公式サイトでは料金を明記していないため、詳細は要確認 |
| 家いちば | ・空き家や土地の個人間売買を支援するサイト ・再建築不可や山林など、訳あり物件も掲載可能 ・売主が直接情報を登録でき、売却希望者の相談にも柔軟に対応している | 掲載料:無料 ※成約するまで一切費用はかからない |
| COCOURI (ココウリ) | ・不動産の個人間取引を仲介するマッチングサービス ・売主と買主が直接交渉し、オンライン上で商談を進めることが可能 | 無料キャンペーン実施中 |
| 空き家バンク | ・自治体が運営 ・監修する公的サービス ・地域ごとに掲載条件や対応が異なるが、地元密着で移住者 ・地域活用ニーズとマッチしやすい | 掲載料:無料 ※成約した場合、不動産業者を介する場合は仲介手数料発生の可能性あり |
一般的な売却方法で結果が出ない場合は、新たなチャネルを積極的に活用しましょう。
トラブルを未然に防ぐためにも、司法書士や行政書士など専門家に相談しながら進めるのが安心です。
買取業者に依頼する
一般の売却ルートで行き詰まった場合、不動産買取業者に直接買い取ってもらう方法があります。
市場価格より低めの査定額になることが多いものの、早期に手放せるうえ、手続きも簡略化されているのが特徴です。
とくに、管理が難しい土地や固定資産税の負担が大きい場合には、現実的かつ有効な手段といえます。
仲介を介さないため、契約から現金化までの流れがスムーズなのもメリットです。
売れない土地を手放す相談はファンズ不動産へ
売れない土地を抱えたままにしておくと、固定資産税の負担や雑草管理、近隣への迷惑など、さまざまな問題が積み重なってしまいます。
「もう手放したい」「処分方法がわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。土地が売れない理由は立地や形状、周辺状況などによって異なるため、適切な対処法を知ることが大切です。
状況に合わせた選択肢を把握するためにも、早めに専門家へ相談しておくと安心して進められます。ファンズ不動産では、売れない土地に悩む方の相談に丁寧に寄り添い、無理のない方法で手放せるようサポートできます。
「どうすれば良いのか迷っている」という段階でも、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
1万人超の「買いたい」層へLINEで直接アプローチ
ファンズ不動産の公式LINEには、1万人を超える購買意欲の高いユーザーが登録しています。
従来のポータルサイトで不特定多数の閲覧を「待つ」のとは異なり、関心の高い層へ直接物件情報を「届ける」ことが可能です。
物件の魅力を理解してくれる可能性が高いユーザーへ絞ってアプローチできるため、スピーディーな反響が期待できます。
早期売却を目指す方にとって、この「届ける」力は大きな強みとなるでしょう。
売却査定から引渡しまで、安心のワンストップ対応
ファンズ不動産は、LINEを活用した効率的なプロセスと、幅広い専門知識でスムーズな不動産売却を実現します。
相談は「オンライン面談」から始まり、やり取りもLINEメインでおこなうため、店舗へ足を運ぶ手間も最小限です。
また土地のプロやリノベーションの専門家も在籍しているので、専門知識が必要な相談も窓口一つで完結します。忙しい方でも、スムーズで安心な売却活動が可能です。
日中は仕事で時間が取れない方や、複雑な手続きをまとめて任せたい方でも、ストレスなく売却活動を進められます。
売れない土地を所有し続けるリスク

売れない土地を「いつか使うかもしれない」と放置し続けると、思わぬコストや責任を背負い込むことになりかねません。
所有を続けるだけでも、固定資産税や管理費用が発生し、将来的なトラブルの原因にもなります。
ここでは、実際に起こり得る主なリスクを4つに分けて解説します。
固定資産税の支払いが必要になる
売却できない土地でも、所有している間は必ず固定資産税がかかります。
たとえば、市街地から離れた山林や農地でも、評価額がゼロでない限り課税対象です。
年に1万~5万円程度の固定資産税でも、10年間所有していた場合は10万〜50万円、20年間では最大で100万円近くの支払いが必要になる可能性があります。
(※固定資産税課税台帳に登録されている価格×税率1.4%=固定資産税、※実際の税額は、課税標準額や各種軽減措置によって異なります)
利用も収益も見込めない土地に対し、税金だけが発生し続けるのは明らかなマイナスです。
税負担を減らしたい場合は、早めに手放すか、税制優遇の対象になるような活用を検討するのが現実的です。
維持・管理の責任を問われる
雑草が伸び放題になっていたり、不法投棄があったりすると、たとえ誰も使っていない土地でも所有者が責任を問われます。
実際に、近隣住民からの苦情で行政から管理指導が入るケースもあります。
とくに住宅街の近くにある土地では、景観や衛生への影響も無視できません。
放置状態が続けば「管理不全土地」として扱われ、罰則や法的通知を受ける可能性もあります。
不要なトラブルを避けるためにも、売却または最低限の管理を行うことが重要です。
不動産価値が下がる場合がある
土地の価値は、将来的に下がるリスクがあります。
とくに過疎地域では、人口減少と需要の低下によって地価が早く下がる傾向です。
また、過去に地滑りや水害などの被害があったエリアはハザードマップの影響で買い手に敬遠されやすいため、不利な売却条件になる場合があります。
少しでも高く売れるタイミングを逃さないよう、早い段階で処分や活用を検討しましょう。
損害賠償請求される可能性がある
管理されていない土地が原因で第三者に被害が生じた場合、土地の所有者が責任を問われる可能性があります。
たとえば、老朽化したブロック塀が倒れて通行人にケガを負わせてしまうと、損害賠償を請求される恐れがあります。
また、境界不明な土地が原因で隣地とのトラブルになり、裁判に発展する事例もあります。
土地を所有している限り、法的な責任からは逃れられません。
万が一のトラブルに備えるためにも、早めに売却や放棄といった選択肢を視野に入れておく必要があります。
売れない土地を売却・活用するために検討すべきこと

「どうせ売れない」と決めつけてしまう前に、土地の状態や活用方法を見直してみましょう。
思いがけない売却のチャンスが見えてくることもあります。
ここで紹介する対策は、実際に売却が成立した事例をもとにしています。
諦める前に、できる工夫を一つずつ検討してみましょう。
更地にする
建物が古くなっている場合、建物自体が土地の売却を妨げている可能性があります。
とくに老朽化した空き家は「解体にコストがかかる」「倒壊リスクがある」といった理由で、敬遠されやすい傾向です。
建物の価値が低い場合は、思い切って更地にすると購入希望者が増える可能性があります。
たとえば、駐車場や資材置き場として活用される例もあるため、建物付きよりもシンプルな土地の方がニーズがあることもあります。
ただし、解体費用や税制変更の影響もあるため、事前に収支をシミュレーションしておきましょう。
土地の状態を改善する
水はけの悪さや道路への接道がないといった物理的な欠点は、少しの工夫で改善できる場合があります。
たとえば、「再建築不可」の原因となっている接道条件をクリアすれば、住宅用地としての価値が高まり、買い手が見つかりやすくなる傾向です。
災害リスクのある土地は、土砂崩れ対策や排水設備の整備など、災害対策をおこなうことで売却のハードルを下げられます。
また、測量図や地目の確認書類、登記情報などをそろえておくことも重要です。
必要な情報が明確に提示されていれば、購入希望者の安心感につながり、売却交渉がスムーズに進む可能性が高くなります。
収益化する
売却が難しい土地でも、うまく活用すれば継続的な収益を生む「資産」として機能させることが可能です。
たとえば、月極駐車場やトランクルーム、貸し農園、太陽光発電設備の設置など、立地や広さに応じた活用法があります。
とくに地方の広い土地では、初期費用を抑えた副収入源として活用されている事例も少なくありません。
一定の収益が見込める状態にすれば、「収益物件」として買い手がつく可能性も高まり、将来的な売却にもつながります。
「売れない土地」を「活かす土地」へと転換する視点が、資産価値を見直すきっかけになります。
売れない土地を手放したいときによくある質問
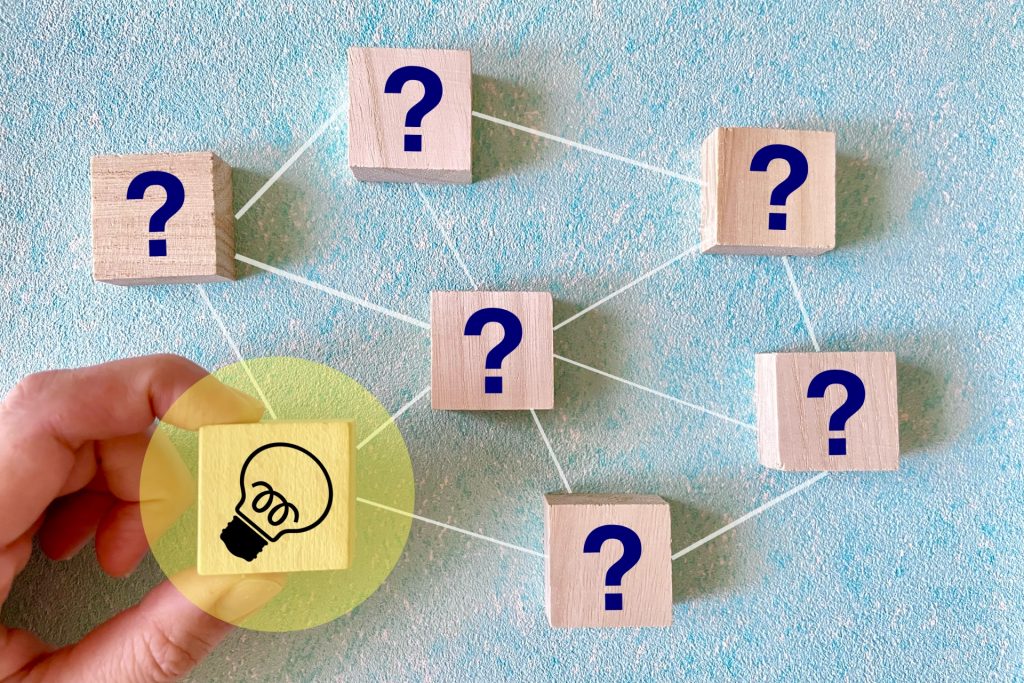
売れない土地を手放す際は、多くの方が同じような疑問を抱きます。
ここでは、特に多い質問について具体的に解説します。
土地の売却にかかる期間の平均は?
一般的な土地の売却期間は3ヶ月〜半年程度が目安です。
ただし、立地条件が悪い土地や需要の少ないエリアでは、1年以上買い手が見つからないケースも珍しくありません。
とくに、地方の過疎地域や交通の便が悪い土地は反響が少なく、長期間掲載しても問い合わせすら入らないこともあります。
早期の売却を目指す際は、不動産買取業者への相談や、販売時期・広告戦略の見直しも有効です。
信頼できる仲介業者と連携しながら、状況に応じた対策を講じていきましょう。
自治体への寄付は必ず引き取ってもらえる?
残念ながら、自治体への土地の寄付は必ずしも受け入れてもらえるとは限りません。
自治体側は管理責任や費用負担を伴うため、引き取りに非常に消極的です。
実際には、「活用の予定がない」「維持費が負担になる」といった理由で断られることが多く、寄付を受け入れてくれる自治体はごく一部に限られます。
寄付を検討する際は、まず担当部署に連絡して、引き取りの可否や必要な手続き・条件を確認しておきましょう。
土地が売れた場合は税金がかかる?
土地を売って利益が出た場合、「譲渡所得税」が課税されます。
ただし、取得時の価格や登記・仲介にかかった諸費用は差し引けるため、実際に課税される金額は下がる可能性があります。
長期保有(5年以上)か短期保有(5年以下)かによって税率が変わる点にも注意してください。
また、赤字で売却しても確定申告が必要なケースがあります。
相続した土地では取得費の把握が難しいことも多いため、税金まわりで迷う場合は、早めに税理士や不動産会社に相談しましょう。
まとめ

売れない土地をそのままにしておくと、固定資産税や管理費用といった出費だけがかかり続け、将来的にはトラブルや損害賠償のリスクにもつながります。
まずは「なぜ売れないのか」を明確にし、状態改善や更地化、不動産会社への買取相談といった対策を検討しましょう。
あわせて、相続土地国庫帰属制度や自治体への寄付といった選択肢も活用すれば、処分方法の幅が広がります。
重要なのは、現状と制度を正しく理解し、自分の状況に合った方法で早めに行動を起こすことです。
負担を最小限に抑えながら、将来的な不安のないかたちで土地を手放していきましょう。













