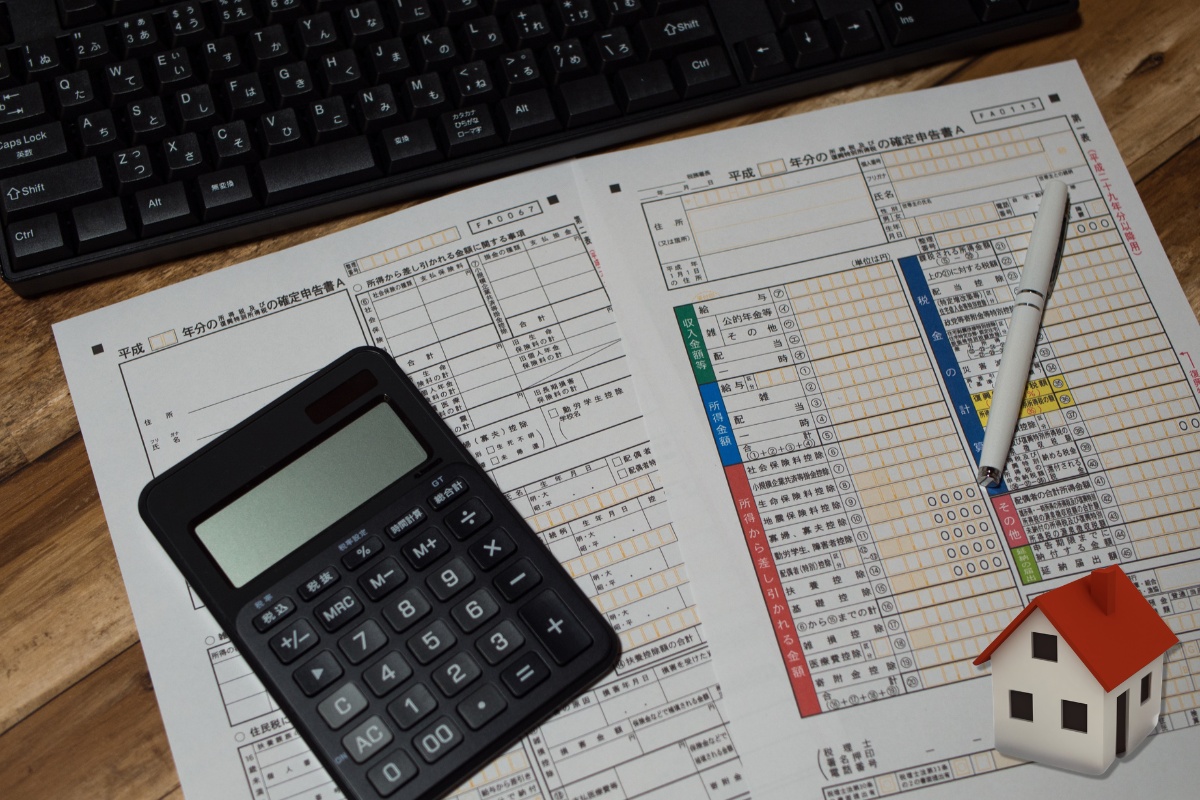「土地を売却したときには確定申告しなければいけないの?」と、土地を売却した後に確定申告が必要なのかどうか悩む方もいるでしょう。
譲渡所得が発生した場合か特例を利用する場合、土地を売却した後に確定申告が必要です。
確定申告が必要であるにもかかわらず、申告しないと重加算税や延滞税が課される場合もあります。
余計な出費を防ぐためにも、土地売却を検討する際には確定申告について事前に確認しましょう。
本記事では土地売却の際に確定申告が必要なケースや申告に必要な書類、申告の流れについて解説します。
土地を売却する際に確定申告は必要?不要?
一定の条件を満たした場合、土地を売却する際に確定申告が必要です。
つまり、確定申告が不要なケースもあります。
まずは確定申告が必要なケースと、そうでないケースについて解説します。
確定申告が必要なケース
土地を売却した際に確定申告が必要なケースは、次のとおりです。
- 譲渡所得が発生する場合
- 税金控除を適用する場合
それでは、確定申告が必要なケースについて解説します。
譲渡所得が発生する場合
土地を売却して譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要です。
譲渡所得とは、不動産や株式などの資産を売却した際に得た所得です。
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、特例を利用しない限り所得税や復興特別所得税、住民税が課税されます。
譲渡所得税の納税額を申告するために確定申告が必要です。
なお、確定申告は土地を売却した年の翌年2月16日から3月15日までにおこなわなければなりません。
期限を1日でも過ぎると、延滞税が課されるため注意しましょう。
特例を適用する場合
譲渡所得税に関する特例を利用する際は、確定申告が必要です。
譲渡所得税には、マイホームを売ったときの特例やマイホームを売ったときの軽減税率の特例、相続した空き家を売ったときの特例などの特例があります。
特例を利用すれば、譲渡所得が控除されたり税率が下がったりします。
確定申告は各種特例を利用するための条件となっており、申告しないと特例を受けられません。
特例を利用した結果、譲渡所得がゼロになったとしても確定申告が必要です。
確定申告が不要なケース
確定申告が不要なケースは譲渡所得が発生せず、かつ特例を利用しない場合です。
確定申告が不要な場合は、申告も書類の作成も必要ありません。
なお、確定申告が不要かどうかは、譲渡所得が発生するかどうかを計算して判断する必要があります。
計算方法を理解すれば自身でも算出できますが、不安な場合は税理士に計算してもらい確定申告も代行してもらいましょう。
確定申告を税理士に代行してもらうと費用がかかるため、事前に代行費用の見積もりを取得することが大切です。
土地売却後に確定申告しないとどうなる?
確定申告が必要な条件を満たしているにもかかわらず、申告しないと次のような問題が発生します。
- 国税庁から連絡がある
- 税務調査がおこなわれる
それでは、土地売却後に確定申告しないときに起こる問題について解説します。
国税庁から連絡がある
確定申告が必要であるにもかかわらず申告しないと、税務署から問い合わせの連絡が来る場合もあります。
土地を売却すると、所有権移転登記したことが情報として法務局に記録されます。
法務局と税務署は情報を共有しており、土地を売却した事実が税務署に伝わるため、売買した事実は隠せません。
土地を売却した方には、税務署から売買内容の確認書類が必ず届きます。
対象となる方が確定申告をしていない場合、税務署から申告が必要ないのか確認する問い合わせが届くため注意が必要です。
税務調査がおこなわれる
税務署からのお尋ねに回答しないと、税務調査がおこなわれる場合もあります。
税務調査の結果、譲渡所得税の納税が必要と判断されると罰則の対象となります。
譲渡所得が発生したにもかかわらず、確定申告しなかった場合は次のような罰則として課されるため注意しましょう。
- 無申告加算税や延滞税、重加算税の課税
- 懲役もしくは罰金、またはその両方
非常に重い罰則が科されるため、譲渡所得が発生した場合は必ず確定申告をおこないましょう。
土地売却後の確定申告に必要な書類
土地売却後の確定申告に必要な書類は、次のとおりです。
- 確定申告書
- 売買契約書
- 譲渡所得の内訳書
- 登記事項証明書
- 取得費や譲渡費用がわかる領収書
- 本人確認書類や源泉徴収票
それでは、各書類について解説します。
確定申告書
土地売却後に確定申告する際は、税務署に確定申告書を提出します。
確定申告書には第一表と第二表があり、こちらには所得金額や控除額などを記載し、確定申告をおこなう方全員が提出します。
また、土地を売却した際は、分離課税用の確定申告書第三表も追加で提出しなければなりません。
譲渡所得税は他の所得と分けて計算し納税するため、第三表も提出する必要があります。
申告年度ごとに書類の内容が変更される場合もあるため、最新年度の書類であることを確認してから利用しましょう。
売買契約書
土地売却後の確定申告では、2通の売買契約書の写しを提出します。
提出する売買契約書の写しは、次のとおりです。
- 売却した不動産を購入したときの売買契約書の写し
- 売却時の売買契約書の写し
売買契約書を提出する理由は、取得費と譲渡費用を確認するためです。
なお、購入時の売買契約書を紛失した場合は、売却時の契約書の写しのみでも申告が可能です。
譲渡所得の内訳書
譲渡所得の内訳書は、譲渡所得の計算に利用する書類です。
譲渡所得の内訳書で計算した金額は、確定申告書第三表に転記します。
記入ミスを防ぐため、国税庁の公式サイトに掲載されている記入例を参考にしましょう。
なお、譲渡所得の内訳書は国税庁の公式サイトからダウンロードできます。
登記事項証明書
確定申告では、売却した土地の登記事項証明書を添付します。
登記事項証明書とは、不動産や所有者の情報が記載された書類です。
登記事項証明書は、法務局にて1通600円で取得できます。
売却した土地に地番が3つある場合、登記事項証明書は3通必要となり、合計で1,800円の費用がかかります。
参照元:法務省 登記手数料について
取得費や譲渡費用がわかる領収書
確定申告の際には、取得費や譲渡費用がわかる領収書を添付します。
【取得費となる費用例】
- 仲介手数料
- 不動産取得税や印紙税、登録免許税
- 司法書士の報酬
- 土地の造成にかかった費用
- 古家の解体費用 など
【譲渡費用となる費用例】
- 仲介手数料
- 印紙税や登録免許税
- 司法書士の報酬 など
領収書や納税証明書を紛失した場合、紛失した分の取得費や譲渡費用は計上できません。
本人確認書類・源泉徴収票
確定申告には本人確認書類が必要であり、不動産を売却した方が給与所得者の場合は最新の源泉徴収票を添付します。
本人確認書類として利用できるものは、次のとおりです。
- マイナンバーカード
- 住民票の写し(番号付きのもの)
- 運転免許証
- パスポート
なお、有効期限がある書類は期限内のもののみ利用できます。
利用の際は有効期限が切れていないか、事前に確認しましょう。
自分でできる!土地売却後の確定申告の流れと書き方
土地売却後の確定申告は、次の流れで進めます。
- 譲渡所得の内訳書を記入する
- 確定申告書を記入する
- 税務署に書類を提出する
- 申告期間中に納税する
確定申告は手続きの流れを理解すれば、専門的な知識がなくても自身で進められます。
1:譲渡所得の内訳書を記入する
確定申告の手続きを開始する際は、まず譲渡所得の内訳書の内容を記入しましょう。
確定申告書には譲渡所得の計算結果を記載する必要があるため、先に内訳書を記入しておくとスムーズに書類を作成できます。
譲渡所得の内訳書は1〜4面で構成されており、次の内容を記載します。
- 申請者の氏名や住所
- 売却した土地の概要
- 取得費と譲渡費用の金額
- 交換・買換え資産の情報(買換え特例を利用する場合のみ)
- 譲渡所得税の計算
なお、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受ける際は、別途、譲渡所得の内訳書の5面を入手して記載します。
参照元:国税庁 譲渡所得の内訳書
2:確定申告書を記入する
譲渡所得の内訳書の記載が終わったら、確定申告書の記入を始めます。
譲渡所得の内訳書に記載した内容のなかには、確定申告書に転記できる項目が含まれます。
まずは確定申告書第三表へ転記しましょう。
確定申告書第三表の内容を記載した後、次にその内容を第一表と第二表に転記します。
その他、給与所得額や保険料控除額などの記載事項は、源泉徴収票や給与明細などを利用しながら記入しましょう。
参照元:国税庁 確定申告書第一表、第二表
参照元:国税庁 確定申告書第三表
3:税務署に書類を提出する
譲渡所得の内訳書と確定申告書の記入がすべて終わったら、確定申告の期限内に添付書類とともに税務署へ提出します。
提出先は住まいの住所を管轄している税務署です。
確定申告の提出方法は4つあり、いずれの方法でも受け付けてもらえます。
- e-Taxやアプリで電子申告する
- 税務署の窓口に持参する
- 税務署に郵送する
- 税務署の時間外収集箱へ投函する
なお、確定申告を郵送する場合、郵送物の消印の日が確定申告期日内であれば到着が遅れても通常通り受理されます。
4:申告期間中に納税する
譲渡所得税の納税が必要な場合、確定申告の期限内に納税しなければなりません。
納税方法は次のとおりです。
- 税務署や金融機関に現金を持参する
- 振替えサービスを利用する
- クレジットカードで支払う
なお、譲渡所得が発生すると住民税も課税されます。
住民税については、確定申告をした年の6月頃に自治体から納税通知書が郵送されます。
給与所得がある方は、与所得分の住民税に加え、譲渡所得による住民税が上乗せされるため注意が必要です。
土地売却後の確定申告で適用できる特例
土地売却後の確定申告の際は、一定の条件を満たすと次のような特例を利用できます。
- マイホームを売ったときの特例
- マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 相続した空き家を売ったときの特例
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- 譲渡損失がある場合に利用できる特例
それでは、各特例の内容について解説します。
各種特例の適用を受けるためには、一定の条件を満たさなければなりません。
条件は複雑で多岐にわたるため、適用されるかどうかは不動産会社や税理士に確認ください。
なお、条件については、各特例の解説で国税庁の公式サイトの該当ページを掲載します。
条件が気になる方は、こちらをチェックしてください。
マイホームを売ったときの特例
マイホームを売ったときの特例とは、自宅を売却した際に譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
特例の適用を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
- 現在住んでいる自宅の売却
- 転居日から3年経過した日の属する年の年末までの売却
- 解体日から1年以内の売買契約
- 夫婦や親戚への売却 など
なお、マイホームを売ったときの特例は、次に紹介する軽減税率の特例との併用が可能です。
譲渡所得税を大幅に軽減できるため、マイホームを売ったときの特例と軽減税率の特例が併用できるかどうかを事前に確認しましょう。
特例の内容や詳しい要件を知りたい方は「マイホームを売ったときの特例」のページを参考にしてください。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
マイホームを売ったときの軽減税率の特例とは、自宅を売却した際に譲渡所得税の税率を下げられる特例です。
特例の適用を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
- 現在住んでいる自宅の売却
- 自宅が売却した年の1月1日現在で所有期間10年以上
- 過去3年間に軽減税率の特例を利用していない
- 特別な関係以外の方への売却 など
マイホームを売ったときの軽減税率の特例を利用すれば、長期譲渡所得よりも税率が下がるため節税が可能です。
なお、税率が下がるのは譲渡所得6,000万円以下までであり、6,000万円を超える部分には長期譲渡所得の税率が適用されます。
特例の内容や詳しい要件を知りたい方は「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」のページを参考にしてください。
相続した空き家を売ったときの特例
相続した空き家を売ったときの特例とは、相続した空き家を売却する際に譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
特例の適用を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
- 亡くなった方がひとりで住んでいた家
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物
- 区分所有権の不動産ではない
- 一定の耐震基準を満たしている建物
相続した空き家を売ったときの特例には期限があり、2027年12月31日までに物件を引渡ししなければなりません。
また、相続が発生したのを知った日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。
特例の内容や詳しい要件を知りたい方は「相続した空き家を売ったときの特例」のページを参考にしてください。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは、相続財産を売却した際に一定条件を満たすと相続税の一部を取得費として計上できる特例です。
特例の適用を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
- 相続や遺贈で財産を取得した方
- 財産を取得した人に相続税が課税されている
- 相続開始から3年10か月以内の売却
本来、譲渡所得を計算する際に相続税は取得費に加算できませんが、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を利用すると、納税した相続税の一部を取得費として計上できます。
納税額が多いほど譲渡所得税の軽減効果が高くなるため、多額の相続税を納めた方は特例の適用を受けられるかどうかを確認しましょう。
特例の内容や詳しい要件を知りたい方は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」のページを参考にしてください。
特定のマイホームを買い換えたときの特例
特定のマイホームを買い換えたときの特例とは、自宅を買い換えた際に一定条件を満たすと譲渡所得税の繰り延べが受けられる特例です。
特例の適用を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
- 現在住んでいる自宅の売却
- 所得の合計が3,000万円以下
- 新居購入で返済期間10年以上のローンを受けること など
通常、譲渡所得税は不動産を売却した年の翌年に課税されます。
しかし、買い換えの特例の適用を受けると、自宅の売却時に課税される譲渡所得税が買い換えた自宅を売却するときまで繰り延べされます。
自宅を売却する際に、譲渡所得税を納税する資金的な余裕がない方におすすめの特例です。
特例の内容や詳しい要件を知りたい方は「特定のマイホームを買い換えたときの特例」のページを参考にしてください。
譲渡損失がある場合に利用できる特例
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例とは、自宅を買い換えた際に一定条件を満たすと譲渡損失を損益通算できる特例です。
特例の適用を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
- 現在住んでいる自宅の売却
- 売却代金が1億円以下
- 特別な関係以外の方への売却
- 売却した年から3年以内の新居購入 など
不動産を売却して譲渡損失が出た場合、通常は他の所得と損益通算できません。
しかし、本特例の適用を受ければ、給与所得や不動産所得から譲渡損失を差し引けます。
また、他の所得から1回で譲渡損失を差し引きできなかった場合、譲渡の年の翌年以後3年まで繰越控除が受けられます。
特例の内容や詳しい要件を知りたい方は「国税庁」のページを参考にしてください。
土地売却にかかる税金の計算方法
自身で確定申告する際には、譲渡所得税を計算しなければなりません。
譲渡所得税を計算する場合は、次の手順で算出します。
譲渡所得を求める
譲渡所得税を計算する際は、まず譲渡所得を求めます。
譲渡所得の計算方法は、次のとおりです。
| 譲渡所得 = 収入金額 -(取得費 + 譲渡費用) |
各用語の意味は、次のとおりです。
| 収入金額 | 土地の売却金額 |
| 取得費 | 売却する土地を購入したときの購入代金と諸費用 |
| 譲渡費用 | 土地を売却した際に支払った諸費用 |
ただし、すべての諸費用が計上できるわけではありません。
計上できる費用かどうか不安な場合は、不動産会社か税理士に確認しましょう。
なお、取得費が不明である場合、次の計算式で求めた金額を概算取得費として計上できます。
| 概算取得費 = 収入金額 × 5% |
取得費を計上しないと譲渡所得税が増えてしまうため、必ず概算取得費を計上して確定申告しましょう。
特別控除を適用する
譲渡所得を計算した後、適用される特別控除の額を差し引いて課税譲渡所得を算出します。
| 課税譲渡所得 = 譲渡所得 – 特別控除 |
特別控除で差し引ける控除額の例は、次のとおりです。
| 特例の名称 | 控除額 |
| 収用等により土地建物を譲渡した場合 | 5,000万円 |
| マイホームを譲渡した場合 | 3,000万円 |
| 被相続人の空き家を譲渡した場合 | 3,000万円または2,000万円 |
| 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 | 1,500万円 |
| 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 | 800万円 |
参照元:国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
特別控除の適用を受ければ譲渡所得を軽減でき、譲渡所得税の節税につながります。
確定申告する前には、特別控除を利用できるかどうか不動産会社や税理士に確認しましょう。
譲渡所得税額を算出する
課税譲渡所得を算出した後、税率を乗じて譲渡所得税額を求めます。
| 譲渡所得税 = 課税譲渡所得 × 税率 |
譲渡所得税の税率は、次のとおりです。
| 不動産の所有期間 | 税率 |
| 5年以下 | 39.63% |
| 5年超〜10年以下 | 20.315% |
| 10年超 | 14.21%(6,000万円超の部分は20.315%) |
上記のとおり不動産の所有期間によって税率が異なるため、どのくらい土地を所有していたかを確認する必要があります。
売却した年の1月1日時点での所有期間になるため、当てはまる税率をかけて譲渡所得税を算出しましょう。
土地売却にかかる税金をシミュレーション
ここからは、土地売却時に課税される譲渡所得税の課税額をシミュレーションします。
シミュレーションの条件例は、次のとおりです。
| 収入金額 | 8,000万円 |
| 取得費 | 3,000万円 |
| 譲渡費用 | 500万円 |
| 所有年数 | 7年(長期譲渡所得) |
それでは、実際にシミュレーションしてみましょう。
特別控除を適用しない場合
【譲渡所得】
| 8,000万円 -(3,000万円 + 500万円)= 4,500万円(譲渡所得) |
【課税譲渡所得】
| 4,500万円 – 0円 = 4,500万円(課税譲渡所得) |
【譲渡所得税】
| 4,500万円 × 20.315% = 914万1,750円(所得税、復興特別所得税、住民税の合計) |
特別控除を考慮せずにシミュレーションすると、土地売却によって約914万円の納税が必要となることがわかります。
なお、約914万円のうち、所得税は675万円です。
3,000万円特別控除を適用する場合
続いて、3,000万円の特別控除が適用された場合の計算をおこないます。
【譲渡所得】
| 8,000万円 -(3,000万円 + 500万円)= 4,500万円(譲渡所得) |
【課税譲渡所得】
| 4,500万円 – 3,000万円 = 1,500万円(課税譲渡所得) |
【譲渡所得税】
| 1,500万円 × 20.315% = 304万7,250円(所得税、復興特別所得税、住民税の合計) |
3,000万円の特別控除を適用すると、合計で約304万円の納税が必要となります。
控除しない場合と比べ、納税額が610万円も減少しています。
特例を利用すれば大幅な減税が可能となるため、適用できる特例がないか確認しましょう。
土地売却時の確定申告に関するよくある質問
土地売却時の確定申告に関するよくある質問は、次のとおりです。
- 税理士に依頼した場合の費用相場は?
- 無申告は絶対にバレる?
- 相続した土地は早めに売るべき?
それでは、よくある質問と回答を紹介します。
税理士に依頼した場合の費用相場は?
土地売却後の確定申告を税理士に依頼した場合、10〜30万円程度の費用がかかります。
費用相場の幅が広い理由は、次のとおりです。
- 土地の売却金額の高さによって変動する
- 特例の適用の有無によって費用が変わる
税理士の代行費用は依頼先によっても異なるため、見積もりを取ったうえで決定しましょう。
無申告は絶対にバレる?
土地売却後の無申告は、絶対に税務署にバレます。
土地を売却する際は、売主から買主に所有権移転登記をしなければなりません。
所有権移転登記した情報は、法務局から税務署に伝わります。
無申告は必ずバレると考え、譲渡所得が発生した場合は必ず確定申告しましょう。
相続した土地は早めに売るべき?
まとまった資金が必要な場合や今後使う予定がない場合は、早めの売却を検討しましょう。
相続した土地を売却する場合、相続した空き家を売ったときの特例や、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の適用を受けられる可能性があります。
いずれの特例も適用を受ければ譲渡所得税の節税につながりますが、相続の発生から一定期間内しか利用できません。
手元に多くの金銭を残したい場合は、早めに行動して土地を売却しましょう。
まとめ
土地を売却して譲渡所得が発生したとき、もしくは特例を利用するときには確定申告しなければなりません。
確定申告が必要であるにもかかわらず、申告しないと罰則の対象となるため注意が必要です。
まずは土地売却後に確定申告が必要な条件を把握して、自身が申告の対象に該当するかどうか確認しましょう。
また、土地売却後の確定申告は税金の知識があまりない方でも、計算方法や手続きの流れを理解すれば自身で申告できます。
税理士に確定申告を依頼すると費用がかかるため、出費を抑えたい方は自身で申告してみましょう。