「固定資産税がかからない土地ってあるの?」
「固定資産税が課されない土地を相続するときの注意点って何があるの?」
固定資産税が課されない土地は例外的なケースであり、どのようなケースで課税されないのか、どのように引継ぐべきなのか、と不安に感じる方もいるでしょう。
また、例外的なケースであるため、相続や売却の際の注意点について知りたい方も多いでしょう。
本記事では、固定資産税がかからない土地や相続するときの注意点について詳しく解説します。
固定資産税がかからない土地は4種類ある

固定資産税がかからない土地は、次の4種類です。
- 固定資産税評価額が30万円以下の土地
- 国・地方自治体が所有する土地
- 地方税法で定められた土地
- 公共の道路と同じように利用されている土地
それでは、固定資産税がかからない土地について解説します。
固定資産税評価額が30万円未満の土地
土地の固定資産税評価額が30万円未満の場合、固定資産税は課税されません。
課税が免除される金額となる基準を免税点と呼びます。
| 土地の免税点 | 30万円未満 |
|---|---|
| 建物の免税点 | 20万円未満 |
免税点を超えたかどうかの判断基準は、納税義務者の所有不動産の評価額合計で決まります。
なお、同一の自治体が管轄する地域のなかで、複数の土地を所有している場合は免税点を超えやすくなる点には注意が必要です。
評価額20万円の土地Aと15万円の土地Bを所有している場合、合計評価額は35万円となり、免税点を超えるため固定資産税が課税されます。
参照元:総務省 固定資産税の概要
国・地方自治体が所有する土地
国や地方自治体が所有する土地には、固定資産税は課されません。
固定資産税を課す権限を持つのは、国や地方自治体です。
課税権を持つ組織が自ら税金を納めるのは、矛盾が生じるためです。
納税に矛盾が生じる組織に対して課税しないことを、人的非課税と呼びます。
公立の病院や学校、市町村役場などには人的非課税が適用され、固定資産税は課されていません。
地方税法で定められた土地
地方税法には、固定資産税を課さないと定められている土地が明記されています。
固定資産税が課されない土地の主な例は、次のとおりです。
- 国立公園や国定公園にある特別保護区
- 重要文化財に指定された建物およびその敷地
- 保安林がある土地
- 墓地 など
用途に応じて税金を課さないことを、用途非課税と呼びます。
なお、用途非課税の適用を受けるためには、自治体に非課税申告書を提出して審査に通る必要があります。
参照元:e-Gov 地方税法
公共の道路と同じように利用されている土地
公共の道路と同様に利用されている土地は用途非課税の対象となり、固定資産税は課されません。
道路と同じように利用されている土地の主な例は、次のとおりです。
| 私道 | ・個人や法人が所有している道路 ・不特定多数の方が利用できる私道は非課税 |
|---|---|
| 位置指定道路 | ・建築基準法上の道路として認定を受けた私道 ・幅1.8m以上あり私物を置いていない場合は非課税 |
表のとおり、公共の道路のように利用されている私道や位置指定道路は、一定の条件を満たさなければ非課税にはなりません。
参照元:e-Gov 地方税法
固定資産税がかからない土地を相続するときの流れ

固定資産税がかからない土地を相続する場合は、次の流れで手続きを進めます。
- 相続する土地を確認する
- 必要書類を取得する
- 遺産分割協議をおこなう
- 申請に必要な書類を作成する
- 登記申請する
なお、相続に関する手続きには法律の知識が必要なため、一般的に司法書士に依頼します。
自身での手続きが難しいと感じる方は、司法書士に依頼しましょう。
1:相続する土地を確認する
固定資産税がかからない土地を相続する際は、まず被相続人の所有している不動産を確認します。
被相続人とは、相続財産を遺して亡くなった方です。
固定資産税がかからない土地には固定資産税納税通知書が送付されないため、自治体で名寄帳を調査し、不動産の有無を確認しなければなりません。
名寄帳とは、所有者別に所有している不動産をまとめた管理台帳です。
自治体の窓口で名寄帳を確認し、相続する土地があるかどうかを調査します。
2:必要書類を取得する
相続する土地がある場合は、相続登記のために次の書類を用意します。
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 戸籍の謄本 | ・被相続人の出生から死亡までの戸籍 ・相続人の戸籍 ・被相続人の本籍地の自治体で取得 ・相続人の本籍地の自治体で取得 |
| 住民票 | ・被相続人の出生から死亡までの住民票 ・相続人の住民票 ・被相続人の住まいがある自治体で取得 ・相続人の住まいがある自治体で取得 |
| 印鑑証明書 | ・相続人全員分が必要 ・相続人の住まいがある自治体で取得 |
| 固定資産評価証明書 | ・相続する土地の評価額が確認できる書類 ・土地所在地の市区町村役場で取得する書類 |
| 遺言書 | ・遺言書が残されている場合のみ ・自宅や公証人役場に保管されている |
相続登記を申請するためには、さまざまな書類を準備する必要があります。
必要書類に不備があると登記ができないため、事前に司法書士や弁護士に相談してから準備しましょう。
3:遺産分割協議をおこなう
遺言書がない場合は書類の準備後に、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方について協議することです。
協議をおこない、全員が遺産の分け方に承諾したら、遺産分割協議書を作成して全員が実印で押印します。
なお、全員の承諾が得られれば、遺言書の内容とは違う分配方法にしたり、法定相続と違う配分で相続しても構いません。
固定資産税がかからない土地を、特定の相続人に相続させることも可能です。
4:申請に必要な書類を作成する
遺産分割協議書を作成した後は、次の書類を作成します。
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 登記申請書 | 相続登記の申請に必要な書類 「法務省公式サイト」でダウンロード可 |
| 相続関係説明図 | 被相続人と相続人の関係を示す図面 一般的に司法書士や弁護士が作成する |
相続関係説明図は家系図に似た書類で、被相続人と相続人の関係をわかりやすくするための書類です。
法務省公式サイト「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」を参考にすれば、個人でも作成できます。
5:登記申請する
必要な書類が揃ったら、法務局に相続登記を申請します。
申請の方法は、次の3つです。
- 窓口に書類を持参
- 郵送で書類を送付
- オンラインで申請
なお、相続登記は義務化されており、相続の開始を知った日から3年以内に登記しなければなりません。
期間内に相続登記をおこなわない場合、10万円以下の過料が科されるため注意しましょう。
固定資産税がかからない土地でも相続税はかかる

相続税は相続財産の総額で計算するため、固定資産税がかからない土地とあわせて高額な遺産を相続した場合には相続税が課されます。
ただし、相続税には基礎控除があり、控除額以内の遺産を相続する場合は課税されません。
ここからは、相続税の基礎控除や固定資産税がかからない土地の評価額の計算方法について解説します。
基礎控除内の場合は申告不要
相続税には基礎控除が設けられており、相続財産の価値が次の計算式の金額以内なら相続税は課されません。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、配偶者と子の2人が相続する場合、基礎控除額は次のようになります。
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円(基礎控除額)
相続財産の価値が4,200万円までであれば相続税は課されません。
基礎控除以内の相続であれば、確定申告は不要です。
相続税評価の方法は2種類ある
固定資産税がかからない土地を相続する場合は、次のいずれかの方式で相続税評価額を算出します。
- 路線価方式
- 倍率方式
それでは、それぞれの計算方法について解説します。
路線価方式
路線価方式とは国税庁の定めた1㎡あたりの価格である路線価を用い、土地の評価額を計算する方法です。
路線価方式の土地評価額 = 路線価 × 面積(㎡)
路線価は国税庁公式サイト「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で確認できます。
財産評価基準書路線価図・評価倍率表には、路線価の調べ方や図面の説明も記載されているため、参考にして該当の路線価を確認してください。
なお、計算式は簡易的なものであり、正確な評価額を計算する際は、土地に対してさまざまな補正をかける必要がある点には注意が必要です。
倍率方式
倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて土地の評価額を算出する方法です。
倍率方式の土地評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
倍率は各地域ごとに異なり、同じ地域でも土地の地目によって異なる数値が適用されます。
路線価と同じく、倍率も国税庁公式サイト「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で確認できます。
正確な評価額を算出するためには補正が必要な場合もあり、倍率地域の土地についても税理士に確認することが大切です。
固定資産税がかからない土地を相続する際の注意点

固定資産税がかからない土地を相続する際は、次の点に注意が必要です。
- 相続税を申告しないと追徴課税の恐れがある
- 3年以内の相続登記が必要
- 今後固定資産税がかかる恐れがある
- 相続財産として評価しにくい
- 相続放棄をしても保存義務は負う
それでは、相続する際の注意点について解説します。
相続税を申告しないと追徴課税の恐れがある
相続税が課される場合、期日までに申告しないと追徴課税される恐れがあります。
受け継ぐ財産が基礎控除を超える場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に税務署に相続税申告書を提出しなければなりません。
期日までに申告しない場合、次の税金が課される可能性もあります。
| 税金の名称 | 概要 |
|---|---|
| 延滞税 | 期限までに納付しなかった際に課される税金 |
| 無申告加算税 | 期日までに申告しなかった際に課される税金 |
| 過少申告加算税 | 実際よりも低い金額で申告した際に課される税金 |
| 重加算税 | 申告内容を故意に隠ぺい、仮装した場合に課される税金 |
追徴課税の中には重加算税のように税率が40%に達するものもあるため、必ず期日までに申告し、相続税を納付しましょう。
3年以内の相続登記が必要
土地を相続した場合、不動産を相続で取得したことを知ってから3年以内に相続登記しなければなりません。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、期日内に登記を行わないと10万円以下の過料が科されるようになりました。
新たに取得した土地のみでなく、過去に相続した土地も義務化の対象となります。
過去に相続で取得した土地の相続登記が未了の場合は、2027年3月31日までに登記をしなければなりません。
今後固定資産税がかかる恐れがある
固定資産税がかからない土地であっても、将来的に課税される恐れがあります。
将来的に課税される主な例は、次のとおりです。
- 同一の市町村で土地を所有した
- 土地の固定資産税評価が上昇した
- 私道を個人で利用するようになった
土地の免税点である30万円を超えたり、用途非課税の対象から外れたりした場合などには固定資産税が課されます。
新たに固定資産税が課されることになった場合は、4月頃に自治体から固定資産税納税通知書が届きます。
相続財産として評価しにくい
固定資産税がかからない土地には固定資産税納税通知書が届かないため、相続財産としての評価額を算出する際に調査が必要となります。
通知書には、相続税の計算のもととなる固定資産税評価額が記載されています。
ただし、通知書は固定資産税が課されている不動産の所有者にしか郵送されません。
固定資産税評価額を知るためには、市町村の窓口で固定資産税評価証明書を取得する必要があります。
取得費用は自治体によって異なりますが、一般的に1通あたり200円から300円で取得できます。
相続放棄をしても保存義務は負う
相続放棄をしても、相続人は放棄した財産の保存義務が生じます。
遺産を相続したくない場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをおこなえば、相続財産を受け継がずに済みます。
ただし、放棄しても家庭裁判所が相続財産清算人を選任するまでの間は、相続人に相続財産の保存義務を負わなければなりません。
土地の場合は害虫や害獣が住み着くのを防ぐために草刈りをしたり、不法投棄を防ぐために管理したりする必要があります。
相続放棄から清算人の選任までには3か月程度かかるため、その期間中は相続放棄をしたとしても、相続財産を適切に管理しましょう。
固定資産税がかからない土地を処分する方法

固定資産税がかからない土地を処分する方法は、次のとおりです。
- 相続土地国庫帰属制度を活用する
- 空き家バンクに登録する
- 隣地の所有者に売却する
- 自治体に寄付する
- 業者に売却する
ここからは、土地を処分する方法について解説します。
相続土地国庫帰属制度を活用する
相続土地国庫帰属制度とは、相続によって取得した土地を有料で国が引き取る制度です。
制度を利用するためには、次の条件をすべて満たす土地である必要があります。
- 土地上に建物がない
- 利用を制限する権利がついていない
- 墓地や境内地、道路が含まれていない
- 土壌汚染の記録がない
- 境界が明確ではない
- 境界について係争していない
また、申請条件を満たしたとしても審査に通らない場合があることや、審査に通過しても負担金がかかることには注意が必要です。
詳しくは、法務省公式サイト「法務省 相続土地国庫帰属制度について」のページを参照してください。
空き家バンクに登録する
空き家バンクは、地方公共団体が運営する不動産の買い手と売り手をマッチングするための制度です。
郊外の不動産流通を促進するため、自治体が運営する公式サイトに売却物件の情報を掲載できます。
不動産会社が取り扱えない地域の物件でも掲載できるため、固定資産税がかからない土地の売却手段として有効です。
ただし、自治体によっては土地上に空き家がある物件のみを取り扱う場合があるため、注意が必要です。
隣地の所有者に売却する
隣地の所有者に売却すれば、一般の第三者に売却するよりも高く売れる可能性があります。
固定資産税がかからない土地の多くは、面積が小さい、利用できる用途が少ないなどの問題を抱えているため高く売れません。
しかし、隣地の所有者によっては、固定資産税がかからない土地でも利用価値が高まる場合があります。
なお、隣地の所有者が誰か調べる際は、法務局で隣地の土地の登記事項証明書を取得すれば、地主の住所と氏名がわかります。
隣地の所有者のみが得られるメリットもあるため、土地を売却する際は、まず隣地の所有者に購入の意思があるかどうかを確認しましょう。
自治体に寄付する
立地や状況によっては、自治体が土地の寄付を受け付けてくれる場合もあります。
固定資産税がかからない土地であっても、自治体にとって必要な土地であれば、寄付の審査後に引き取ってもらえるケースもあります。
たとえば、小学校の隣地で拡張のために必要な場合や、新たに公民館を建設するために必要な場合などです。
なお、無償でも有償でも、公共団体への譲渡は贈与税の課税対象外となります。
業者に売却する
買取業者に買取を依頼すれば、一般の買い手が見つからない土地でも売却できる可能性があります。
業者はビジネスチャンスがあると判断した場合、予想される利益額を基準に買取価格を算出します。
買取価格と予想される利益額のバランスが取れている物件であれば、利用に制限がある土地でも買取が可能です。
固定資産税がかからない土地は利用制限がかかりやすい物件ですが、安く購入できる可能性がある土地でもあります。
業者にとってはビジネスチャンスとなる物件でもあるため、固定資産税がかからない土地の売却を検討する際は、まず買取業者に相談してみましょう。
固定資産税が気になる土地の売却相談はファンズ不動産へ
固定資産税がかからない土地と聞くとお得に感じますが、実際には建築制限や利用制限が厳しいケースも多く、「この土地をどう扱うべきか」と悩む方も少なくありません。
相続した場合は、税金がかからなくても管理の手間や将来的なリスクが生じることもあります。土地の特徴や利用条件を正しく理解したうえで、適切な対応を検討することが大切です。
売却や活用方法に迷ったときは、早めに専門家へ相談することで、最適な選択肢を把握しやすくなります。
ファンズ不動産では、固定資産税が気になる土地のお悩みにも丁寧に寄り添い、状況に合わせて進め方をサポートします。
リノベ前提の物件や土地売却も。専門チームが対応
ファンズ不動産は、一般的なマンションや戸建てだけでなく、専門知識が求められる不動産の売却にも対応しています。
社内には土地売買のプロが在籍しているほか、2025年10月からはリノベーションのワンストップサポートも開始しました。
そのため「リノベーション前提」といった付加価値を付けた売却提案や、複雑な権利関係が絡む土地の売却も、窓口一つでスムーズに進められます。
他社では取り扱いが難しいと言われた物件でも、まずは一度相談してみる価値があるでしょう。
信頼度の高い買主とマッチングが可能
ファンズ不動産は、キュレーターの価値観に「共感」した、購買意欲の高いユーザーへ物件情報を届けます。
キュレーターは日頃からSNSで専門知識やライフスタイルを発信しており、人柄や実績が公開されています。
そのため単なる物件情報としてではなく、「あのキュレーターが勧める物件」という信頼度の高い情報として不動産情報を届けることが可能です。
情報発信のプロセスを介することで、物件の背景にあるストーリーや価値観を理解してくれる買主と出会う確率も高められるでしょう。
ぜひファンズ不動産で、物件への想いを共有できる「信頼できる買主」とのマッチングを実現してみましょう。
業者に買取を依頼するメリットとデメリット

固定資産税がかからない土地を売却する際は、買取業者への依頼が一般的です。
ただし、買取にはメリットとデメリットがあるため、それぞれの内容を理解したうえで利用を検討しましょう。
ここからは、買取のメリットとデメリットについて解説します。
買取のメリット
買取業者による買取には、次のようなメリットがあります。
- 仲介よりも早く現金化できる
- 条件が悪い物件でも購入してもらえる
- 仲介手数料がかからない
買取では買取業者が買主となるため、仲介のように買い手を探す時間は必要ありません。
ビジネスチャンスがあると判断されれば、条件が悪い土地でも買取してもらえ、1週間程度で現金化できる場合もあります。
また、不動産仲介会社を利用しなくても取引ができ、直接売買すれば仲介手数料はかかりません。
買取は仲介よりも売却価格が低くなる傾向がありますが、仲介手数料が不要なため、手元に残る資金の差がそれほど大きくならない場合もあります。
買取のデメリット
買取業者による買取には、次のようなデメリットがあります。
- 買取価格は相場より安くなる傾向がある
- 買取ができない物件もある
業者は購入金額に利益、リフォームや土地造成などの費用を上乗せして再販します。
相場で再販しなければ売却できないため、買取金額は仲介での売却よりも20~30%程度低く設定されることが一般的です。
また、買取業者には得意分野と不得意分野があるため、すべての不動産を取り扱っているわけではありません。
買取価格が安くて納得できない場合や、取り扱ってくれない場合は相続土地国庫帰属制度や空き家バンクの利用を検討しましょう。
固定資産税がかからない土地に関するよくある質問

固定資産税がかからない土地に関するよくある質問は、次のとおりです。
- 固定資産税のかからない土地の後継者は事前に決められますか?
- 固定資産税がかからない土地を無償譲渡したら贈与税は発生しますか?
それでは、よくある質問とその回答について解説します。
固定資産税のかからない土地の後継者は事前に決められますか?
固定資産税がかからない土地の後継者は、事前に遺言によって指定できます。
遺言とは、亡くなった方が生前に自身の最終的な意思を書き残すものです。
相続の際は、法定相続よりも遺言の内容が優先されます。
法定相続の内容によらず、自身の意思で特定の相続人に土地を受け継がせたい場合は遺言を活用します。
固定資産税がかからない土地を無償譲渡したら贈与税は発生しますか?
固定資産税がかからない土地を無償で譲渡した場合、受け取った方に贈与税が課税されます。
ただし、贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、控除額以内の財産を無償で譲渡する場合は課税対象外となります。
贈与した財産が110万円を超える場合は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までに贈与税申告書を提出しなければなりません。
なお、贈与税の納付期限も確定申告と同様に、贈与を受けた年の翌年3月15日までです。
まとめ
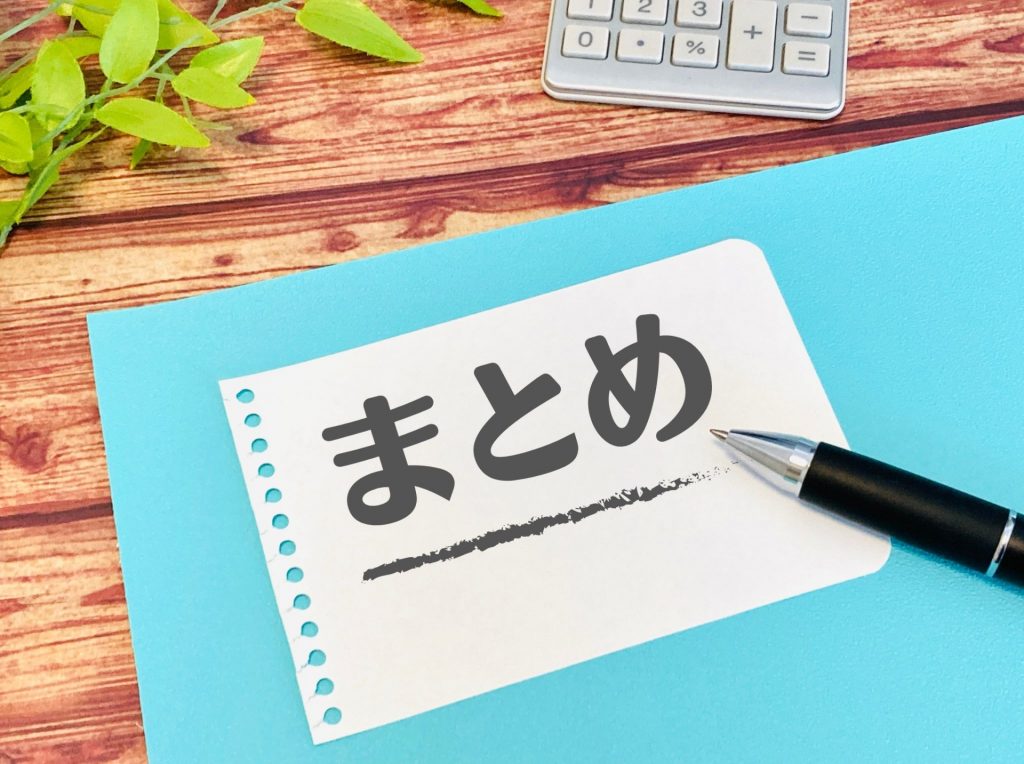
評価額が30万円未満の土地や、道路として提供されている土地などには、固定資産税が課されません。
固定資産税がかからない土地は利用できる用途が限られているため、そのまま保有しても活用が難しい場合が多いです。
相続税の基礎控除を超える遺産総額の場合は相続税がかかるため、土地を処分して売却代金を他の用途に活用し、節税対策をおこなうとよいでしょう。
利用できる用途が限られているため、一般の方が購入する可能性は低く、業者による買取がおすすめです。
業者による買取を利用すれば、迅速に現金化でき、すぐに相続対策を実行に移すことができます。













