共有名義の土地や家の売却には、全共有者の同意が必要なため、反対する方がいると売却できません。
しかし、共有持分の売却であればほかの共有者の同意なしでも売却できます。
とはいえ、共有持分の需要は低く、買い手が見つからない、売却価格が相場より低いなどの問題が発生する可能性が高くなります。
また、勝手に売却すると、ほかの共有者とトラブルになるケースもあるでしょう。
本記事では、共有名義の土地や不動産を売却する方法について、詳しく解説します。
併せて、売却にかかる費用や税金、買取業者に売却するリスク、トラブル事例と対処法なども紹介します。
共有名義の土地の売却に関する悩みや疑問がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
共有名義の不動産(土地・家)は売却できない?

共有名義の不動産は、状況によって売却できるケースとできないケースがあります。
判断のポイントとなるのは、共有者全員の合意が得られるかどうか、売却対象が自身の持分なのかという点です。
ここでは、共有名義の不動産を売却できる代表的な2つのケースについて、それぞれ解説します。
共有者全員の同意があれば売却可能
共有名義の不動産は、共有者全員が売却に同意していれば問題なく売却できます。
売却手続きは単独名義の不動産とほぼ同じ流れとなり、売却代金は原則として各共有者の持分割合に応じて分配します。
一方、共有者のうち一人でも売却に反対すると、不動産全体の売却は進められません。
共有名義では、契約締結や引き渡しといった各手続きにも全員の同意が必要となるため、事前の話し合いが欠かせない点に注意が必要です。
自身の持分は自由に売却できる
共有名義の不動産では、不動産全体の売却に同意が得られない場合でも、自身が所有する持分だけを売却することは可能です。
ただし、持分のみを購入しても物件を単独で利用できるわけではないため、買取の多くは不動産会社や投資家が中心となります。
結果的に、市場価格より低い金額での売却になりやすい点はデメリットといえるでしょう。
また、持分を第三者へ売却すると、残る共有者との関係が複雑化する可能性もあります。
トラブルを避けるためにも、持分売却を検討する際は事前に共有者へ説明したうえで、不動産会社や専門家へ相談するのをおすすめします。
不動産の共有持分とは?

不動産の共有持分とは、共有者それぞれの所有権の割合を指します。
兄弟姉妹で不動産を相続した場合や、夫婦や親子で不動産を一緒に購入した場合に設定するケースが一般的で、持分に応じた使用権が認められます。
不動産が共有名義になる理由や共有持分の割合、共有者に与えられる共有持分権などについて解説するため、ぜひトラブル回避に役立ててください。
不動産が共有名義になる理由
不動産が共有名義になる主な理由は、次のとおりです。
- 夫婦それぞれが資金を出してマイホームを購入
- 親と子がそれぞれ資金を出して二世帯住宅を購入
- 親の不動産を複数人で相続
住宅ローンを組んで不動産を購入する場合、共有名義にすると夫婦または親子の収入を合算して審査を受けられるため、借入可能額を増やせます。
また、共有名義の場合、一定の条件を満たせば共有者がそれぞれ住宅ローン減税の申請が可能で、節税対策にもなります。
不動産を複数人で相続した場合、共有名義にすると固定資産税や管理費、維持費の分担が可能です。
ただし、代表者が支払ったあとにほかの共有者へ請求するケースが一般的で、スムーズにいかないとトラブルに発展する可能性もあります。
さまざまな利点がある共有名義ですが、デメリットもふまえて慎重に検討しましょう。
共有持分の割合
共同でお金を出して不動産を購入した場合は、負担した金額に応じた共有持分に設定されることが一般的です。
たとえば、夫婦で3,000万円の住宅を購入する際、1,500万円ずつ出した場合の共有持分は互いに2分の1です。
一方、夫が2,000万円、妻が1,000万円を出した場合の共有持分は、夫が3分の2、妻が3分の1となります。
不動産を複数人で相続した場合は、法定相続分や遺言書に応じて割合を決めることが一般的です。
共有者には共有持分権がある
共有持分権とは、共有持分を有する者に認められている権利や行為を指します。
共有持分権を有する方に認められる内容の一例は、次のとおりです。
- 所有物を使用、管理、保存する権利
- 売却や贈与、賃貸借契約など変更、または処分する行為
ただし、それぞれ条件が設けられています。
たとえば、売却や贈与は、共有者全員の同意がなくてはおこなえません。
共有持分権を持つと、上記の権利や行為が認められますが、大部分でほかの共有者の理解を得る必要があります。
共有名義の土地や家の全体売却に反対された場合の売却方法

共有名義の土地や家を売却する際は、全共有者の同意を得る必要があります。
自身の共有持分であれば個人の判断で売却が認められるため、ほかの共有者や第三者、買取業者への売却も選択肢になります。
ほかには、土地を分筆して売却する方法もありますが、土地の状態次第では資産価値が下がる可能性もあるため、専門家に相談し慎重に検討すべきです。
共有名義の土地や不動産を売却する3つの方法について、詳しく解説します。
自身の共有持分を共有者に売る
共有持分は買い手が見つかりにくく売却は難しいですが、ほかの共有者が購入を希望するケースがあります。
たとえば、兄弟2人で物件を相続した場合、相手の共有持分を得ることで共有名義の土地を単独で所有できます。
単独名義になればさまざまな制限がなくなり、自由に物件を使用できるようになるため、買い取りを希望する方も多いでしょう。
共有名義の土地を相続する気がない場合、もうひとりの共有者は買い手として候補になります。
ただし、3人以上で共有している場合は、持分割合をめぐったトラブルが発生するおそれがあるため、注意が必要です。
身内でのトラブルを回避するためにも、売却する際は不動産会社立会いのもと、正当な売買契約の手続きをおこないましょう。
土地を分筆して売る
共有名義を解消する方法として、土地を分筆して単独名義で売りに出す方法もあります。
分筆とは、登記上一つの土地を複数に分けることです。
分筆した土地は単独名義にできるため、ほかの共有者の同意が得られなくても土地の売却が可能です。
ただし、分筆すると土地の資産価値が下がる可能性もあるため、不動産会社に相談してアドバイスを求めたほうがよいでしょう。
また、分筆して土地が小さくなると、建築を目的とする買い手のニーズには合わず、売れない可能性が高くなります。
安易に「分筆すれば自由に売れる」とは考えず、慎重に検討してください。
自身の共有持分を第三者に売る
自身の共有持分は、ほかの共有者の同意なしで第三者に売却できます。
共有持分を第三者に売却する場合、仲介業者を通じての売却か専門業者への買取依頼が一般的です。
仲介業者を介して共有持分の買い手を探す際は、売却成立まで時間がかかると考えたほうがよいでしょう。
なぜなら、他人と共同で使用する土地に魅力を感じる買い手が少ないためです。
早く現金化したい方には、共有持分の買取に対応している業者に依頼する方法が有効ですが、買取価格は相場より低くなりやすいことを押さえておきましょう。
共有名義の土地や家の売却で起こりうるトラブル事例

共有名義の土地や家の売却では、共有者がわからなかったり、売却価格が決まらなかったり、さまざまなトラブルが発生します。
売却したくても、ほかの共有者の同意が得られず売却できないこともあるでしょう。
共有名義の土地や家の売却で起こりうるトラブルを具体例とともに紹介し、対処法を解説します。
共有者がわからない
何度も相続が繰り返され、相続登記がおこなわれていなかった場合、共有者を把握できない場合があります。
共有者が分からないままだと、不動産は売却できません。
放置すればするほど、調査にかかる手間と時間が増えるため、早めに司法書士に相談しましょう。
売却価格が決まらない
高く売りたい売主側と、買い手の幅が広がるよう安く出したい不動産側とで話がまとまらず、売却価格が決まらないケースもあります。
話し合いがまとまらない場合は、まず複数の不動産会社に査定を依頼して相場を把握しましょう。
自身の言い値が正しいかどうかを判断し、希望の金額で売ったほうがよいのか、不動産会社の言い値で売ったほうがよいのかがわかります。
他の共有者の同意が得られない
複数人で不動産を相続すると、売却したい派としたくない派で意見が衝突するケースも少なくありません。
2人で相続して意見が分かれる場合は、共有持分を相手に売ることで解決可能です。
しかし、3人以上で意見が衝突する場合、話がまとまらない可能性が高くなります。
どうしても売却したい方が、独断で共有持分を第三者や買取業者に売却すると、余計にトラブルが大きくなります。
親族に話し合いに参加してもらう、相続を放棄するなどの対処法も念頭に置くとよいでしょう。
贈与とみなされる場合がある
共有名義の土地や家を売却する際、相場より著しく低い価格で持分を譲渡すると税務上「贈与」と判断される可能性があります。
特に、親族間での売却や名義整理を目的とした取引では、実態よりも価格を下げて契約していないか注意が必要です。
贈与とみなされると、受け取った側に贈与税が課されることがあり、想定外の税負担が発生しかねません。
意図せず税務上のトラブルに発展するケースもあるため、事前に不動産会社や税理士へ相談し、適正な価格で取引を進めましょう。
勝手に共有持分を売却される
共有持分の売却に同意が必要ないことを逆手に取り、勝手に売却されると、突然他人が共有者になります。
勝手に売却した先が買取業者だった場合、稀に強引な営業で共有者に買い取りを持ちかけられるケースもあります。
共有者間で意見が衝突する場合でも、勝手に共有持分を売却し話し合いから離れることはおすすめできません。
互いが納得できる点が見つかるまで、根気よく話し合いを続けるべきです。
共有名義の土地や家を売却する際の注意点

共有名義の土地や家を売却する場合、進め方を誤ると、共有者間のトラブルや不利な条件での売却につながるおそれがあります。
とくに注意したいポイントは、次のとおりです。
- 買取業者への売却は避ける
- 個人売買はしない
- 信頼できる不動産会社に依頼する
- 売却スケジュールに余裕をもつ
それぞれの注意点について、詳しく確認していきましょう。
買取業者への売却は避ける
共有名義の土地や家を売却する際、安易に買取業者を選ぶのはおすすめできません。
買取はスピーディーに現金化できる反面、相場よりも売却価格が大きく下がりやすく、共有者全員が納得できない結果になる可能性が高くなります。
「安すぎる」「もっと高く売れたはずだ」といった不満が生じやすく、売却後にトラブルへ発展するケースも少なくありません。
価格の妥当性や説明責任を明確にし、共有者間の合意を得ながら進めるためにも、まずは仲介による売却を検討するほうが無難でしょう。
個人売買はしない
共有名義の土地や家を個人間で売買すると、契約内容の不備や認識のズレが生じやすく、結果としてトラブルに発展するおそれがあります。
とくに、共有名義では共有者全員の意思確認や契約条件の整理が欠かせず、専門知識がないまま手続きを進めるのはおすすめできません。
代金の支払い方法や引き渡し条件、税務上の扱いをめぐるトラブルを避けるためにも、個人売買は避け、必ず専門家を介した取引を選びましょう。
信頼できる不動産会社に依頼する
共有名義の不動産売却では、信頼できる不動産会社に依頼しましょう。
共有者間の調整や説明が必要になる場面が多く、経験の浅い対応では話し合いが滞るケースも少なくありません。
売却実績が豊富な不動産会社であれば、法的な注意点や手続きの流れを整理しながら、全員が納得できる形で売却を進めてもらえます。
実績や説明の丁寧さなどを確認したうえで、依頼先を判断しましょう。
売却スケジュールに余裕をもつ
売却スケジュールに余裕をもつことも、共有名義の土地や家を売る際に注意すべきポイントのひとつです。
共有名義の場合、共有者全員の同意や条件調整に時間がかかりやすく、単独名義に比べて売却まで長引く傾向があります。
急ぐとトラブルにつながったり、条件面で妥協せざるを得なかったりする可能性もあるため、早めに準備を始め、計画的に進めることが大切です。
共有名義の土地や家を安全に売却するならファンズ不動産
共有名義の土地や家の売却は、名義人全員の合意や手続きの進め方など、慎重な対応が求められます。進め方を誤ると、思わぬトラブルや売却の長期化につながることも少なくありません。
安全に売却を進めるためには、事前に注意点や流れを整理し、冷静に判断することが大切です。
共有名義不動産の売却について迷いがある場合は、相談先の一つとしてファンズ不動産を検討してみるのもよいでしょう。納得のいく売却を目指すことが重要です。
売却が初めての方へ:ファンズ不動産が選ばれる3つの強み
ファンズ不動産は、売主様が抱える不安を解消する、独自の「訴求力」「専門性」「手軽さ」を兼ね備えています。
- 訴求力:1万人超のLINE登録者へ直接情報を届ける高い「訴求力」が、早期の買主発見をサポートします。
- 専門性:都心特化・設立1年半で取扱高100億円を突破した「専門性」が、適正な価格設定と売却戦略を実現。
- 手軽さ:オンライン面談からLINEで活動を進められる「手軽さ」が、忙しい方でもスムーズな売却を可能にします。
初めての売却で不安をお持ちなら、まずはLINEでの気軽なご相談から、納得のいく売却への第一歩を踏み出しましょう。
オンライン面談から開始。LINEで完結する売却プロセス
ファンズ不動産での売却活動は、忙しい方でもストレスなく進められる「手軽さ」が特徴です。
最初の相談は店舗に出向く必要のない「オンライン面談」からスタートします。その後の担当者とのやり取りや進捗確認も、主にLINEでおこなうため、日中の時間を拘束されません。
仕事や家事で忙しい方でも、自身のペースで効率的に売却活動を進めたい方に最適です。
1万人超の「買いたい」層へLINEで直接アプローチ
ファンズ不動産の公式LINEには、1万人を超える購買意欲の高いユーザーが登録しています。
従来のポータルサイトで不特定多数の閲覧を「待つ」のとは異なり、関心の高い層へ直接物件情報を「届ける」ことが可能です。
物件の魅力を理解してくれる可能性が高いユーザーへ絞ってアプローチできるため、スピーディーな反響が期待できます。
早期売却を目指す方にとって、この「届ける」力は大きな強みとなるでしょう。
共有名義の土地や家の売却に必要な費用・税金

共有名義の土地や家の売却には、仲介手数料や司法書士報酬、登録免許税などさまざまな費用や税金が掛かります。
必要なお金の種類、相場の事前調査を怠ると、売却後に想定外の出費や納税義務に頭を抱えることになりかねません。
そこで、共有名義の土地売却にかかる諸費用や税金、さらに譲渡所得がある場合の確定申告について、詳しく解説します。
必要な諸費用
共有名義の土地の売却には、次のような費用が掛かります。
- 仲介手数料
- 測量費
- 司法書士報酬
不動産会社を通じて共有持分を売却すると、仲介手数料が発生します。
手数料は売却金額により異なり、上限額は「売却価格×3%+6万円+消費税※」の計算式で求められます。
測量費は土地の境界を調べるための調査にかかる費用、司法書士報酬は抵当権抹消登記の依頼にかかる費用です。
それぞれ土地や不動産の状態、依頼内容により金額が異なるため、自身のケースに即した見積もりを取り詳細を確認しましょう。
※売買金額が400万円を超える場合の計算式です。
売却でかかる税金の種類
共有名義の土地を売却すると、次のような税金がかかります。
- 譲渡所得税
- 登録免許税
- 印紙税
共有名義の土地を売却して譲渡所得が出た場合、金額に応じた譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税の計算式は「(売却価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特例控除)× 税率」で、売却した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えるか否かで税率が異なります。
登録免許税は登記をする際に必要になる税金、印紙税は不動産売買契約書の作成時に必要な税金です。
内容と課税額をよく確認して、納付漏れがないよう注意しましょう。
税金控除に利用できる特例
共有名義の土地や家を売却する場合でも、一定の条件を満たしていれば、税金負担を軽減できる特例を活用できます。
代表的な制度として挙げられるのが、「居住用財産の3,000万円特別控除」や「所有期間10年超の軽減税率の特例」です。
売却した不動産が自分の居住用であれば、譲渡所得から3,000万円まで控除できる可能性があり、共有者それぞれが利用できるケースもあります。
ただし、共有者全員が居住していたかどうか、過去に同様の特例を適用していないかなど、確認すべき条件は少なくありません。
特例が使えるかどうかは状況によって左右されるため、不動産会社や税理士に相談しながら進めることがおすすめです。
譲渡所得がある場合は確定申告が必要
原則として、共有名義か単独名義かは関係なく、不動産を売却して譲渡所得が発生したら確定申告が必要です。
譲渡所得は、売却価格から取得費(購入代金や取得時にかかった費用)と譲渡費用(仲介手数料や司法書士報酬や測量費など)を差し引いた金額です。
譲渡所得がプラスの場合は、申告義務が生じます。
確定申告の期間は、売却した翌年の2月16日から3月15日までです。
申告漏れや申告遅れはペナルティを課せられるため、必要書類を早めに準備して必ず期日内に申告を済ませましょう。
共有名義の土地や家を売却する際の手続き・必要書類
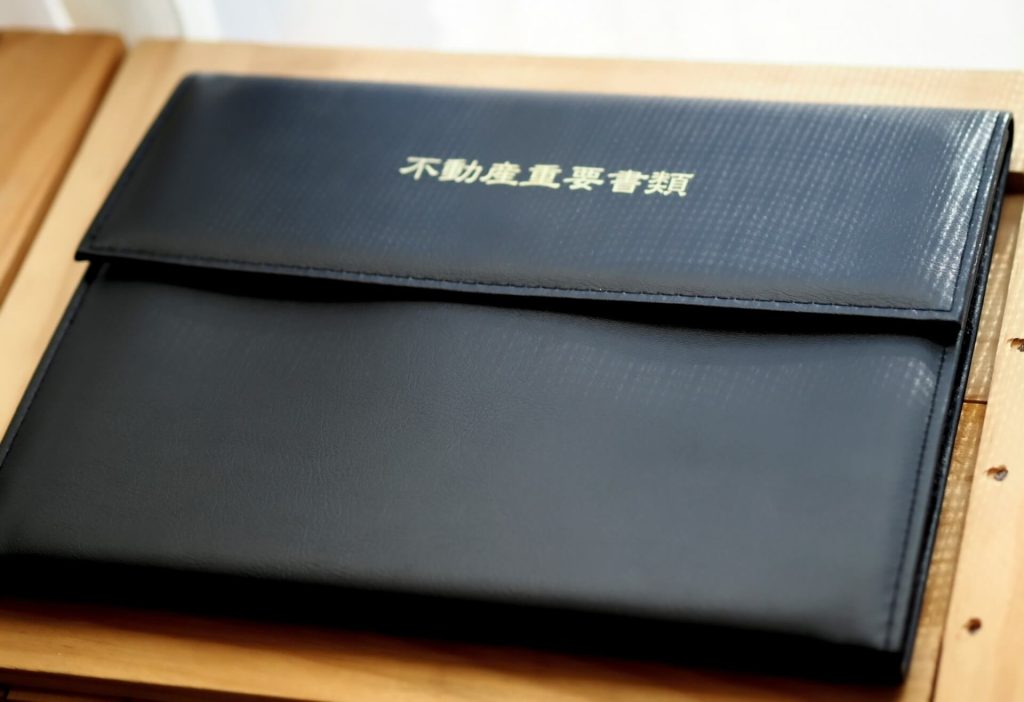
共有名義の土地や家を売却する際、多くの手続きが生じ、そのたびに複数の書類の用意が必要です。
いざ、売却するときに慌てないよう、共有名義の土地や家を売却する流れ、手続きの際に必要になる書類について詳しく解説します。
必要な書類
共有名義の土地を売却する際は、次のような書類が必要になります。
- 権利証もしくは登記識別情報
- 土地測量図
- 境界確認書
- 身分証明書
- 住民票
- 印鑑登録証明書
権利証は、不動産の所有権を証明する書類です。
平成17年以前に所有権を取得している場合、共有名義でも権利証の発行は1冊のみだったため、共有持分の所有権を証明する書類がないケースも珍しくありません。
権利証がない場合は、司法書士が本人確認をおこない、所有者であると証明してもらう手続きが必要です。
土地を売却する際は、土地測量図や境界確認書で、土地の境界を明確にしなくてはなりません。
身分証明書、住民票、印鑑登録証明書はさまざまな場面で必要になるため、忘れずに用意しておきましょう。
売却の流れ
共有者全員が共有名義の土地売却に同意している場合は、まず複数の不動産会社に査定を依頼し、対応やアドバイス内容、査定額を比較しましょう。
信頼できる不動産会社と媒介契約を結んだら、売却活動を依頼します。
買い手が決まるまでの間は、売却にかかる費用の見積もりや負担する割合を決めておくと、売却後のトラブル回避につながります。
買い手との売買契約が締結したら、室内を空の状態にして引き渡せるよう不用品を処分しましょう。
大量にあると専門業者への依頼が必要になるため、早めに不用品を処分しておけば、スムーズに引き渡しをおこなえます。
共有名義の土地や家を勝手に売却された際の対処法

共有名義の土地や家は、「知らない間に話が進められていた」「一部の共有者が勝手に売却を進めていた」といったトラブルが起こるケースもあります。
このような状況に直面した場合、重要になるのは「不動産を手放してもよいのか」「それとも所有を続けたいのか」という判断です。
希望する方向性によって、取るべき対応は大きく異なります。
ここでは、不動産を手放してもよい場合と、手放したくない場合に分けて、具体的な対処法を解説します。
不動産を手放してもよい場合
共有名義の不動産を手放しても構わないと考えている場合は、条件面を整理したうえで売却を進めるのが現実的でしょう。
売買契約を締結する際には共有者全員の同意が必要であり、改めて売却条件や代金の分配方法について話し合う場を設けられるよう働きかけることが大切です。
売却代金の分け方は原則として持分割合に応じますが、これまでの負担状況や共有者間の合意によって調整されるケースもあります。
冷静に話を進めやすくするためにも、話し合いをする際は不動産会社や専門家に間に入ってもらい、書面に合意内容を残しておきましょう。
不動産を手放したくない場合
不動産を売却したくないと考えている場合は、売却に同意していない意思を明確に伝えることが重要です。
すでに売却の話が進んでいる場合でも、状況によっては差止めや契約を無効にできる可能性があります。
できるだけ早い段階で弁護士や司法書士に相談し、法的な対応が必要か確認しましょう。
また、将来的なトラブルを防ぐ手段として、共有関係そのものの解消を検討するのも選択肢のひとつです。
不動産の共有名義を避ける方法

不動産の共有名義は、共有持分権を明確にできる反面、将来的にはさまざまなトラブルにつながる可能性もあります。
トラブルを回避したい方は、不動産の共有名義は避けたほうがよいでしょう。共有名義を避ける方法を2つ紹介します。
遺産分割時に共有名義にしない
不動産の所有者が遺言書を遺さずに他界した場合、相続を公平にしようと不動産を共有名義にしがちですが、リスクも考慮して慎重に検討すべきです。
遺産の不動産を共有名義で相続すると、次のような問題が生じます
- 売却時に意見がまとまらず揉めやすい
- 共有持分を勝手に売却し、他人が共有者になる可能性がある
- 時間が経つと権利関係が複雑になる
1つの不動産を複数人で相続した場合、売却するためには全員の同意が必要になるため、意見が衝突する可能性があります。
収拾がつかずそのままにする場合でも、管理費が発生するとだれが負担するかで揉めるケースも少なくありません。
共有名義による不動産の相続は、はじめこそ争いを生まない平和な解決法に見えますが、長い目で見ると多くのリスクがともなうためおすすめできません。
共有物分割をおこなう
すでに共有名義の土地を所有している方は、共有物分割をおこない共有物に関する悩みや不満を解決しましょう。
共有物分割とは、共有状態を解消するための方法であり、次の3つの方法があります。
| 現物分割 | 土地を分筆して共有から単独の所有に変える方法 |
|---|---|
| 換価分割 | 不動産を売却して現金を分ける方法 |
| 代償分割 | 相続人の一人が不動産を相続し、相続しなかった方に持分相当の現金や資産を渡す方法 |
話し合いで方針が決まらない場合は、裁判所に共有物分割を請求するとよいでしょう。
共有名義の土地や不動産の扱いは難しくトラブルが多いため、問題を避けたい方は共有物分割をおこなうのをおすすめします。
参照元:e-Gov 民法
共有名義の不動産売却に関するよくある質問

最後に、共有名義の不動産売却に関するよくある3つの質問に回答します。
特別控除や確定申告に関する疑問がある方、ほかの共有者への譲渡を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
土地のみの売却でも3,000万円の特別控除は受けられる?
過去に住居用建物が存在していた土地であれば、土地のみの売却でも3,000万円の特別控除は受けられます。
ただし、3,000万円特別控除は、建物の有無により適用期間が異なるため注意が必要です。
具体的には、住居を解体し土地のみで売却する場合、特別控除の適用期間は取り壊した日から1年以内に売買契約を締結しなければなりません。
譲渡所得税に対する3,000万円の特別控除は、あくまで住居用の土地が対象です。別荘や投資用のマンションがあった土地は該当しません。
参照元:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例
共有持分を共有者に譲渡できる?
共有持分は、売却か贈与により他の共有者に譲渡できます。
売却する場合は、売買契約書や持分の移転登記などをおこなわないと、後々共有者を正しく把握できないトラブルに発展しかねません。
身内とはいえ、必ず不動産会社や司法書士などの専門家を交えて、正式な手続きをおこないましょう。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告をしないと、違反内容により次のようなペナルティが課せられます。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
期限までに確定申告しなかった場合、ペナルティとして原則約15〜30%の無申告加算税が課せられます。
期限内に確定申告は済ませたものの、納付がおくれた場合には延滞日数に応じて納付額が上乗せされます。
また、確定申告の内容に誤りがある場合もペナルティの対象になるため、正確に申告できているか不安な方は専門家に依頼したほうがよいでしょう。
まとめ

共有名義の土地や家は、全共有者の同意があれば1つの不動産として売却できます。
同意が得られない場合には、自身の共有持分をほかの共有者、もしくは第三者や買取業者に売却する方法もあります。
共有名義の土地や家は扱いが難しく、将来的に多くのリスクを抱える結果になりかねません。
トラブルを回避したい場合は、共有名義で不動産を購入しない、遺産相続時は共有名義以外の相続の仕方を検討したほうがよいでしょう。
すでに共有名義を所有している方は、共有物分割をおこなうことで不安や悩みを解決できます。
土地や物件の購入、不動産の相続時には軽率に共同名義を選択せず、トラブルの少ない方法を選ぶためよく話し合うことが大切です。













