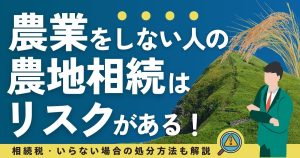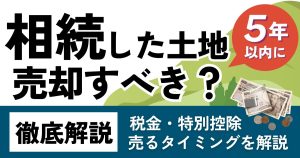相続した土地を3年以内に売却したほうがよいと聞くけれど、「本当に?」「なぜ?」という疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
結論、相続した土地は3年以内に売却するのがおすすめです。3年以内に売却すれば、税金を大きく軽減できる特例や控除を利用できるためです。
本記事では、3年以内売却の具体的な税制メリットや2つの重要な特例、手続きや注意点まで徹底解説します。
最後には、自身にとって最適な売却タイミングや、損をしないためのポイントが明確になり、安心して一歩を踏み出せるようになるでしょう。
相続した土地を3年以内に売却すべき?

相続した土地の売却は、3年以内を目指しましょう。
理由は、相続開始の翌日から3年以内に売却すれば、次の制度が適用されて節税できる可能性があるためです。
- 取得費加算の特例
- 3,000万円特別控除
相続から3年を超えると、上記特例は利用できず、固定資産税の支払いや管理の手間などの負担が増えるため、注意が必要です。
ここからは、実際にかかる税金の種類や、利用できる特例について詳しく解説します。
相続した土地を売却したときにかかる税金
相続した土地を売却する際にかかる税金は5種類で、相続3年以内の売却で特例のあるものとないものがあります。
特例のある税金は、次の2つです。
- 所得税
- 住民税
一方、特例の無い税金は次の3つです。
- 印紙税
- 登録免許税
- 消費税
相続した土地の売却により発生した利益には、譲渡所得として税金がかかります。
譲渡所得の計算では、取得費や売却にかかった費用も考慮されますが、相続による取得の場合、被相続人の取得費を引き継ぐため、計算方法が複雑になる場合もあります。
また、売却金額が大きくなると所得税・住民税の税率も高くなるため、事前にシミュレーションが不可欠です。
加えて、場合によっては確定申告書や明細書などの書類提出が必要となり、税務署への申告期限も守らなければなりません。
土地売却に伴う税金の計算は複雑でわかりにくいため、専門家への相談がおすすめです。
2つの特例の適用で節税が可能
相続した土地を3年以内に売却した場合、取得費加算の特例と3,000万円特別控除の特例が適用される可能性があります。
取得費加算の特例は、相続税として納めた金額のうち一定額を売却時の取得費に加算できる制度です。
譲渡所得の計算上、利益が抑えられ、結果的に納める税金も軽減されます。
一方、3,000万円特別控除は、相続した土地を一定の要件で売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
特例の併用はできないため、どちらがより有利になるかシミュレーションした上で選択することが節税の鍵となります。
相続した土地を3年以内に売却した場合の「3,000万円特別控除の特例」

3年以内に相続した土地を売却する最大のメリットは、3,000万円特別控除を活用し、大幅に節税できることです。
該当する条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。
たとえば、売却益が3,000万円以下なら所得税・住民税が0円になるケースも珍しくありません。
この特例は取得費や相続税の加算とは別の制度で、資産売却時の税負担を大きく減らせるチャンスです。
ここでは適用要件から手続きまで、実際の申告に役立つポイントを解説します。
適用要件
3,000万円特別控除の対象となるためには、相続開始から3年後の年末までに売却し、相続した空き家と売却時の状態が次の条件を満たす必要があります。
| 相続した空き家の適用条件 | 売却時の状況の適用条件 |
|---|---|
| 空き家と土地を併せて相続している 建築された年は1981(昭和56)年5月31日以前である 相続開始まで被相続人が住んでいた 相続開始から売却まで空き家だった | 売却先は第三者である 売却額は1億円以下である 相続してから3年目の年末までに売却した 地震に対する安全基準等に適合した状態、もしくは建物を取り壊した状態で売却した |
申告書や明細書の提出も必要なため、手続きを怠らないようご注意ください。
計算方法
3,000万円特別控除の計算方法はシンプルで、売却により得た譲渡所得から3,000万円を差し引けば課税対象となる金額が算出できます。
たとえば、譲渡所得が2,800万円なら課税対象額は0円となり、税負担が一切発生しません。
譲渡所得は売却代金から取得費や仲介手数料、登記費用などを差し引いて算出します。
また、取得費が不明な場合は、売却代金の5%を取得費とする簡易計算も認められています。
確定申告時には、計算結果や控除額を正確に記載した内訳書や資料を添付しなければならないため注意しましょう。
手続き方法
3,000万円特別控除を受けるためには、確定申告の際に必要な書類をそろえ、正しく手続きをおこなうことが重要です。
必要書類は、売買契約書や登記事項証明書、被相続人が居住していたことを証明する書類などです。
さらに、空き家の場合は耐震基準適合証明書や家屋解体証明書なども揃えなければならないケースもあります。
不備がないよう、税務署の窓口や専門の税理士に相談しながら、申告期限までに提出しましょう。
相続した土地を3年以内に売却した場合の「取得費の特例」

相続した土地を3年以内に売却した場合、取得費加算の特例を利用して節税できるケースもあります。
取得費の特例は、譲渡所得の金額を大きく抑えることで税金の負担が軽減できる制度です。
とくに、相続税を支払っているケースでは節税効果が大きく、実際の負担額が数十万円単位で変わることも珍しくありません。
ここからは、取得費加算の特例の適用要件や計算方法、手続きのポイントなどを詳しく解説します。
適用要件
取得費加算の特例は、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却する場合の次の条件を満たしたときに適用されます。
- 相続や遺贈により取得した不動産であること
- 相続税を支払っていること
たとえば、父親から土地を相続し、相続税の申告・納付を済ませたうえで、その土地を3年以内に売却した場合が典型です。
適用の際は、相続税の申告期限や確定申告書の作成、必要な書類の提出が求められるため、事前に準備しておきましょう。
計算方法
取得費加算の特例では、売却する土地や建物に関して納付した相続税の一部を取得費として加算できます。
取得費加算特例の適用を受けた場合、譲渡所得は次のように計算します。
譲渡所得=不動産の売却額−(取得費+譲渡費用)−取得費加算
なお、取得費加算として認められる金額の計算方法は複雑であり、計算するには税務の知識が欠かせません。正確な取得費を知りたい方は、税理士に相談して計算してもらいましょう。
手続き方法
取得費加算の特例を適用するには、相続した土地を売却した翌年に、次の書類を添付して確定申告をおこなう必要があります。
- 相続税の申告書の写し(第1表、第11表、第11の2表、第14表、第15表)
- 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書【土地・建物用】)
手続きに不備があると特例が認められない場合もあるため、不動産会社や税理士と連携しながら、余裕を持って準備しましょう。
相続土地の売却タイミングに迷ったらファンズ不動産へ
相続した土地を「3年以内に売却すべきか」は、多くの方が悩むポイントです。税金の控除や特例の適用は期限が決まっているものも多く、タイミングを誤ると負担が大きくなる可能性があります。
また、土地の状態や市場の動きによって、売却に適した時期は変わるため、早めに状況を整理して判断することが大切です。
迷ったときは、専門家へ相談することで、税制面と不動産面の両方から適切な方向性を見極めやすくなります。
ファンズ不動産では、相続土地の売却に関する不安にも丁寧に寄り添い、最適な進め方を一緒に考えるサポートが受けられます。
売却が初めての方へ:ファンズ不動産が選ばれる3つの強み
ファンズ不動産は、売主様が抱える不安を解消する、独自の「訴求力」「専門性」「手軽さ」を兼ね備えています。
- 訴求力:1万人超のLINE登録者へ直接情報を届ける高い「訴求力」が、早期の買主発見をサポートします。
- 専門性:都心特化・設立1年半で取扱高100億円を突破した「専門性」が、適正な価格設定と売却戦略を実現。
- 手軽さ:オンライン面談からLINEで活動を進められる「手軽さ」が、忙しい方でもスムーズな売却を可能にします。
初めての売却で不安をお持ちなら、まずはLINEでの気軽なご相談から、納得のいく売却への第一歩を踏み出しましょう。
オンライン面談から開始。LINEで完結する売却プロセス
ファンズ不動産での売却活動は、忙しい方でもストレスなく進められる「手軽さ」が特徴です。
最初の相談は店舗に出向く必要のない「オンライン面談」からスタートします。その後の担当者とのやり取りや進捗確認も、主にLINEでおこなうため、日中の時間を拘束されません。
仕事や家事で忙しい方でも、自身のペースで効率的に売却活動を進めたい方に最適です。
相続した土地を3年以内に売却する際の注意点

3年以内に相続した土地を売却する場合、税金や手続き面で重要な注意点があります。
知らずに進めてしまうと、節税特例を受けられなかったり、余計な負担が発生したりする可能性もあります。
ここでは、特例の併用不可や所有形態、売却活動のタイミングなど、実務でよくあるトラブルを防ぐための具体的なポイントを紹介します。
2つの特例は併用できない
取得費加算の特例と3,000万円特別控除は、併用できません。
実際にどちらを選ぶべきかは、相続税の金額や売却価格によって大きく異なります。
基本的に、相続税を多く納付している場合は取得費加算の特例を、譲渡所得が大きい場合は3,000万円特別控除が有利になります。
事前にシミュレーションして最適な選択を心がけましょう。
単独所有の状態で売る
売却する土地が複数人の共有名義になっている場合、特例の適用が難しくなります。
とくに3,000万円特別控除では、相続人それぞれが単独で所有している必要があり、遺産分割協議で名義を整理してから売却しなければなりません。
たとえば兄弟で土地を共有している状態では控除額が分割されるなど、期待した節税メリットが得られないこともあります。
売却前には登記内容を確認し、必要に応じて登記事項証明書を取得しましょう。
手続きの流れや注意点は専門家への相談がおすすめです。
早めに売却活動を開始する
3年以内の期限は意外に短く、売却活動は早めの開始がおすすめです。
相続手続きや買い手探し、契約、登記などの売却活動には予想以上に時間がかかります。
実際、土地や建物の状態確認や不動産会社への査定依頼など、売買契約までにやるべきことが多岐にわたるうえ、空き家や古家付き土地の場合は、解体や管理の問題も絡んできます。
売却の期限を過ぎると特例が使えなくなるため、手続きや資料の準備はできるだけ早めに進めましょう。
相続から3年を超えた土地も売却を急ぐべき?

相続から3年を過ぎた土地も放置せず、早めの売却がおすすめです。
相続から3年を過ぎた土地の放置は、特例や控除を受けられなくなるのみでなく、維持コストや資産価値の下落、トラブル発生のリスクも高まります。
ここでは、土地を長期間持ち続けた場合に起きやすい具体的なリスクや、短期譲渡での税金負担についてわかりやすく解説します。
土地を放置し続けるとリスクがある
土地を相続したものの、売却せず放置すると、さまざまなリスクが発生します。
代表的な負担は、固定資産税や管理費用です。また、空き地や空き家を長く放置すれば、草木が伸びたり、建物が劣化したりなどによる近隣とのトラブルが発生する恐れがあります。
さらに、土地や建物の資産価値が年々下がるケースも多く、将来の売却価格が低下するリスクもあります。
特例が使えなくなると、税負担も増すため、計画的な売却を検討しましょう。
短期譲渡の場合は税率が高くなる
相続した土地を売却する際の所有期間は、ご自身が相続した日からではなく、亡くなった方(被相続人)がその土地を取得した日から計算します。
もし、被相続人の所有期間と合わせて5年以下の場合は短期譲渡とみなされ、譲渡所得に対する税率が高くなります。
たとえば、5年以内の売却での税率は約39%ですが、5年超の長期譲渡では約20%です。
3年以内の売却であれば特例を使えば得できることもありますが、そもそもの税率が高いため、状況次第では5年を過ぎてから売却する方がいいケースもあるでしょう。
タイミングを誤らないことが納税額を抑えるポイントです。
相続した土地を3年以内に売却するときによくある質問

最後に、相続した土地を3年以内に売却する場合の税金や手続きについて、よくある質問を紹介します。
手続きをスムーズに進め、無駄な税負担やトラブルを避けるためにも、正しい知識を身につけましょう。
確定申告が不要のケースとは?
原則として、相続した土地を売却した場合は確定申告が必要です。
ただし、売却による譲渡所得がゼロ、またはマイナスの場合は、確定申告が不要になるケースもあります。
たとえば、売却価格から取得費や仲介手数料、登記費用などの必要経費を差し引いたときに利益が出ず、給与所得のみでその他の所得もなければ、確定申告が不要となるケースもあります。
自身のケースが該当するか不安な方は、税務署や税理士に早めに相談して確認しましょう。
確定申告をしないとどうなる?
本来、確定申告が必要な場合に申告を怠ると、加算税や延滞税などのペナルティが発生します。
たとえば、譲渡所得に対する所得税や住民税の納付が遅れると、追加で税金を支払うことになり、手続きも複雑になります。
また、特例や控除を利用したい場合は、必ず確定申告書や内訳書を期限内に提出しなければなりません。
確定申告を忘れると、取得費加算の特例や3,000万円特別控除が適用できなくなり、本来よりも大きな負担を背負うことになります。
3年以上5年以内の場合に適用できる特別控除はある?
相続開始から3年を超えて土地を売却した場合、原則として取得費加算の特例や3,000万円特別控除は適用できません。
たとえば、売却が4年目になった場合は、譲渡所得に対する税金がすべて課税されます。
ただし、ほかの一般的な控除や特別な事情がある場合は、個別に税務署へ相談する余地はあります。
節税メリットを最大限に活かしたい場合は、なるべく3年以内の売却を目指し、制度適用条件を事前に確認しましょう。
まとめ

相続した土地は、3年以内の売却により節税や税金対策の面で非常に大きなメリットを受けられます。
とくに、国税庁が定める3,000万円特別控除や取得費加算の特例の適用で、譲渡所得税や住民税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
しかし、特例には適用要件や期限、確定申告書の提出など細かな条件があるため、早めに手続きを開始し、必要な書類や明細書の準備が大切です。
また、土地の放置は固定資産税や管理費用、資産価値の下落などリスクが多く危険です。
相続した不動産の売却を検討する際は、今回の記事内容を参考に、最適なタイミングで売却しましょう。