「土地を売却するときの解体費用はいくらかかるの?」と、古家付きの土地を売却する場合、解体費用の相場について知りたい方もいるでしょう。
解体費用は建物の構造や土地の立地によって変動し、条件によっては100万円以上かかる場合もあります。
土地を売却する前に解体費用の相場を把握していないと、予想よりも手元に残る資金が少なくなるかもしれません。
本記事では、土地売却時の解体費用の相場や解体のメリット・デメリットについて解説します。
土地売却で古家の取り壊しを検討している方や、解体費用がどのくらいかかるのかなどが知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
土地売却における解体費用の相場
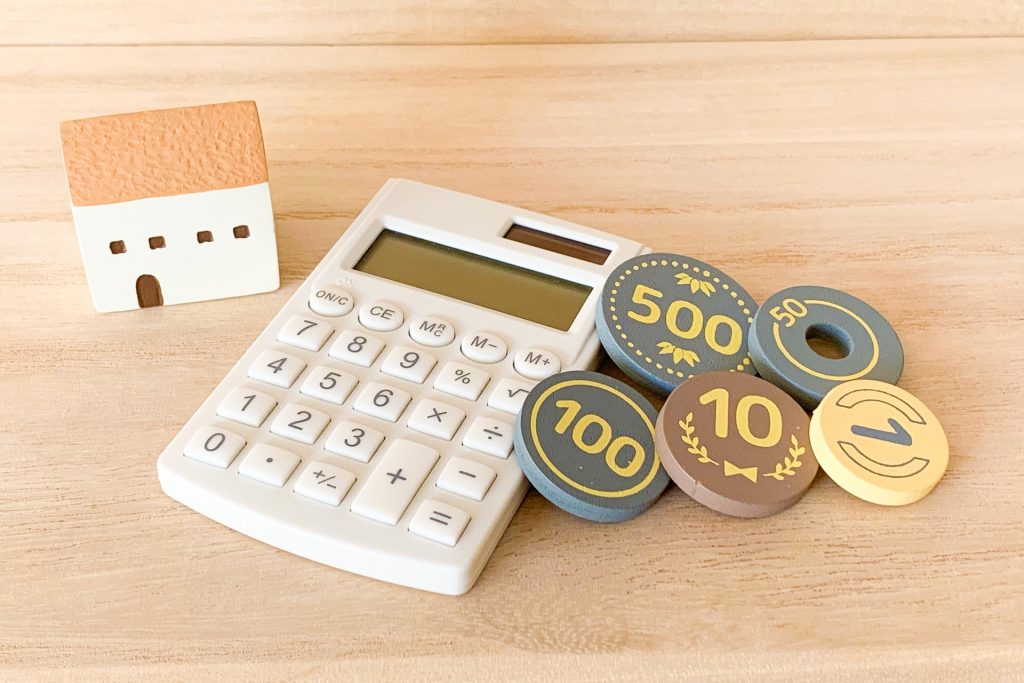
土地を売却する際の解体費用の相場は、建物の構造や土地の状況によって異なります。
ここからは、構造別の相場や費用が高くなる理由について解説します。
構造によって相場は異なる
解体費用は建物の構造によって、次のように相場が異なります。
| 木造 | 坪当たり3万円~5万円 |
|---|---|
| 鉄骨造 | 坪当たり4万円~6万円 |
| 鉄骨鉄筋 コンクリート造 | 坪当たり5万円~8万円 |
※一般的な住宅の大きさを想定
建物が頑丈になると油圧ショベルのみでは解体できず、コンクリートクラッシャーのような特殊な機材を利用しなければなりません。
また、構造によっては産業廃棄物の重量が増加し、分別作業や運搬作業のコストも高くなります。
建物が硬くなるほど壊しにくくなり、作業全体のコストも上昇するため、構造によって価格に差が生じます。
土地の状況で費用が高くなる
建物の構造が同じだとしても、土地の状況によって解体費用が高くなります。
たとえば、次のような土地の場合、解体費用が高くなる傾向にあります。
- 車庫や物置など残置物がある
- 樹木の伐採処分費用がかかる
- 解体現場に接する道が細く重機を搬入できない
- 隣の家が近すぎて重機を利用できない
- 交通量が多く警備員が必要になる
土地の状況によって、解体作業にかかる時間が長くなったり、作業の負担が増えてコストが上昇します。
コストは解体費用に反映されるため、建物以外の条件でも費用が高くなります。
建物解体の有無による土地売却額の違い

建物を解体する場合としない場合では、土地の売却額に多少の差が生じます。
解体の有無による違いは、次のとおりです。
| 建物解体の有無 | 売却金額 | 売却スピード |
|---|---|---|
| 解体する場合 | 土地の売却相場 | 早くなる |
| 解体しない場合 | 売却相場から少し下がる | 遅くなる |
土地に古家が残っていると新築後のイメージがしづらくなり、買い手の購入意欲がなかなか高まりません。
また、古家を残したまま引渡しすると、買主が解体費用を負担する必要があるため、購入の際に価格交渉をする買い手が増えます。
土地を売却する際に解体しておけば、買い手にとって購入しやすい物件になります。
土地売却前に建物を解体するメリット

土地売却前に建物を解体するメリットは、次のとおりです。
- 買主が購入後のイメージをしやすい
- 売却後の買主とのトラブルを防げる
- 解体費用を経費に計上できる
それでは、解体のメリットについて解説します。
買主が購入後のイメージをしやすい
更地になると買主が購入後のイメージをしやすくなり、購入判断が早くなります。
建物が残っていると日当たりの程度や、土地の奥行きを確認できません。
確認事項の調査が終わらない場合、新築の配置や間取り、窓の位置などがイメージできず、不安な気持ちを解消できません。
更地であれば隣地の建物の状態や窓の位置など、購入に必要な事項がすぐに確認でき、次のステップに進みやすくなります。
早く売却できれば売却資金を次の用途に活用しやすくなり、土地管理の負担も軽減できます。
売却後の買主とのトラブルを防げる
建物を解体して売買する場合、売却後の買主とのトラブルを防げます。
売主は引渡しした不動産について、一般的に契約不適合責任を負います。
契約不適合責任とは、契約書に引渡しすると記載した商品よりも低い品質のものを引渡しした場合に負う責任です。
たとえば、シロアリの被害がないとして契約した後、引渡し直後に被害が発覚した場合、損害賠償請求や補修を要求される可能性があります。
買主とのトラブルの原因を減らすことができれば、金銭的、精神的な負担を負うリスクを低減できます。
解体費用を経費に計上できる
解体費用は経費に計上できるため、譲渡所得税の節税が可能です。
譲渡所得税は、次の計算方法で求めます。
(1)収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除 = 課税譲渡所得
(2)課税譲渡所得 × 税率 = 譲渡所得税
解体費用は譲渡費用として計上でき、課税譲渡所得を軽減する役割を果たします。
なお、解体費以外にも次の費用が譲渡費用として計上できます。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 登記費用 など
上記のような費用や解体費などの譲渡費用を上手に活用して、節税につなげましょう。
参照元:国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
土地売却前に建物を解体するデメリット

土地売却前に建物を解体するデメリットは、次のとおりです。
- 固定資産税が高くなる
- 解体費用をローンに含めると金利が高い
それでは、解体のデメリットについて解説します。
固定資産税が高くなる
住宅を解体すると、土地の固定資産税が高くなります。
土地上に住宅が存在する場合、固定資産税の住宅用地の課税標準の特例が適用されています。
| 区分 | 土地の固定資産税 | |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 住宅用地で200㎡までの部分 | 課税標準額 × 1/6 |
| 一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 課税標準額 × 1/3 |
特例の適用を受けている土地の固定資産税は、最大で6分の1に軽減されます。
解体すると特例の適用が受けられなくなり、住宅を壊した年の翌年度から土地の固定資産税が高くなります。
参照元:総務省 固定資産税
解体費用をローンに含めると金利が高い
解体に関するローンは金利が高く、返済を負担に感じる場合もあります。
| ローンの名称 | 金利 | 返済期間 |
|---|---|---|
| 解体ローン | 3.0%前後 | 10年以内 |
| 住宅ローン | 0.6%~ | 35年以内 |
住宅ローンと比べると解体ローンは金利が高く、返済期間が短い融資です。
借入金額が少なくても月々の返済額が高くなる傾向にあり、金銭的な負担が大きくなります。
解体資金が用意できない場合は、不動産会社と相談し古家付き土地として売り出しましょう。
解体が必要な土地の売却相談はファンズ不動産へ
古家付きの土地を売却する際、解体費用がどれくらいかかるのかは、多くの方が不安に感じるポイントです。建物の構造や大きさ、周辺環境によって費用は大きく異なり、場合によっては思った以上の出費になることもあります。
また、条件を満たせば確定申告で経費や控除の対象になるケースもあり、正しい知識を持つことが重要です。売却をスムーズに進めるためには、早めに専門家へ相談して現状を整理しておくと安心です。
ファンズ不動産では、解体が必要な土地に関する相談にも丁寧に寄り添い、状況に合わせた進め方を一緒に検討できます。
オンライン面談から開始。LINEで完結する売却プロセス
ファンズ不動産での売却活動は、忙しい方でもストレスなく進められる「手軽さ」が特徴です。
最初の相談は店舗に出向く必要のない「オンライン面談」からスタートします。その後の担当者とのやり取りや進捗確認も、主にLINEでおこなうため、日中の時間を拘束されません。
仕事や家事で忙しい方でも、自身のペースで効率的に売却活動を進めたい方に最適です。
売却査定から引渡しまで、安心のワンストップ対応
ファンズ不動産は、LINEを活用した効率的なプロセスと、幅広い専門知識でスムーズな不動産売却を実現します。
相談は「オンライン面談」から始まり、やり取りもLINEメインでおこなうため、店舗へ足を運ぶ手間も最小限です。
また土地のプロやリノベーションの専門家も在籍しているので、専門知識が必要な相談も窓口一つで完結します。忙しい方でも、スムーズで安心な売却活動が可能です。
日中は仕事で時間が取れない方や、複雑な手続きをまとめて任せたい方でも、ストレスなく売却活動を進められます。
購買意欲の高いユーザーへ能動的にアプローチできる
ファンズ不動産が運営する「SNS不動産®」は、LINEで購買意欲の高いユーザーに不動産情報を届けます。
従来のポータルサイトで「待つ」のではなく、1万人超のLINE登録者へ能動的にアプローチできる点は大きな強みです。
さらに都心に精通した担当者が的確な売却戦略でサポートするため、物件の魅力を最大限に引き出す価格設定と販売活動がおこなえるでしょう。
購買意欲の高いユーザーへ「届ける」力と、物件価値を引き出す「専門家の戦略」が組み合わさることで、「高く・早く」売却できる可能性を最大化できます。
土地売却前の建物解体の見極め方

土地上に建物が存在していたとしても、売却前に必ずしも解体する必要はありません。
建物を解体すべきケース、解体すべきではないケースを確認し、必要な場合に応じて建物を壊しましょう。
建物を解体すべきケース
土地売却時に建物を解体すべきケースは、次のとおりです。
- 早く売却したい
- 建物の状態が悪い
- 解体費用が安く済む
更地にすると買い手は解体費用を支払わずに済むため、資金計画が立てやすくなり、購入判断が早くなります。
また、解体すれば建物の契約不適合責任を負う必要がなく、買い手とのトラブルを防ぎやすくなります。
解体費用が安く済む場合、早期売却やトラブル回避のために解体を検討しましょう。
建物を解体すべきでないケース
土地売却時に建物を解体すべきでないケースは、次のとおりです。
- 建物がまだ利用できる
- 条件がよく解体せずに売れる
- 買取りを検討している
建物がまだ利用できる状態、条件がよく古家付きのままでも売却できる土地なら、解体せずに売れる可能性があります。
また、買取業者によっては建物を解体しなくても買取りする会社があります。
条件がよくすぐに売却できる場合、買取を検討している場合は解体せずに売却するのも方法のひとつです。
土地売却時の解体費用や税金の負担を軽減する方法
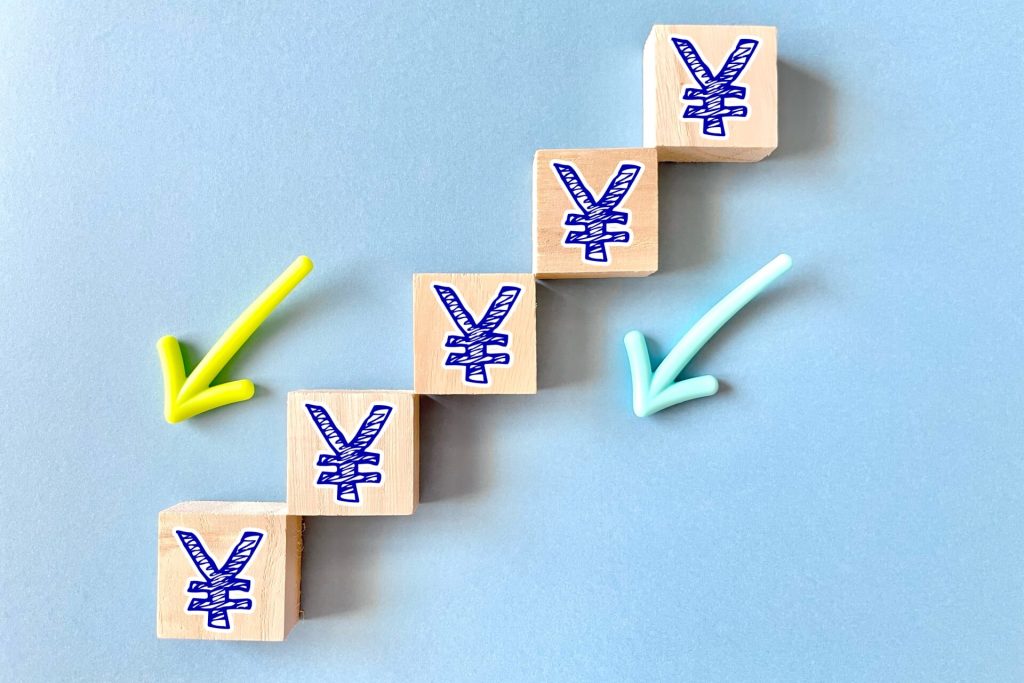
土地売却時の解体費用や税金の負担を軽減する方法は、次のとおりです。
- 自治体の補助金・助成金制度を確認する
- 複数の解体業者に見積もりを依頼する
- 税金の控除制度を活用する
- 残置物や不用品を事前に撤去しておく
- 固定資産税と解体タイミングに注意する
負担を軽減する方法を実践して、手元に残る資金を増やしましょう。
自治体の補助金・助成金制度を確認する
自治体の補助金や助成金の制度を活用すれば、解体費用を抑えられます。
たとえば、東京都江東区では1981年5月31日以前に建築された、耐震性の低い木造の建物を解体する場合、最大で100万円の補助が受けられます。
自治体によっては制度の利用条件が異なる場合もあれば、そもそも制度自体がない場合もあるため注意が必要です。
補助金制度や助成金制度の利用を検討する場合、まずは自治体の公式サイトなどで制度内容を確認しましょう。
複数の解体業者に見積もりを依頼する
複数の解体業者に見積もりを依頼すれば、金額や工事内容を比較でき、相場より高い会社への発注を防止できます。
解体費用は建物の構造や土地の状況によって変わるうえ、依頼先の解体業者によっても変動します。
見積もりが相場より高い解体業者もあるため、複数の見積もりを比較して相場を把握することが大切です。
また、見積もりを比較する際は、工事内容に漏れがないか、あいまいな表記でないか確認しましょう。
漏れやあいまいな表記があると、追加で費用を請求されるリスクが高まるため注意が必要です。
税金の控除制度を活用する
解体費用を譲渡費用として計上してもなお譲渡所得が生じる場合、税金の控除制度を活用して節税を図りましょう。
| 控除制度の名称 | 控除可能額 |
|---|---|
| 収用等により土地建物を売ったときの特例 | 5,000万円 |
| マイホームを売ったときの特例 | 3,000万円 |
| 被相続人の空き家を売却したときの特例 | 3,000万円または2,000万円 |
控除制度を活用すれば、譲渡所得を大幅に減らせます。
ただし、それぞれの制度には利用するための条件が定められています。
条件に該当するか調査する際は、国税庁公式サイトの各制度のページを見て確認しましょう。
残置物や不用品を事前に撤去しておく
建物内の残置物や不要品を事前に撤去しておけば、解体費用を抑えられます。
残置物などの撤去は、解体業者に依頼できますが、自身で撤去した場合と比べて高くなるため注意が必要です。
自身で撤去すれば行政サービスを利用して格安で処分できますが、解体業者が処分する場合、一般廃棄物処理業者に委託しなければならず処分費用がかかります。
撤去する時間が確保できる場合は、自身で撤去して解体費用を抑えましょう。
固定資産税と解体タイミングに注意する
住宅を解体すると土地の固定資産税が高くなるため、解体のタイミングには注意しましょう。
土地上の住宅を解体すると、土地の固定資産税が最大で6倍になります。
解体した年の翌年1月1日から土地の固定資産税が上がるため、壊した日からその年の年末までに買主へ引渡ししましょう。
引渡し時期の調整は売主のみではできないため、不動産会社にスケジュール調整してもらうことが大切です。
土地売却時の解体費用を経費にする場合の注意点

土地売却時の解体費用を経費にする場合の注意点は、次のとおりです。
- 土地売却のための解体が条件
- 解体後1年以内の売却は譲渡費用として計上できない場合がある
それでは、解体費用を経費にする場合の注意点について解説します。
土地売却のための解体が条件
解体費用を経費に計上するためには、前提として土地を売却するための解体であることが条件となります。
国税庁公式サイトでは、譲渡費用について次のように表記されています。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
引用:国税庁 No.3255 譲渡費用となるもの
解体の目的が土地や建物を売るためではない場合、譲渡費用として計上できません。
たとえば、土地を貸す、倒壊のおそれがあるなどの理由で解体した場合、譲渡費用として認められない可能性があります。
解体後1年以内の売却は譲渡費用として計上できない場合がある
土地を売却するために建物を壊したとしても、譲渡費用として計上する場合、解体から1年以内に売買契約を締結する必要があります。
譲渡費用に計上できる期間についての定義は存在しませんが、譲渡所得に関連する特例には次のような記述があります。
その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
引用:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例
マイホームを売ったときの特例以外にも、軽減税率の特例にも同じ表記が見られるため、解体から1年以内の売買契約締結が基準となっていると推測されます。
譲渡費用として計上できないと譲渡所得税の節税ができなくなるため、解体工事は売買契約の締結日を見越しておこないましょう。
土地売却で解体費用が支払えないときの対処法

土地売却時に解体費用を支払えない場合、次の対処法を実践しましょう。
- 古家付き土地で売る
- 買取業者に依頼する
それでは、解体費用を支払えないときの対処法について解説します。
古家付き土地で売る
解体費用が支払えない場合、古家付き土地として売りましょう。
土地上にある建物を利用できる場合、中古住宅として売却が可能です。
また、利用できない建物だったとしても、買い手が解体費用を負担する場合もあります。
ただし、買い手が解体費用を負担する場合、相場よりも低い売却価格になる可能性があります。
不動産会社から査定を受ける際、古家付き土地の場合、どの程度価格が下がるのか確認することが大切です。
買取業者に依頼する
解体費用が支払えず、かつ土地を素早く現金化したい方は買取業者の利用を検討しましょう。
買取業者は不動産のプロであり、利用できない建物がある土地を購入しても、自社で解体や工事をして売却するノウハウを持っています。
土地の現状に関係なく、ビジネスチャンスがあると判断すれば古家付き土地でも購入します。
また、買取業者が買主となるため、新たに買い手を探す時間がかかりません。
買取業者によっては1週間程度で現金化できる場合もあるため、すぐに現金を手に入れたい方にもおすすめの売却方法です。
土地売却時の解体費用に関するよくある質問

土地売却時の解体費用に関するよくある質問は、次のとおりです。
- 解体費用は買主と売主のどちらが負担する?
- 解体費用が買主負担になるケースとは?
- 確定申告時の解体費用の仕訳方法は?
それでは、よくある質問とその回答を紹介します。
解体費用は買主と売主のどちらが負担する?
買主と売主のどちらが負担するかは、ケースによって異なります。
一般的に、建物の所有者である売主が解体費用を負担して建物を壊しますが、費用を支払う余裕がない場合もあるでしょう。
解体費用を負担できないときには、買主に費用を負担してもらうことも可能です。
ただし、買主に解体費用を負担してもらう場合は、その分価格交渉を受ける可能性があるため注意が必要です。
解体費用が買主負担になるケースとは?
解体費用が買主負担になる主なケースは、次のとおりです。
- 売主が解体費用を支払えない
- 買主が建物を利用する
- 買取業者が買取りする
必ずしも売主が解体する必要はなく、状況によっては買主が費用を負担します。
ただし、買主が費用を負担する場合は解体費用を譲渡費用として計上できず、譲渡所得税の節税が難しくなる点に注意しましょう。
確定申告時の解体費用の仕訳方法は?
確定申告時の解体費用の仕訳方法は、解体する目的によって異なります。
| 目的 | 借方の記入例 | 貸方の記入例 |
|---|---|---|
| 取り壊しのみが目的 | 固定資産除却損 | 普通預金 |
| 建て替えが目的 | 固定資産除却損 | 建物 |
| 売却が目的 | 土地 | 普通預金 |
| 建物の復旧にともなう一部解体が目的 | 修繕費 | 普通預金 |
目的に応じた勘定科目で仕訳をおこない、正確な内容で確定申告をしましょう。
まとめ

土地上に建物がある場合、解体するかどうかで売却金額や売却スピードに違いが出ます。
解体したほうが早く高く売れる可能性が高くなるものの、解体費用が発生します。
解体費用は決して安くはないため、費用を抑える方法を実践したり、税金などの他の費用を抑えることが大切です。
また、取り壊す必要がない場合もあるため、解体するかどうかは不動産会社と相談しながら進めるのをおすすめします。
専門家に相談すれば解体の必要性のみでなく、信頼できる解体業者も紹介してもらえるでしょう。













