「土地を売却するとき、手元にどのくらいお金が残るの?」と、売却後に実際に手元に残る金額が気になる方も多いでしょう。
手元に残る金額は、売却金額から諸費用と税金を差し引いて計算します。
ただし、諸費用や税金の金額は売却金額や土地の状況によって変わるため、費用の内訳とあわせて計算方法も理解しておかなければなりません。
手元に残る金額を知るためには、まずその計算方法を理解することが大切です。
本記事では、土地を売却するときの手元に残る金額の計算方法や発生する費用と税金、節税する方法について解説します。
土地売却で手元に残る金額の計算方法

手元に残る金額を知るためには、まず計算方法を把握する必要があります。
また、譲渡所得税が発生する条件を理解しておかないと、正確な金額を計算できません。
まずは手元に残る金額の計算方法、譲渡所得税の発生条件について解説します。
売却価格から諸費用・経費を差し引く
土地を売却したときの手元に残る金額は、次の計算式で求めます。
手元に残る金額 = 売却金額 – 諸費用や経費の金額
売買契約を締結した後であれば簡単に計算できますが、売却する前に金額を知る場合、土地の価格相場を把握する必要があります。
土地の相場を間違えた場合、手元に残る金額が変わるため注意が必要です。
正確な金額を知りたい方は、不動産会社の査定を受け、相場を確認してから計算しましょう。
売却益がある場合は税金が発生する
売却益(譲渡所得)が生じた場合、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税を計算する際は、次の計算式を利用します。
(1)譲渡所得 = 収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)
(2)課税譲渡所得 = 譲渡所得 – 特別控除
(3)譲渡所得税 = 課税譲渡所得 × 税率
計算式で用いている各単語の内容は、次のとおりです。
| 収入金額 | 売却金額 |
|---|---|
| 取得費 | 売却した土地を購入したときの代金や諸費用、税金の合計額 |
| 譲渡費用 | 土地を売却したときに支払った諸費用と税金の合計額 |
税金が課される場合、売却金額から諸費用と税額を差し引いて、手元に残る金額を計算します。
参照元:国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
土地売却時に発生する費用

土地売却時に発生する費用は、次のとおりです。
| 費用の名称 | 概要 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 売買契約が成立した際に支払う報酬 |
| 司法書士報酬 | 登記手続きの代行費用 |
| 解体費用 | 建物の解体にかかる費用 |
| 測量費用 | 土地の面積を確定させるための費用 |
それでは、それぞれの費用について解説します。
仲介手数料
仲介手数料は、不動産仲介会社に対して支払う報酬です。
計算する際は、次の計算式を用います。
| 計算式 | 利用条件 |
|---|---|
| 仲介手数料 = 売買金額 × 3% + 6万円 | 売買金額が400万円を超える場合 |
| 仲介手数料 = 売買金額 × 4% + 2万円 | 売買金額が200万円を超え400万円以下の場合 |
| 仲介手数料 = 売買金額 × 5% | 売買金額が200万円以下の場合 |
たとえば、土地を5,000万円で売却した場合、次のように求めます。
5,000万円 × 3% + 6万円 = 156万円(仲介手数料)
※料率(税抜)
仲介手数料は、不動産仲介会社に対して売買契約時と引渡し時にそれぞれ半額ずつ、または引渡し時に全額を支払います。
司法書士報酬
司法書士報酬は、登記申請の代行を依頼する際に発生する費用です。
売主の場合、抵当権抹消登記や住所変更登記の代行が主な司法書士の業務となります。
抵当権抹消登記や住所変更登記の代行を依頼する際の費用目安は、1件につき2万円前後です。
登記する際には登録免許税の納付も必要となるため、引渡し時に司法書士報酬と登録免許税額を司法書士に渡します。
なお、司法書士報酬と登録免許税の合計金額を登記費用と呼びます。
解体費用
解体費用は、売却する土地上にある建物やブロック塀、樹木などの撤去費用です。
解体する建物の構造や土地の状況、残置物の量などによって価格が変動します。
目安となりますが、建物の構造の違いによる費用は次のとおりです。
| 木造 | 3万円~5万円/坪 |
|---|---|
| 鉄骨造 | 4万円~6万円/坪 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 5万円~8万円/坪 |
解体費用は着手金や中間金、残代金など、複数回に分けて支払います。
また、費用の支払い時期は、一般的に解体工事の着手時や工事完了後1週間以内などに設定されます。
測量費用
測量費用は、土地の境界線や面積を確定する際に土地家屋調査士へ支払う費用です。
測量費用は、一般的に40万円〜80万円かかります。
測量費用の目安に幅があるのは、土地ごとに必要な作業量が大きく異なるためです。
隣地所有者が国や県で打ち合わせが何回も必要な土地の場合、隣地所有者が何十人にもおよぶ土地の場合など、手続きの多さによって費用が高くなります。
費用に大きな差が出るため、正確な測量費用を知りたい場合は土地家屋調査士に見積もりを依頼しましょう。
土地売却で発生する税金

土地を売却した際に発生する税金は、次のとおりです。
| 税金の名称 | 概要 |
|---|---|
| 譲渡所得税 | 譲渡所得(売却益)が生じた際に課される税金 |
| 印紙税 | 課税文書を作成する際に課される税金 |
| 登録免許税 | 登記申請の際に課される税金 |
| 消費税 | 物やサービスを消費する際に課される税金 |
それでは、各税金について解説します。
譲渡所得税
譲渡所得税は譲渡所得が生じた際に課される税金です。
譲渡所得が生じた場合、次の税率を掛けて税額を計算します。
| 長短区分 | 所有期間5年以下 (短期譲渡所得) | 所有期間5年超 (長期譲渡所得) |
|---|---|---|
| 税率 | 39.63% | 20.315% |
上記のとおり、土地の所有期間によって税率が異なるため、不動産を取得して5年以下の方は注意が必要です。
なお、譲渡所得税は所得税と復興特別所得税、住民税から構成されています。
所得税と復興特別所得税は売却した年の翌年2月16日から3月15日までに税務署へ納付し、住民税は翌年6月以降に自治体へ納付します。
参照元:国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
印紙税
印紙税は課税文書を作成する際に課される税金です。
土地売却時に作成する課税文書の代表例は、不動産売買契約書です。
課税額は次の表のとおり、売買金額によって異なります。
| 売買金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 100万円超から500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超から1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超から5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超から5億円以下 | 6万円 |
※2027年3月31日までに作成する売買契約書に適用される税額
印紙税は課税文書に収入印紙を貼り、割印したうえで納付します。
収入印紙は郵便局や法務局、市町村で販売されているため、売買契約締結前に購入しておきましょう。
参照元:国税庁 印紙税額
登録免許税
登録免許税は登記を申請する際に課される税金です。
売主が負担すべき登記は、抵当権抹消登記と住所氏名変更登記です。
| 抵当権抹消登記 | 融資を利用する際に設定した担保(抵当権)を消す登記 |
|---|---|
| 住所氏名変更登記 | 登記事項証明書に記載された所有者の住所や氏名を変更する登記 |
住宅ローンを借りたときに設定した抵当権が土地に残っている場合、引渡し時に抵当権抹消登記を申請する必要があります。
また、登記事項証明書に記載されている所有者の住所、氏名を正確な情報に変更するため、引渡し時に住所氏名変更登記を申請しなければなりません。
どちらの登記も1件申請するごとに1,000円の登録免許税が課されます。
登録免許税は税額が3万円以下の場合、税額分の収入印紙を台紙に貼り、登記申請時に法務局に提出します。
消費税
消費税は日本国内で物やサービスを消費した際に課される税金です。
土地を売却する際に、消費税が課税される物やサービスは次のとおりです。
- 仲介手数料
- 司法書士報酬
- 解体費用
- 測量費用
消費税が課される物やサービスを消費した際は、10%の消費税が課税されます。
たとえば、200万円の仲介手数料を支払う場合、20万円の消費税を上乗せして不動産会社に渡す必要があります。
なお、土地の売却は非課税取引にあたるため、土地の売却代金に消費税は課されません。
固定資産税の清算金
土地の引渡し時、売主は固定資産税の精算金を受け取れます。
引渡し日の前日までは売主が、引渡し日以降は買主が負担するのが一般的なため、日割り計算で清算します。
どのように精算されるかの一例は、次の表を参考にしてください。
| 固定資産税が20万円の場合:計算式20万円×所有日数÷365 | ||
|---|---|---|
| 売却年の所有期間 | 金額 | |
| 売主 | 1月1日〜6月30日(181日) | 99,178円 |
| 買主 | 7月1日〜12月31日(184日) | 100,822円 |
固定資産税は、1月1日時点で不動産を所有している方に毎年課される税金で、不動産を売却したとしても売主に納付義務があります。
清算金の金額は不動産会社が計算してくれるため、不明点がある場合や金額を知りたい方は担当者に確認しましょう。
土地売却で手元に残る金額をシミュレーション
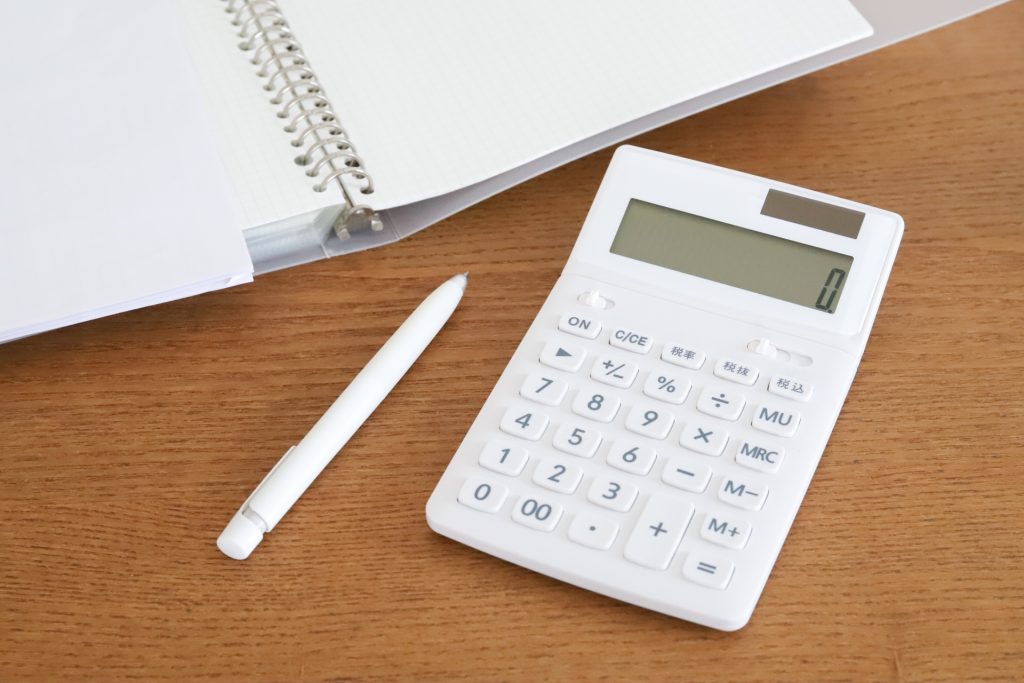
手元に残る金額を、次の条件をもとにしてシミュレーションします。
| 売却金額 | 5,000万円 |
|---|---|
| 解体費用 | 200万円 |
| 測量費用 | 50万円 |
| 司法書士報酬 | 5万円 |
| 抵当権設定 | あり(1件) |
| 取得費 | 2,000万円 |
| 所有期間 | 15年(長期譲渡所得) |
最初に諸費用の合計額を計算します。
【仲介手数料の計算】
売却金額 × 3% + 6万円 × 1.1 = 仲介手数料(税込)
5,000万円 × 3% + 6万円 × 1.1 = 171万6,000円
【諸費用の合計】
仲介手数料 + 解体費用 + 測量費用 + 司法書士報酬 = 諸費用の合計
171万6,000円 + 200万円 + 50万円 + 5万円 = 426万6,000円(諸費用の合計)
諸費用の合計を計算した後は、税額の合計を求めます。
【印紙税の確認】
売却金額5,000万円の場合、1,000万円超え5,000万円以下に該当するため印紙税は1万円
【登録免許税の計算】
抵当権抹消登記の件数 × 1,000円 = 登録免許税
1件× 1,000円 = 1,000円(登録免許税)
【譲渡費用の計算】
諸費用の合計 + 印紙税 + 登録免許税 = 譲渡費用
426万6,000円 + 1万円 + 1,000円 = 427万7,000円(譲渡費用)
【課税譲渡所得の計算】
収入金額 -(取得費 + 譲渡費用) = 課税譲渡所得
5,000万円 -(2,000万円 + 427万7,000円)= 2,572万3,000円(課税譲渡所得)
【譲渡所得税の計算】
課税譲渡所得 × 税率 = 譲渡所得税
2,572万3,000円 × 20.315% = 約522万円(譲渡所得税)
【税額の合計】
印紙税 + 登録免許税 + 譲渡所得税 = 税額の合計
1万円 + 1,000円 + 約522万円 = 約523万1,000円(税額の合計)
諸費用の金額と税額を計算した後は、手元に残る金額を求めます。
【手元に残る金額の計算】
売却金額 – (諸費用の合計 + 税額の合計)= 手元に残る金額
5,000万円 -(426万6,000円 + 約523万1,000円)= 約4,050万3,000円(手元に残る金額)
シミュレーションの条件で計算した場合、手元に約4,050万3,000円残ります。
土地売却で手元に残る金額を増やす方法

手元に残る金額を増やす方法は、次のとおりです。
- 売却価格を上げる
- 売却するタイミングを見極める
- 測量費用を抑える工夫をする
- 譲渡所得税を控除できる特例を活用する
手元に残る金額を増やすための方法を実践し、諸費用や税金の負担を抑えましょう。
売却価格を上げる
売却価格を上げれば、手元に残る金額が増加します。
諸費用や税金などの支出を抑えられない場合、売却金額を上げて手元に残る金額を増やします。
ただし、売却金額を上げる場合は、事前に土地の相場を確認しましょう。
不動産には相場があり、相場よりも高い金額で売り出してもなかなか売却できません。
売却できないと草刈りや固定資産税など、ランニングコストがかかり続けるため、相場を不動産会社に確認してから売却価格を上げましょう。
売却するタイミングを見極める
土地を売却するタイミングを見極めれば、譲渡所得税の節税が可能です。
売却する年の1月1日現在で所有期間が5年を超えてる場合、長期譲渡所得の税率が適用されます。
長期譲渡所得の税率は20.315%と、短期譲渡所得の39.63%よりも低い税率です。
たった1日で税率が20%近く変わる場合もあるため、土地を売却する前に長期譲渡所得と短期譲渡所得のどちらが適用されるのかを確認しましょう。
測量費用を抑える工夫をする
測量費用は工夫次第で金額を抑えられます。
土地の境界線が不明瞭な場合は測量する必要がありますが、次のように確定測量か簡易測量かで大きく費用が異なります。
| 測量の種類 | 相場 |
|---|---|
| 確定測量 | 40〜60万円 |
| 簡易測量 | 10〜30万円 |
上記のとおり簡易測量で済むのであれば費用を抑えられるため、あらかじめ不動産業者や業者に確認する必要があります。
また、複数の測量業者に見積もりを依頼して、よく比較検討するのもコストを抑えるのに効果的です。
譲渡所得税を控除できる特例を活用する
譲渡所得が発生しても、控除できる特例を活用すれば譲渡所得税を節税できます。
節税につながる主な控除できる特例は、次のとおりです。
| 特例の名称 | 控除額 |
|---|---|
| 収用等により土地建物を売ったときの特例 | 5,000万円 |
| マイホームを売ったときの特例 | 3,000万円 |
| 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 | 3,000万円または2,000万円 |
特例を利用すれば、特例に応じた額を譲渡所得から控除できます。
なお、特例の適用を受けるためには、その特例に定められた条件を満たす必要があります。
条件を確認する際は、税務署や税理士に相談し、適用を受けられるか確認しましょう。
土地売却で手元に残る金額を増やすために利用できる特例

手元に残る金額を増やしたい場合、次の特例の利用を検討しましょう。
- マイホームを売ったときの特例
- マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
それでは、それぞれの特例について解説します。
マイホームを売ったときの特例
マイホームを売ったときの特例を利用すれば、譲渡所得から3,000万円を控除できます。
特例を利用するためには、次の条件を満たす必要があります。
- 現に利用している自宅を売却
- 解体してから一定期間内に売買契約を締結する
- 自宅の退去後、一定期間内に売却
土地を売却して生じた譲渡所得が3,000万円以下の場合、本特例の適用を受ければ譲渡所得税は課税されません。
譲渡所得が生じた際に大きな節税効果を生むため、土地を売却するときは国税庁公式サイト「マイホームを売ったときの特例」で条件の詳細を確認してください。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
マイホームを売ったときの軽減税率の特例を受ければ、長期譲渡所得よりも低い税率が適用されます。
軽減税率の特例を利用するためには、次の条件を満たさなければなりません。
- 所有期間10年を超えた自宅を売却
- 過去3年間に本特例の適用を受けていない
- 夫婦や親子など特別な関係の方への売却ではない
特例を利用すれば、次の税率が適用されます。
| 軽減税率の特例 | 14.21%(課税譲渡所得6,000万円以下の部分) 20.315%(課税譲渡所得6,000万円超の部分) |
|---|---|
| 所有期間5年超 (長期譲渡所得) | 20.315% |
税率が下がれば譲渡所得税の課税額も減るため、土地売却の際は国税庁「軽減税率の特例」のページで適用を受けられるか確認してください。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を利用すれば、納付した相続税の一部を取得費に計上できます。
特例の主な利用条件は、次のとおりです。
- 相続や遺贈で受け継いだ不動産を売却
- 相続した不動産に相続税が課されている
- 相続開始日から3年10か月以内に売却
特例の適用を受ければ納付した相続税の一部を取得費に計上でき、譲渡所得を減らせます。
本特例は利用条件が少ないものの、取得費に計上できる相続税の計算方法が複雑です。
国税庁公式サイト「取得費の特例」を参照し、どの程度計上できるのか確認しておきましょう。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例の適用を受ければ、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
特例を利用するための条件は、次のとおりです。
- 被相続人が亡くなる直前に住んでいた自宅の売却
- 昭和56年5月31日以前の建物
- 一定以上の耐震性がある建物
控除額は相続人の数により変動し、3人未満なら一人あたり3,000万円、3人以上なら一人あたり2,000万円控除できます。
本特例を利用するための条件は多岐にわたるため、適用を受けられるかどうかは事前に「国税庁公式サイト」で確認してください。
土地売却後の手取り額に悩んだらファンズ不動産へ
土地を売却したあと、実際に手元に残る金額は「売却価格」だけでは判断できず、税金や手数料などさまざまな費用が関わります。
「結局いくら残るのか」「思っていたより少なくならないか」と不安に感じる方も少なくありません。正確な手取り額を把握しておくことで、資金計画が立てやすく、後悔のない売却につながります。
手取り額に悩んだときは、早めに専門家へ相談することで、状況に応じた見通しを確認できます。ファンズ不動産では、土地売却に伴う疑問や不安にも丁寧に寄り添い、よりよい判断をサポートできます。
オンライン面談から開始。LINEで完結する売却プロセス
ファンズ不動産での売却活動は、忙しい方でもストレスなく進められる「手軽さ」が特徴です。
最初の相談は店舗に出向く必要のない「オンライン面談」からスタートします。その後の担当者とのやり取りや進捗確認も、主にLINEでおこなうため、日中の時間を拘束されません。
仕事や家事で忙しい方でも、自身のペースで効率的に売却活動を進めたい方に最適です。
信頼度の高い買主とマッチングが可能
ファンズ不動産は、キュレーターの価値観に「共感」した、購買意欲の高いユーザーへ物件情報を届けます。
キュレーターは日頃からSNSで専門知識やライフスタイルを発信しており、人柄や実績が公開されています。
そのため単なる物件情報としてではなく、「あのキュレーターが勧める物件」という信頼度の高い情報として不動産情報を届けることが可能です。
情報発信のプロセスを介することで、物件の背景にあるストーリーや価値観を理解してくれる買主と出会う確率も高められるでしょう。
ぜひファンズ不動産で、物件への想いを共有できる「信頼できる買主」とのマッチングを実現してみましょう。
フォロワー数万人のキュレーターがあなたの物件を紹介
ファンズ不動産は、キュレーターのSNS発信を通じて「情報拡散力」と「信頼性」を掛け合わせ、物件の売却可能性を広げます。
例えば、同社キュレーターのJeremy Tsang氏は、Instagramで8万人以上(2023年9月時点)のフォロワーを有しています。
影響力の高い専門家が「おすすめできる家」としてSNSで紹介することは、キュレーターを信頼するフォロワーへの「価値ある情報」として届きます。
この独自の仕組みが、高い反響とスピーディーなマッチングを生み出す秘訣です。
土地売却で手元に残る金額に関するよくある質問

土地売却で手元に残る金額に関するよくある質問は、次のとおりです。
- 不動産売却時の手取り計算ツールはある?
- 土地売却にかかる税金はいつ支払う?
- 土地売却後に確定申告が必要?
それでは、よくある質問とその回答を紹介します。
不動産売却時の手取り計算ツールはある?
不動産売却時の手取り計算ツールを公開しているサイトはいくつもあります。
必要な項目を入力すると、手元に残る金額を簡単に計算できます。
ただし、取得費や譲渡費用を正確に入力する必要がある、特例を適用した結果が反映されないなどのデメリットもあるため、参考程度に利用しましょう。
入力項目を誤ったり、計算結果をそのまま鵜呑みにしたりすると、実際に手元に残る金額が異なる場合があります。
土地売却にかかる税金はいつ支払う?
土地売却にかかる税金の支払い時期は、次のとおりです。
| 税金の名称 | 支払い時期 |
|---|---|
| 譲渡所得税 | ・所得税と復興特別所得税は確定申告の期間 ・住民税は土地を売却した年の翌年6月以降 |
| 印紙税 | 売買契約締結時 |
| 登録免許税 | 引渡し時 |
| 消費税 | ・売買契約締結時(仲介手数料) ・引渡し時(司法書士報酬、仲介手数料、測量費用) ・工事完了時(解体費用) |
支払いのタイミングは税金によって異なります。
土地を売却する前に、各税金の支払い時期を把握し、必要な資金を準備しておきましょう。
土地売却後に確定申告が必要?
土地を売却した後、次の条件のいずれかを満たす場合は確定申告が必要です。
- 譲渡所得が生じた
- 特例を利用する
条件に該当する場合、土地を売却した年の翌年2月16日から3月16日までに確定申告する必要があります。
確定申告の際はさまざまな書類の準備が必要となるため、不動産会社や税理士に相談しながら申告手続きを進めましょう。
まとめ

土地売却時に手元に残る金額は、売却金額や土地の状況によって異なります。
仲介手数料は売却金額によって高額になり、解体費用は土地の立地によって高くなる場合もあります。
どのようなケースで費用が変動するのか把握したうえで、費用や税金の計算方法まで理解すれば、自身でも手元に残る金額の計算が可能です。
土地売却前に手元に残る金額がわかれば、将来の資金計画も立てやすくなります。
自身で計算した金額が正しいかどうか、不動産会社に確認してもらうことで、より正確な金額を把握できるでしょう。













